寺田寅彦の作に『秋の歌』という短い随筆がある。大正11年に書かれたもので、後に海軍に志願して職業軍人となる私の父が3歳の頃だ。
大正の後に続く昭和の戦争の歴史を学んだ私は、大正デモクラシーと呼ばれることになるこの時代の文化の質と深さに長く疑問を持ってきたが、この秋の静かな夜に寺田のこういう随筆に目をさらしていると、どうしても「ちょっと待てよ」という気持になる。どんな時代でも一つの時間区分の内容を、単純安易に評価してはやはりいけないのだ・・・という気持である。
戦争によって昭和前期に失った物や精神文化のうち、片方については戦後の昭和後期になっても更に平成の時代になっても取り戻すことができないでいる現代日本人の有様についても少々考えさせられる秋の夜長だ。
「・・・独り静かにこの曲の呼び出す幻想の世界にわけ入る。北欧の、果てもなき平野の奥に、白樺の森がある。歎くように垂れた木々の梢は、もう黄金色に色づいている。傾く夕日の空から、淋しい風が吹き渡ると、落葉が、美しい美しい涙のようにふり注ぐ。・・・」
こんなみごとな幻想的情景描写ができる作家が現代にいるだろうか・・・父がその青春前期に寺田寅彦を読み込んでいたら果たして軍人への道を選んだであろうか。
短編なので以下全文を掲載しておく。
----------
秋の歌
寺田寅彦
チャイコフスキーの「秋の歌」という小曲がある。私はジンバリストの演奏したこの曲のレコードを持っている。そして、折にふれて、これを取り出して、独り静かにこの曲の呼び出す幻想の世界にわけ入る。
北欧の、果てもなき平野の奥に、白樺の森がある。歎くように垂れた木々の梢は、もう黄金色に色づいている。傾く夕日の空から、淋しい風が吹き渡ると、落葉が、美しい美しい涙のようにふり注ぐ。
私は、森の中を縫う、荒れ果てた小径(こみち)を、あてもなく彷徨(さまよ)い歩く。私と並んで、マリアナ・ミハイロウナが歩いている。
二人は黙って歩いている。しかし、二人の胸の中に行(ゆ)き交(か)う想いは、ヴァイオリンの音になって、高く低く聞こえている。その音は、あらゆる人の世の言葉にも増して、遣(や)る瀬(せ)ない悲しみを現わしたものである。私がGの絃で話せば、マリアナはEの絃で答える。絃の音が、断えては続き続いては消える時に、二人は立止まる。そして、じっと眼を見交(みか)わす。二人の眼には、露の玉が光っている。
二人はまた歩き出す。絃の音は、前よりも高くふるえて、やがて咽(むせ)ぶように落ち入る。
ヴァイオリンの音の、起伏するのを受けて、山彦の答えるように、かすかな、セロのような音が響いて来る。それが消えて行くのを、追い縋りでもするように、またヴァイオリンの高音が響いて来る。
このかすかな伴奏の音が、別れた後の、未来に残る二人の想いの反響である。これが限りなく果敢(はか)なく、淋しい。
「あかあかとつれない秋の日」が、野の果に沈んで行く。二人は、森のはずれに立って、云い合わせたように、遠い寺の塔に輝く最後の閃光を見詰める。
一度乾いていた涙が、また止(と)め度(ど)もなく流れる。しかし、それはもう悲しみの涙ではなくて、永久に魂に喰い入る、淋しい淋しいあきらめの涙である。
夜が迫って来る。マリアナの姿はもう見えない。私は、ただ一人淋しく、森のはずれの切株に腰をかけて、かすかな空の微光の中に消えて行く絃の音の名残を追うている。
気がつくと、曲は終っている。そして、膝にのせた手のさきから、燃え尽した巻煙草の灰がほとりと落ちて、緑のカーペットに砕ける。
(大正十一年九月『渋柿』)
大正の後に続く昭和の戦争の歴史を学んだ私は、大正デモクラシーと呼ばれることになるこの時代の文化の質と深さに長く疑問を持ってきたが、この秋の静かな夜に寺田のこういう随筆に目をさらしていると、どうしても「ちょっと待てよ」という気持になる。どんな時代でも一つの時間区分の内容を、単純安易に評価してはやはりいけないのだ・・・という気持である。
戦争によって昭和前期に失った物や精神文化のうち、片方については戦後の昭和後期になっても更に平成の時代になっても取り戻すことができないでいる現代日本人の有様についても少々考えさせられる秋の夜長だ。
「・・・独り静かにこの曲の呼び出す幻想の世界にわけ入る。北欧の、果てもなき平野の奥に、白樺の森がある。歎くように垂れた木々の梢は、もう黄金色に色づいている。傾く夕日の空から、淋しい風が吹き渡ると、落葉が、美しい美しい涙のようにふり注ぐ。・・・」
こんなみごとな幻想的情景描写ができる作家が現代にいるだろうか・・・父がその青春前期に寺田寅彦を読み込んでいたら果たして軍人への道を選んだであろうか。
短編なので以下全文を掲載しておく。
----------
秋の歌
寺田寅彦
チャイコフスキーの「秋の歌」という小曲がある。私はジンバリストの演奏したこの曲のレコードを持っている。そして、折にふれて、これを取り出して、独り静かにこの曲の呼び出す幻想の世界にわけ入る。
北欧の、果てもなき平野の奥に、白樺の森がある。歎くように垂れた木々の梢は、もう黄金色に色づいている。傾く夕日の空から、淋しい風が吹き渡ると、落葉が、美しい美しい涙のようにふり注ぐ。
私は、森の中を縫う、荒れ果てた小径(こみち)を、あてもなく彷徨(さまよ)い歩く。私と並んで、マリアナ・ミハイロウナが歩いている。
二人は黙って歩いている。しかし、二人の胸の中に行(ゆ)き交(か)う想いは、ヴァイオリンの音になって、高く低く聞こえている。その音は、あらゆる人の世の言葉にも増して、遣(や)る瀬(せ)ない悲しみを現わしたものである。私がGの絃で話せば、マリアナはEの絃で答える。絃の音が、断えては続き続いては消える時に、二人は立止まる。そして、じっと眼を見交(みか)わす。二人の眼には、露の玉が光っている。
二人はまた歩き出す。絃の音は、前よりも高くふるえて、やがて咽(むせ)ぶように落ち入る。
ヴァイオリンの音の、起伏するのを受けて、山彦の答えるように、かすかな、セロのような音が響いて来る。それが消えて行くのを、追い縋りでもするように、またヴァイオリンの高音が響いて来る。
このかすかな伴奏の音が、別れた後の、未来に残る二人の想いの反響である。これが限りなく果敢(はか)なく、淋しい。
「あかあかとつれない秋の日」が、野の果に沈んで行く。二人は、森のはずれに立って、云い合わせたように、遠い寺の塔に輝く最後の閃光を見詰める。
一度乾いていた涙が、また止(と)め度(ど)もなく流れる。しかし、それはもう悲しみの涙ではなくて、永久に魂に喰い入る、淋しい淋しいあきらめの涙である。
夜が迫って来る。マリアナの姿はもう見えない。私は、ただ一人淋しく、森のはずれの切株に腰をかけて、かすかな空の微光の中に消えて行く絃の音の名残を追うている。
気がつくと、曲は終っている。そして、膝にのせた手のさきから、燃え尽した巻煙草の灰がほとりと落ちて、緑のカーペットに砕ける。
(大正十一年九月『渋柿』)










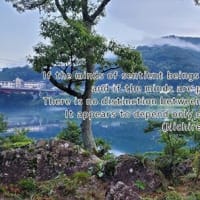
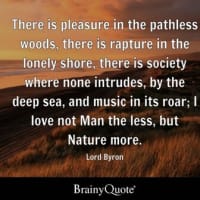
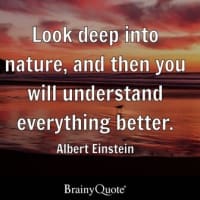







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます