
ヨットやウインドサーフィンなどのセーリングスメ[ツのほか多くの「風読みスメ[ツ」の一つとして、PPGにとっても「風を読む」ことは最も大切なことの一つです。 大気と共に移動するバルーン(気球)等を除いて、他の航空スメ[ツに比べてPPGの対気速度は非常に遅く(秒速10m前後)、わずかの風の変化でもその安定性や運動性に影響します。
時速300kmで飛行する航空機にとって時速30kmの風は地上との関係において10%の影響しか与えませんが、時速30kmのPPGにとっては100%影響します。例えばアップウインド(ヘッドウインド・アゲンストの風ともいう)で飛行する場合、航空機の対地速度は270km/時間を保てるのに対して、PPGの方は対地速度ゼロになるわけで、風上に向かってはまったく進めなくなります。
またPPGのテイクオフスピードは更に遅く秒速5m前後の上、フットランチ(足で助走しテイクオフする)ですから、わずかの風がテイクオフ・ランディングの難易を決定します。風を読む・・大気の状態を正しく把握することは、PPGにとって初めであり終わりであるとも言えるでしょう。
一般に「風」と言う場合、地面に対する大気の水平方向の運動のことですが、実際の風は様々な要因によって複雑な流れを形成しています。大気の流れがどのようなものであり、どのようにして生じるかについては別の章で触れるとして、ここではこの「風」を如何に「読む」かについて説明します。
風を見る
地球上の大気の大部分は窒素と酸素に水蒸気が混じったものであり本来無色透明です。その動きである「風」を直接目で見ることは出来ません。だから、まず風によって動かされている物体を見ることになります。
エアフィールドのTLゾーン(テイクオフ・ランディングゾーン)には吹き流し(ストリーマー・ウインドソックとも呼ばれる)が設置してありますから、まずこの傾き具合で風の方向、強さを推定します。
風が安定している時は、吹き流しは一定方向に向いてあまり動揺しません。ストリーマーの動きに落ち着きが無い時は、風も不安定だと考えます。
地上に存在する柔らかくて軽い物体は全て風と共に動こうとします。緑眩(まぶ)しい木々の葉のざわめきも大枝小枝のゆらぎも風の所産です。風に上昇成分がある時は、山の斜面の木々の葉っぱはその裏側を見せるため全体的に色が淡くなります。桜の花の散る4月の晴天には、上昇風に乗って花吹雪が舞うのを見る機会もあるでしょう。植林地帯の杉林は繁殖期にまとまって花粉を放出し、うす緑色のもやのようなものが風に乗って移動します。
風は海や川の水面に風紋を作ります。小さな風紋が小波になり来し方の距離が長ければ徐々に成長して大きな波になります。海上の波の様子を観察していると、風の強さ、方向、どのくらい遠い所から吹いているか(吹走距離)、強くなるのか、弱まるのかが推定できます。
鳥たちも風を教えてくれます。特にトンビなどのソアリング(滑翔:かっしょう)を見ていると、サーマルの場所、上空の風の流れが良く分かります。彼らにも好みの風や気象があるように思われます。彼らがいつ、どのような時に飛行し、飛行しないのかを詳しく知ることが出来れば、飛行速度が似通ったPPGのフライト条件の決定にも大いに役立つでしょう。
煙突から出る煙は格好の風見です。また大気中の水蒸気が凝結して出来る雲の態様や動きもそれぞれの高度での風の状態をはっきり示してくれます。
計器を使う
風速計を使うと、いかに大気が常に変動しているかを知ることができます。気象庁で採用している毎時の風速の出し方は、過去10分間の平均風速ですが、エリアでの風速で大事なのは瞬間最大風速です。
大気が不安定な時ほど、最小と最大の幅が大きくなります。一定時間継続的に数値を観察し、およその平均風速を推定すると共に、最も大きな数値に注意をしなければなりません。瞬間最大風速とは多くの場合、危険な突風を意味するからです。
また、大気密度(密度高度)を決定する3つの要素、大気圧、温度、湿度はおおよそその日の天気図で知ることができます。大気密度はPPGではグライダーに作用する揚力、抗力に影響するだけでなく、ユニットの出力=推力に直接的に影響しますから、非常に大切な要素になるので後に詳しく触れます。
風を聞く
風は変化します。特に地上の近くでは地形や熱源の影響を受けて風は変化します。風見のある場所の風が必ずしも自分の位置する場所の風とは限りません。
自分が今いる場所の風を知るためには、自分自身を風見にする必要があります。
まず、風の音を聞いてみましょう。両耳に神経を集中して風の音を聞きます。風に向かうと「ゴー」と言う音が聞こえるはずです。左右に頭を動かすと音が強くなったり弱くなったりします。もっとも大きく聞こえる方向が風が吹いてくる方向です。
人間の感覚は、訓練すればどんどん鋭敏になります。慣れてくると0、数mという弱い風でもかなり正確に風の方向を知ることが出来るようになります。
風を感じる
風には匂いがあり、肌触(はだざわ)りもあります。山から吹く風は山の匂いを含み、海を渡ってくる風は潮の香り含んでいます。風は絶えず移動するものであり、旅の道中に出会ったものたちの残り香を漂わせているものです。
また湿度の高い風はじっとりとした肌触りを生み、乾燥した風はさらっとしていることは言うまでもないでしょう。
後に触れますが、温度・湿度は大気密度を決定する上での重要な要素の一つです。
感覚を総動員する
ともかく体全体を使うこと。大きく大気を吸い込みながら、目で見、耳で聞き、鼻で嗅ぎ、肌で感じる。自分の持っている全ての感覚を使って、その大気の中に含まれる情報を探って下さい。
こうして常にフライト前に風を読み、予測する訓練を重ねるにつれて、その後のフライトとの関連の中でその風がどういう意味を持っているのかが徐々に分かるようになってきます。
この自然界の現象は、どんな些細(ささい)なことも全部互いに関連し合いながら存在し運動していることを忘れてはいけません。










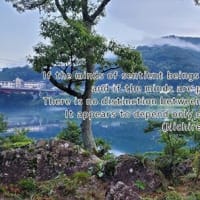
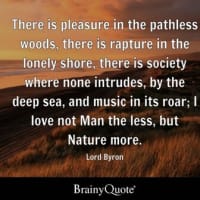
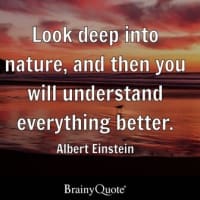







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます