もう9月だ。あれほど元気だったクマゼミのジャージャーが夕方のミンミンやツクツクに替わった。毎年確実に季節が推移して行く。今年も秋が近い。
再び、時間について考える。時間とは一体何か。
時計を見る。秒針がコツコツ動いている。これが1回転すると分針が一つ進み、分針が1回転すると時針が一つ進み。時針が2回転すると1日が進む。とりあえず、これが最も身近な時間の捉え方だが、実はこれは利便上、人間が作った単なる一つのモノサシしにすぎない。
小は我が心臓の鼓動や呼吸、大は地球の自転やら公転やら小宇宙の回転やら、更に大きな銀河団の動きやら・・・規則的リズムを奏でながら絶えず運動を続けているこの世界のありさまを、人間の感覚で測れるように工夫して作った道具の一つだ。
時計の進行は余りに確実な物理的事実で、小さい頃からずっとこれで生活上のあらゆる運動を測ってきたから、時間とは客観的で絶対的なもの、つまりいつでもどこでも何に対しても変わらない普遍性を持っている・・・と長い間思っていた。
しかし、歳を重ねるにつれ、様々な自然現象や多くの生命のあり方により深い興味と共感を得るようになってからは、この考えが徐々に怪しくなっていくのを感じている。
この宇宙世界の生命現象がほとんど無限に多様であるように、時間の多様性も無限であるのではないか・・・つまり、時間の相対性を生命レベルで感じるようになってきた、ということだ。
さて、そうすると、その時間の相対性を基にした世界観や価値観はどう変わらざるを得ないのか・・・。物質の三態に喩えて言えば、あれほど堅固でガッシリしていた個体的世界が、徐々に溶け出して液体的なものに変わり、遂には気体的な身軽さと自由の空気を特質とする相対的世界観とあらゆる価値観に絶対性を認めない価値相対主義に向かうのは自然な流れのように思える。
ただしかし、この地上世界のあらゆる構造物が固い個体の大地の上にはじめて成り立つことができるように、簡単には揺るがぬ堅固な普遍的原理や倫理を求める真摯な努力無くしては、人間世界は善悪の基準を失い、浮遊的で軽薄なものに流れ、価値相対主義はその真の美徳を失うであろう。
この世界の物質変化が個体・液体・気体という3つの主要形態をとること一つとってみても、宇宙や世界のあり方はそれ自体で、人間のあり方や生き方を正しく導く善き指針になっていることが良く分かるような気がする。
水を例にあげるなら、大気中に水蒸気がなければ、人間はすぐに喉を痛めて病気になるだろうし、地球規模でも水の大循環はあり得ない。氷がなければ、オンザロックが飲めないだけでなく、地上は灼熱の地獄模様になるだろう。
一つの物質が、最も不動で堅固な個体や、変幻自在の液体や、最も自由な気体へと、条件に応じて変化してくれることの有り難さ・・・時間について想いにまかせていたら、こんなところまで流れ着いてしまった。
再び、時間について考える。時間とは一体何か。
時計を見る。秒針がコツコツ動いている。これが1回転すると分針が一つ進み、分針が1回転すると時針が一つ進み。時針が2回転すると1日が進む。とりあえず、これが最も身近な時間の捉え方だが、実はこれは利便上、人間が作った単なる一つのモノサシしにすぎない。
小は我が心臓の鼓動や呼吸、大は地球の自転やら公転やら小宇宙の回転やら、更に大きな銀河団の動きやら・・・規則的リズムを奏でながら絶えず運動を続けているこの世界のありさまを、人間の感覚で測れるように工夫して作った道具の一つだ。
時計の進行は余りに確実な物理的事実で、小さい頃からずっとこれで生活上のあらゆる運動を測ってきたから、時間とは客観的で絶対的なもの、つまりいつでもどこでも何に対しても変わらない普遍性を持っている・・・と長い間思っていた。
しかし、歳を重ねるにつれ、様々な自然現象や多くの生命のあり方により深い興味と共感を得るようになってからは、この考えが徐々に怪しくなっていくのを感じている。
この宇宙世界の生命現象がほとんど無限に多様であるように、時間の多様性も無限であるのではないか・・・つまり、時間の相対性を生命レベルで感じるようになってきた、ということだ。
さて、そうすると、その時間の相対性を基にした世界観や価値観はどう変わらざるを得ないのか・・・。物質の三態に喩えて言えば、あれほど堅固でガッシリしていた個体的世界が、徐々に溶け出して液体的なものに変わり、遂には気体的な身軽さと自由の空気を特質とする相対的世界観とあらゆる価値観に絶対性を認めない価値相対主義に向かうのは自然な流れのように思える。
ただしかし、この地上世界のあらゆる構造物が固い個体の大地の上にはじめて成り立つことができるように、簡単には揺るがぬ堅固な普遍的原理や倫理を求める真摯な努力無くしては、人間世界は善悪の基準を失い、浮遊的で軽薄なものに流れ、価値相対主義はその真の美徳を失うであろう。
この世界の物質変化が個体・液体・気体という3つの主要形態をとること一つとってみても、宇宙や世界のあり方はそれ自体で、人間のあり方や生き方を正しく導く善き指針になっていることが良く分かるような気がする。
水を例にあげるなら、大気中に水蒸気がなければ、人間はすぐに喉を痛めて病気になるだろうし、地球規模でも水の大循環はあり得ない。氷がなければ、オンザロックが飲めないだけでなく、地上は灼熱の地獄模様になるだろう。
一つの物質が、最も不動で堅固な個体や、変幻自在の液体や、最も自由な気体へと、条件に応じて変化してくれることの有り難さ・・・時間について想いにまかせていたら、こんなところまで流れ着いてしまった。










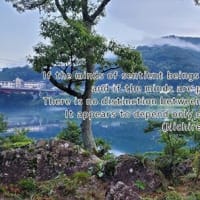
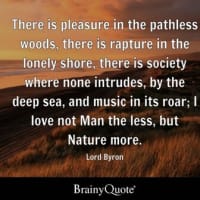
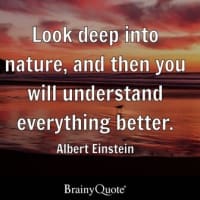







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます