航空力学の中心が「揚力」と「抗力」にあることにちょっと触れました。そして、揚力と抗力に欠かせない要素が大気の動き、つまり「風」であることは言うまでもありません。風と飛行翼との関係が揚力・抗力に決定的な影響を与える「迎え角」だとも言えます。
では、航空気象の中心は何でしょう?・・・これは航空云々だけの話ではなくて、気象全般の話ですが、これも「風」です。空気の運動のことを「風」と呼び、水蒸気を含んだ大気がどのような運動をするかを明らかしようとするのが気象学であれば、当然の話です。
※ちなみに航空気象とは、航空機が飛べる高さまでの気象ということで、ジェット戦闘機など特殊なものを除いては、およそ対流圏界面(対流圏と成層圏の境目)のちょっと上およそ15000m程度)までです。
そして、航空航法で最もやっかいなのが偏流計算で、これの決定的な要素になるのもやはり「風」です。
以上当たり前みたいな話ですが、私たちが地上でも日常的にお付き合いしている「風」は飛行理論を考える上でも、常に中心概念に関係している・・・言い換えると全ての飛行に関する理論は「風」を中心に置いて互いにつながり関係しあっているということを確認しておきましょう。
ちなみに、空気は窒素が78%、酸素21%、その他の1%がアルゴンやメタンやアンモニアや二酸化炭素などできている混合気体なわけですが、例えば酸素濃度が4%増えるだけで地球上の植生は全て炎上するし、窒素濃度が75%に落ちると全地球がたぶん終わることのない氷河期になります。地球温暖化で大問題になっている二酸化炭素などは、たかだか0.04%程度の中の話です。
自然界の調和がいかに絶妙なレベルで行われているか・・・わずかな資料を一瞥しただけでも充分想像が付きますね。
空気について、ライアル・ワトソン「風の物理学」から少し・・・
「生命と精神に不可欠な第一の前提条件は大気の存在である。大気がなければ世界は古い骨のように枯渇し、硬く固まった砂漠と化してしまい、足が踏み込んでも音も立てず、埃(ほこり)すらも死んでしまう。あらゆるものが存在しえているのは大気があるおかげだ。これがあるおかげで、軌道運動をしている岩山、すなわちある種の星は、生き物のような自己完結した姿をとり、情報をやり取りし、太陽に対処するのに不可欠な技術を学んで、自らを成立させてきた。
地球はそういう生き物の一つである。成長もするし、湿気を帯びて光を放つ空気膜を身にまとってもいる、それなりの有機的生命体なのである。この半透明の膜の内部には微風の毛細管網が張り巡らされていて、端から端まで情報やエネルギーを運んでいるが、そこには更に卓越風という太い動脈が走っている。
空気中には単なる気配以上のものがうごめいている。
空気自体が脅威の宝庫だともいえ、その発生は決して偶然ではなく、その存続も幸運の賜物ではないような気がしてくる。
・・・・・
35億年間に渡って、地表は生命にとって好都合であるばかりか、極めて安定した温度を保ってきた。熱放射の量が一定せず、調整機能を持たない太陽に身をさらして自転しながら、それをやってのけたのである。この微妙なサーモスタット調節のメカニズムを性格に分析するのは困難だが、調節機能があることは否定できないし、また地球の気温ばかりか、もしかしたら機構全体が何者かによって操作されているとも考えられる。・・・「まかない上手」とも言うべき巧みさでいつの時代にも大気成分の構成比率が決定されてきたが、それがどんな内実なのかは定かではない。ほとんどあらゆることが化学の法則に反するのである・・・」
では、航空気象の中心は何でしょう?・・・これは航空云々だけの話ではなくて、気象全般の話ですが、これも「風」です。空気の運動のことを「風」と呼び、水蒸気を含んだ大気がどのような運動をするかを明らかしようとするのが気象学であれば、当然の話です。
※ちなみに航空気象とは、航空機が飛べる高さまでの気象ということで、ジェット戦闘機など特殊なものを除いては、およそ対流圏界面(対流圏と成層圏の境目)のちょっと上およそ15000m程度)までです。
そして、航空航法で最もやっかいなのが偏流計算で、これの決定的な要素になるのもやはり「風」です。
以上当たり前みたいな話ですが、私たちが地上でも日常的にお付き合いしている「風」は飛行理論を考える上でも、常に中心概念に関係している・・・言い換えると全ての飛行に関する理論は「風」を中心に置いて互いにつながり関係しあっているということを確認しておきましょう。
ちなみに、空気は窒素が78%、酸素21%、その他の1%がアルゴンやメタンやアンモニアや二酸化炭素などできている混合気体なわけですが、例えば酸素濃度が4%増えるだけで地球上の植生は全て炎上するし、窒素濃度が75%に落ちると全地球がたぶん終わることのない氷河期になります。地球温暖化で大問題になっている二酸化炭素などは、たかだか0.04%程度の中の話です。
自然界の調和がいかに絶妙なレベルで行われているか・・・わずかな資料を一瞥しただけでも充分想像が付きますね。
空気について、ライアル・ワトソン「風の物理学」から少し・・・
「生命と精神に不可欠な第一の前提条件は大気の存在である。大気がなければ世界は古い骨のように枯渇し、硬く固まった砂漠と化してしまい、足が踏み込んでも音も立てず、埃(ほこり)すらも死んでしまう。あらゆるものが存在しえているのは大気があるおかげだ。これがあるおかげで、軌道運動をしている岩山、すなわちある種の星は、生き物のような自己完結した姿をとり、情報をやり取りし、太陽に対処するのに不可欠な技術を学んで、自らを成立させてきた。
地球はそういう生き物の一つである。成長もするし、湿気を帯びて光を放つ空気膜を身にまとってもいる、それなりの有機的生命体なのである。この半透明の膜の内部には微風の毛細管網が張り巡らされていて、端から端まで情報やエネルギーを運んでいるが、そこには更に卓越風という太い動脈が走っている。
空気中には単なる気配以上のものがうごめいている。
空気自体が脅威の宝庫だともいえ、その発生は決して偶然ではなく、その存続も幸運の賜物ではないような気がしてくる。
・・・・・
35億年間に渡って、地表は生命にとって好都合であるばかりか、極めて安定した温度を保ってきた。熱放射の量が一定せず、調整機能を持たない太陽に身をさらして自転しながら、それをやってのけたのである。この微妙なサーモスタット調節のメカニズムを性格に分析するのは困難だが、調節機能があることは否定できないし、また地球の気温ばかりか、もしかしたら機構全体が何者かによって操作されているとも考えられる。・・・「まかない上手」とも言うべき巧みさでいつの時代にも大気成分の構成比率が決定されてきたが、それがどんな内実なのかは定かではない。ほとんどあらゆることが化学の法則に反するのである・・・」










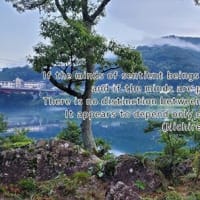
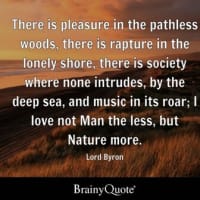
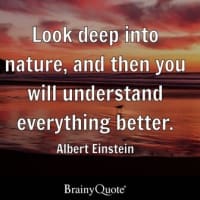







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます