
大人になってから読書を楽しめなくなった。仕事におわれて趣味が楽しめない
疲れいるとスマホを見て時間をつぶしてしまう・・・・
そのような悩みを抱えている人は少なくないのではないか。
仕事と趣味が両立できないという苦しみは、いかにして生まれたのか、
自らも兼業で執筆活動をおこなってきた著者が労働と読書の歴史をひもとき
日本人の仕事と読書の在り方の変遷を辿る・・・
そこから明らかになる日本の問題点とは・・・
明治時代からさかのぼり・・昭和の司馬朗太郎ブームや 自己啓発書ブーム
まで各時代を考察している・・
自己啓発書て30代ぐらいの時によく読んだが結局のところ、なんの役にも
あたなかったというのが結論だな・・40代の時も読んだカーネギーとか
読んだけれど役に立った記憶がない、読む動機が自己啓発だからもともと
読書としてみたら不純な動機かもしれない。
自己啓発という言葉は嫌いになった










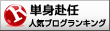















そういう類いの本をよく読みましたが
ほとんど何も覚えていないですね。
小説の一場面とか、台詞の方がよほど記憶というか
印象に残っている気がします。
そう言う自己啓発的な本が次から次へと出てくるのは
そう言う本を欲している人がたくさんいるからしょうね。
自分もよく読みました、鈴木健一でしたっけ30代で
これをしておけとか・・読んだ記憶はありますが
中身は全く覚えていません。
自己啓発本がよくでてるのは、やはり悩み多きこの
世相とかですかね、それと安直に答えを求める傾向に
今あるような気がします。