 |
|
|||||||
|
日本経営士協会は、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。 プロのコンサルタント集団であるとともに、プロのコンサルタントを育成する団体でもあります。 各種情報を提供する中に、会員が趣味で撮影した写真を紹介するサイトです。 素人写真ですが、旅行の参考にされたり、話材の一つとしてお使いくださったりしてくださると幸いです。 |
|
|||
 |
京都 宝厳院 |
||
| 京都 天龍寺 宝厳院の紅葉 |
 京都市の右京区に位置する「宝厳院(ほうごんいん)」は、臨済宗天龍寺派に属す、天龍寺の塔頭の一つです。天龍寺から歩いて10分ほどのところにあります。渡月橋からも15分も歩きません。
境内は主に本堂・書院・無畏庵・青嶂軒・庭園の5つから成り立っています。庭園は「獅子吼の庭(ししくのにわ)」と呼ばれ、嵐山を借景とした廻遊式山水庭園で、紅葉と苔の名所として知られています。 この庭園は、室町時代に中国に二度渡った禅僧である、策彦周良禅師によって作庭されました。「獅子吼」とは「仏が説法する」という意味で、鳥の声や風の音を聴くことで、人生の心理、正道を肌で感じ、心が大変癒する庭といわれています。 「風河燦燦三三自在」(田村能里子画伯筆) という障壁画は、現代風の絵で、「これがお寺の襖?」と思うような、朱を基調にしたものです。 紅葉は、名所といわれるだけあって、苔の緑と調和し、見事という以外の表現ができません。 宝厳院写真集 1 ←クリック
|

◆【経営コンサルタントの育成と資格付与】











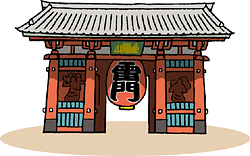

 b20
b20






