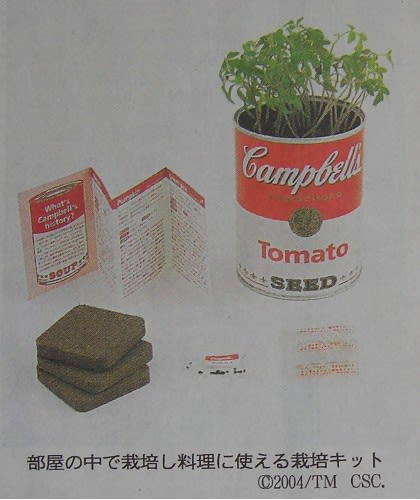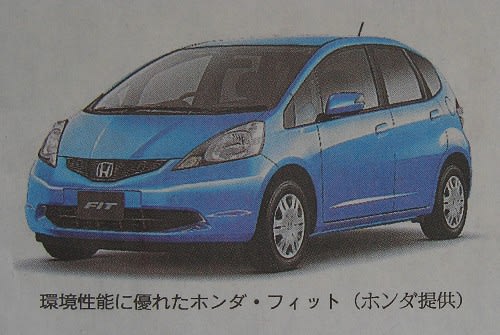<幼児向き>
このサンタさんも実に優しいサンタさん。しかも、気前がよくてトナカ イもそりも子供たちにプレゼントしてしまいます。仲間の待つ北の空 へ歩いて帰らなければならないサンタさん。二月になってもまだ雪野 原を歩いているという訳なのです。そのサンタさんが道草をしていて、 動物園のライオン親子の部屋の天井から落っこちてしまいます。喜ん だのはライオンの坊やたち。「僕たちにもプレゼントを」とおねだりしま す。何も持ってないサンタさんが考えたプレゼントって、いったいなん だったのでしょう。あべさんの描くライオンファミリ-は本当にすてきで す。そして青い雪の世界に浮かび上がるサンタクロ-スの姿は、限り なくあたたかい。
クリスマスにマルチはサンタクロ-スから「ぎんのくま」をもらいまし た。妹のモニカがもらったのは、「まり」でした。モニカはどうしてもぎ んのくまがほしくてたまりません。そこで、マルチはモニカのために、 ぎんのくまを探しに出かけます。森の中で耳の冷たいリスに自分の 手袋をプレゼントするマルチ。リスたちはオオカミが持っていってしま ったマルチのぎんのくまを取り返してくれます。やがてマルチはサン タクロ-スが住むゆきだるまの町に着きました。この絵本の作者ベ ロニカはハンガリ-の人。この国のサンタさんはトナカイに乗らずに、 お供に小鬼を連れています。ゆきだるまもカラフルなお家に住んで いて、とても楽しそう。マルチとサンタさんの優しさがいっぱい伝わ ってきます。
<低・中学年向き>
 |
初雪のふる日
価格:¥ 1,470(税込)
発売日:2007-11 |
懐かしくて不思議で、少し怖くて美しい安房直子の世界を、こんな にも切なく描いてくれたこみねゆらさんにありがとうを伝えたい。ど こまでも続く石けりの輪。女の子がひとりその輪を飛んでゆきます。 ほほを赤く染めて。やがて雪が降り始めます。「もう帰ろうかな」と 女の子がつぶやいたとき、後ろから真っ白いウサギが石けりをしな がら女の子の後をついてきます。雪を降らせる白うさぎたちでした。 アンデルセンの「赤い靴」の主人公は踊り続けたのですが、この女 の子は白うさぎたちと、とび続けなければなりませんでした。けれど、 おばあちゃんの言葉がおまじないとなって女の子を救います。季節 の巡りや自然の神秘をこんなお話に結晶させる安房直子ってやっ ぱりすごい。
「ソルビム(1)」の女の子編がすばらしかったので、この男の子編 が翻訳されるのを楽しみにしていました。今年6月、道内三ヵ所を 回したアジアの絵本展、うちのギャラリ-でも開催しました。その中 にこの絵本の原書もあったのです。男の子がお正月の晴れ着「ソル ビム」を独りで着る様子がいきいきと愛らしく描かれています。まず、 ポソン(足袋)から。足先にかわいい花が刺しゅうされています。そし て健康と長寿を祝って「命」を意味する「寿」という字も。お母さんの 縫ってくれた晴れ着はとにかく愛情いっぱいに、あふれんばかりで す。どうぞどうぞ、世界中の子供たちのもとへ、お正月も新しい年も 「福」がいっぱい来ますように!この男の子のように。
<高学年以上>
先日、この絵本を上川管内剣淵町の小学校で読んできました。お父 さんお母さんたちが聞いてくれました。PTA会長さんが「懐かしかった。 僕も子供の時、田んぼのそばの小屋で、月明かりの下で稲刈りをす る父母の代わりに、小さい妹や弟の子守をしながら、いろんな話をし てやりました。まだランプをともしてくださった。少年のようにきれいな 瞳を輝かせて語るお話に、みんな心がほっこり暖かくなりました。小 屋って本当にいいです。私の住む東川にも小屋がいっぱいあります。 オンボロ、おしゃれ、めんこい小屋たち。みんな物語りを抱いています。 風景の中で、控えめに息しています。「ここにいるよ。いつだってここに いるよ」とひとりごちながら。
「小公女」や「秘密の花園」そして今は「ニルスのふしぎな旅」と名作 再読ブ-ムのこのごろの私でしたので、この絵本の表紙、白い鳥に 乗った小さい女の子に心引きつけられました。「ニルスの女の子版か しら」。そうではありませんでした。サンタクロ-スになったマ-ガレッ トがクルミ割り人形ルデイに導かれて、森へ湖へプレゼントを届けに行 く姿だったのです。ルデイも八羽の白い鳥たちもとても頼もしい。マ- ガレットとルデイの会話も愉快です。植田真の絵は「静謐」という言葉 で表現されてきたけれど、この絵本はとてもチャ-ミング。物語と絵が 溶け合い、奏で合いながら、いとおしい世界を作り上げています。白と 黒のコントラストがこんなに美しかったなんて!