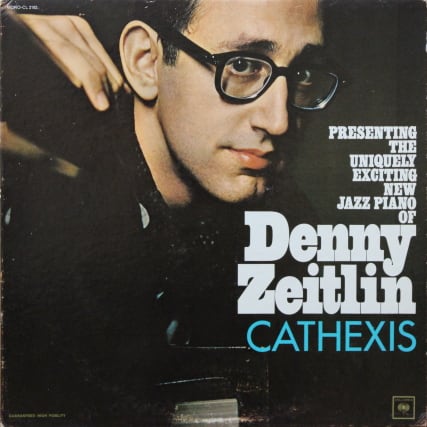今週も少しですが、つまみました。


■ Sonny Murray / Sonny's Time Now ( Jihad / DIW-355 )
サニー・マレイが1965年にニューヨークで自主制作として作った作品で、何と言っても目玉はアルバート・アイラーが参加していることです。
そのために、このアルバムはたくさんあるフリージャズの中でも別格扱いされることが多い。
ESPとの契約の関係で Sunny ではなく Sonny という綴りになっているし、アイラーも Albert ではなく Albbert という綴りで表記されています。
また、オリジナル・マスターはステレオ録音なのに、レコードが作られた際はミックスダウンしてモノラルとして発売されていますが、DIWはマスター
テープのままステレオとしてこのCDを作っています。
アイラーの客演は珍しいのでそういう観点でどうしても聴いてしまいますが、やはり上手いサックスです。 この人は上手い。
アイラーはオーソドックスなフリースタイルとゴスペル調のスピリチュアルスタイルの2種類をアルバム毎に使い分けた人ですが、ここでは前者の形式で
吹いています。 ただ、それでも演奏は大らかでゆったりしているし、もう一方の管のドン・チェリーも奇音を発することなく普通のオープンホーンの
音なので、リード2人の音に不快感はない。 それよりも、誰かの"ウー"という低い唸り声がずーっと曲の間じゅう聴こえるのが不気味で、これが全体の
トーンを支配しています。
サニー・マレイのドラムは所謂パルスビートでこれが革新的なことだったと言われる訳ですが、果たしてそうなんだろうかと疑問に思います。
リズムを作ることを拒否した時点で、ドラムという楽器はその存在意義を失ってしまいます。 じゃあ、その時ドラムは一体何をするのかというと、
何か音を出さなければいけない以上は選択肢は自ずと絞られてくるだろう。 スネアとシンバルを同時に鳴らし続けるこのやり方もルーツはきっと
ネイティヴアメリカンドラムなんだろうし、全く同時期にトニー・ウィリアムスも始めていますが、トニーの演奏には感動するのに、サニーの演奏には
特に感動しません。 大事なのはそういう形式上のことではなく、やはりクォリティーなんだと思います。 この人の演奏にそういう何か特別なものを
感じるかというと、そんなことはありません。
注意して聴くと確かに耳につくことはつくし、フリー以前の音楽では見られないものですが、でもそれはそれまでの音楽がそんなものを必要としなかったから
であって、サニー・マレイの場合はどちらかというとフリージャズからの要請にただ従っただけのことなんじゃないかという気がします。
だから、逆に主流派の中にそういうドラミングを持ち込んだトニーのほうが文字通り革新的だったし、そもそもリズムを作るためにこのやり方を選んだ
というのは、リズムを叩かないためにそれを選んだサニーとは正反対の発想だよな、と思うわけです。
■ Maria Schneider Orchestra / The Thompson Fields ( artistShare AS0137 )
待望の新作です。 DUの週間売り上げチャートでは上位に入っていたようですが、なんだか不思議な気がします。
トンプソンフィールズというのはマリアの故郷であるミネソタにある広大な森林地帯の名前で、そこで彼女が感じたいろんなことをオリジナルの
楽曲として作品に仕上げたものを1枚のアルバムとして世に問うたものです。
この人のこれまでの足跡を丹念に追ってきた人であればこの作品に違和感を感じることはないでしょうが、そうではない人にはいわゆるジャズっぽさが
まったくないこの内容にがっかりするんじゃないでしょうか。
豪華なブックレットの中には、草原に佇む彼女の姿や野鳥の挿絵、著名な森林学者の箴言などが載っていて、彼女の溢れる想いが詰まった作品である
ことがよくわかります。 そういう詩情豊かな音楽をこれまた豪華なビッグバンドを使って描き出していくのですが、各楽器の稼働率は低いので、
団員たちはジャズと演奏してるというよりはブルックナーの交響曲を演奏しているような気分だったのではないでしょうか。
この artistShare というレーベルはクラウドファンド型の投資レーベルで、ファンが投資することで作品の制作が始まり、投資した人への特典として、
その制作過程の様子など様々なプレミアム情報が提供されます。 だから、マリアはこのアルバムに収録されているいくつかの楽曲を資金集めのために
すでに2年前からコンサートで繰り返し演奏・お披露目していて、それに賛同し投資が集まったのでこの新作が出来上がっています。
つまり、マリア・シュナイダーの次回作がどういう内容になるのかは、事前に簡単にわかるのです。
この作品、せわしない殺風景な東京の街の中で聴くのは相応しくない。
残念ながら今はその中にいるしかないのですが、いつの日か、もっといい環境の中でこの作品を愉しめるようになれたらいいなあ、
と夢見ながら聴いています。