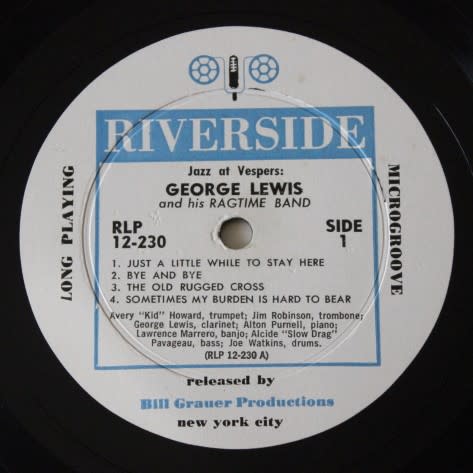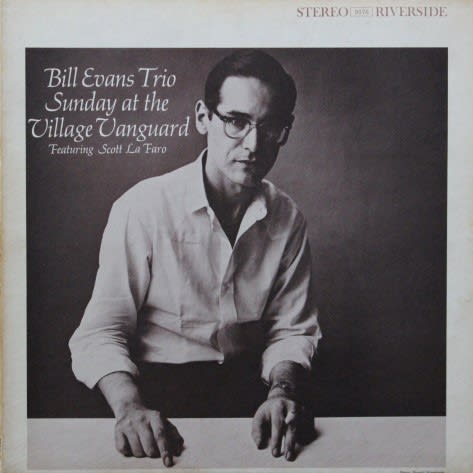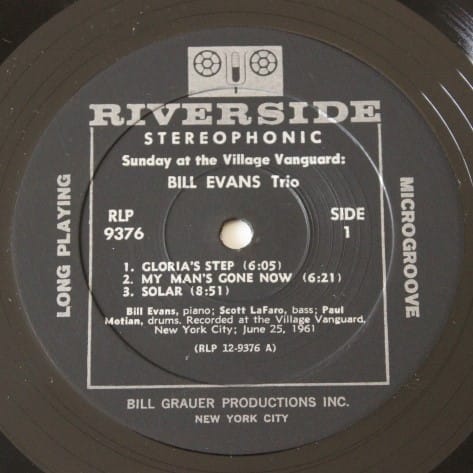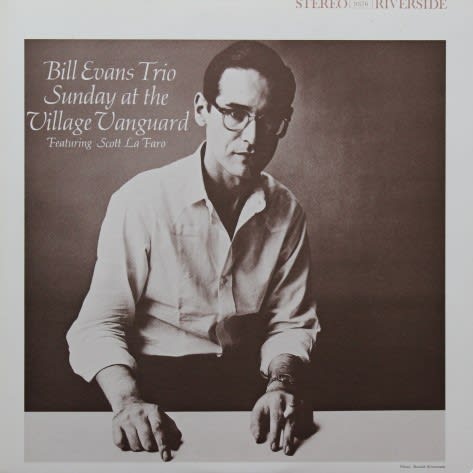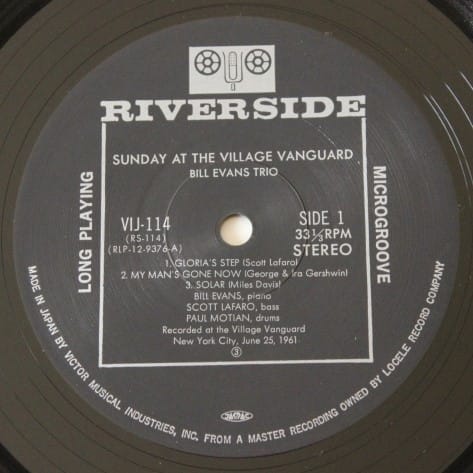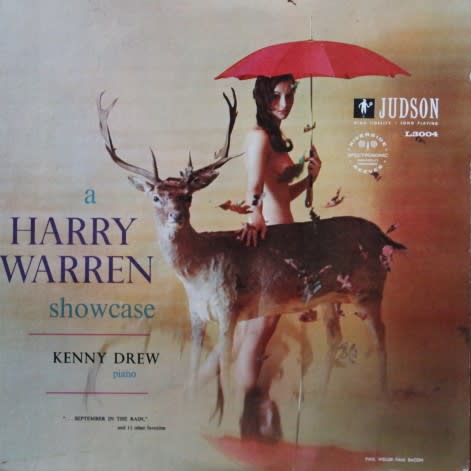Bill Evans / At The Shelly's Manne-Hole ( 米 OJC-263 )
OJC盤は音がいい、というのは今では常識になっているが、具体的にどういう音なのかについてはあまり伝わってこない。
そこで、音楽を繰り返し聴くに耐え得るビル・エヴァンスのアルバム群を題材にして、オリジナル盤と対比させながらも、
実際のところはどういう音なのかを聴き比べてみる。
一口にOJCと言っても、何度かプレス・発売されていて、このタイトルもレコードは1986年、2018年にプレスされている。
手持ちのものは86年プレスなので、その前提で聴いてみる。
A面 OJC 263 A1 G1 (A) 手書き
B面 OJC 263 B1 G1 (A) 手書き
一聴して、3つの楽器のバランスの良さに溜め息が出る。再生される音は上質でなめらかで、極めて自然なステレオ感。
プレス品質も良く、耳障りなロードノイズはまったくない。
ベースの音はリアルで、弦が震える音がクッキリと再生される。ドラムもスネア、ハイハット、ブラシの音が物凄く自然な音。
ピアノはきちんとアコースティック・ピアノらしい音で、弱音になっても音場の中に埋没しない。拍手の音もクッキリとしている。
聴いていて、気になる瑕疵は何も感じない。
このOJC盤を聴いた後にオリジナルのステレオ盤を聴いてみると、こちらはピアノの音がもっと硬質で、音がより立っている。
一方でベースの音圧が弱く、音が音場の中で埋没していて、あまりよく聴こえない。チャック・イスラエルがラファロと比べて
大人しく覇気がないと言われるのは、こういうオリジナル音源のサウンド感が影響していると思う。ドラムも控えめな音圧で、
スネアの音に深みが欠けている。
オリジナルは明らかにエヴァンスのピアノを目立たせるようなマスタリングをしていることがわかる。ただ、各楽器の音色は
明るくクリアで輪郭もクッキリとしていて、音圧の強弱の影響からOJC盤よりもサウンドに奥行き感がある。
拍手の音は潰れて割れている。とにかく、ピアノの音に全神経を集中させたような音作りになっている。
もう1度OJC盤に戻ってみると、オリジナルは全体的に古風な雰囲気、OJC盤はリノベされたばかりの清潔な部屋のような印象だ。
各楽器の音色を根本から見直し、1つ1つ丁寧に磨き上げて、正しい位置にきちんと配置し直した、という感じである。

オリジナルのモノラルとステレオでは、音場感はまったく異なる。モノラルは音がこもっていて、ぼんやりと霞んでいる。
それに比べると、ステレオはベールを1枚剥がしたようなクリアな音。普通に考えれば、このアルバムはステレオ盤で聴く方がいい。
1965年のリリースという時期を考えると、これは当然の結果だろう。