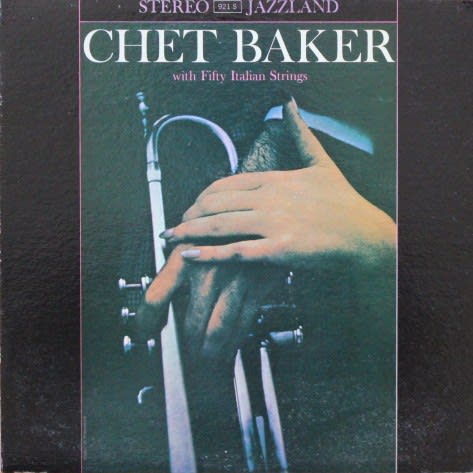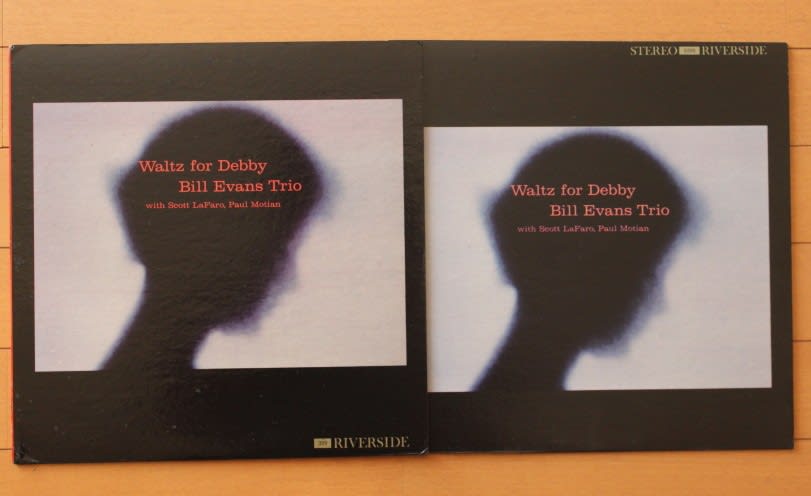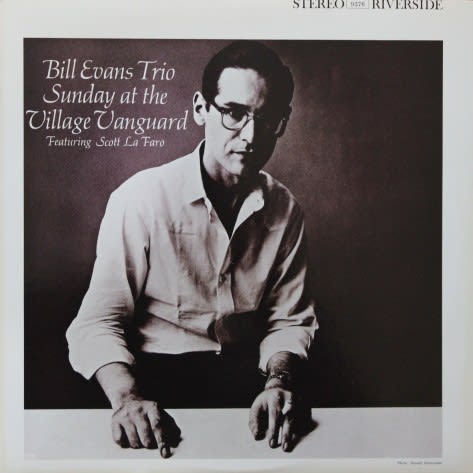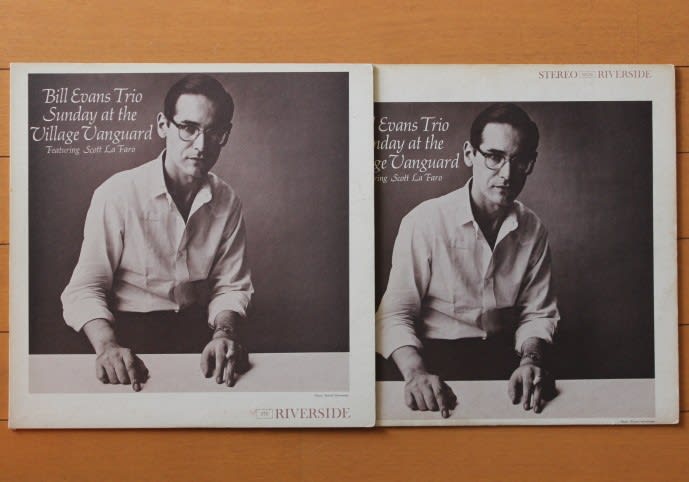Cannonball Adderley / Jazz Workshop Revisited ( 米 Riverside RS9444 )
キャノンボールはやはりリヴァーサイドがいい。この前のエマーシー/マーキュリー時代やリヴァーサイドが倒産して止む無く移籍した
キャピトル時代のものはレーベル側の意向が優先されたアルバムが多く、キャノンボールの姿はあまりよく見えない。
それに比べて、リヴァーサイド時代は彼が当時考えていた音楽がそのままパッケージされていて、本当に自由にやっているのがよくわかる。
それはオリン・キープニューズが音楽は音楽家の物だと考えて、彼らの意向を最優先にして自由にやらせたからだ。
そういうのは経営者としては失格だったのかもしれないけれど、音楽プロデューサーとしては最上の資質だったと思う。
それはこのレーベルに残されたアルバム群が証明している。とにかく、このレーベルは傑作の森なのだ。
コレクターたちが相手にしないこの時期のキャノンボールの演奏は、音楽的には非常に充実している。ユーゼフ・ラティーフを加えた3管に
ザヴィヌルのピアノを擁した音楽の質は極めて高く、独自の世界観に満ちている。彼は自身のバンドを持つことにこだわり続けた人だったけど、
メンバーがなかなか安定せず、そのせいで音楽水準を維持させるのには常に苦労していたが、人格者だったラティーフの人柄に惹かれて
バンドに迎え入れてからは束の間の安定をみせた。
オーボエやフルートでオリエンタリズムをグループに持ち込んだことで、ファンキー一色だったバンドのカラーは当然ながら変化する。
このライヴでも、そのミックス具合いが面白いようにわかる。冒頭でキャノンボールがこれから演奏する "Primitivo" という異色の曲が
どういう曲であるかを熱心に解説するところから始まる。そして、2曲目、3曲目は往年のビッグバンド・サウンドのような、とても3管とは
思えない分厚い重奏による楽曲が続き、B面に移ると名曲 "Jive Samba" がカッコよく演奏されたかと思うと、ナット・アダレイの
夢見るような珠玉のバラード演奏が披露され、最後は正統派ハード・バップで幕を閉じるという何とも最高のセットリストだ。
ジャズのライヴ・アルバムとして、こんなにも音楽的に充実した万華鏡のような内容はちょっと珍しいのではないか。
音楽的な引き出しの多さが圧巻だし、演奏力の高さも群を抜いていて、これは本当に凄いバンドだということが理屈抜きにわかる。
そして、ステレオ・プレスの音の良さが音楽のダイナミクスをヴィヴィッドに伝えてくれる。会場の空間表現に長けており、観客の熱気、
演奏家の息遣い、そして何より楽器の音色の新鮮さが際立つ。リヴァーサイドのキャノンボールはステレオ・プレスがいい。