
(琉球王府時代、赤はジュリの色だった!「かせかけ」も廃藩置県以前は笠を被っていた!)
衣裳が階層や社会のシンボリズムであることは明らかだが、その境界に位置した美らジュリの衣装に児玉さんは触れられない。どなたもふれない。UN-touchableな美女たちは近代においては高価な紺地や絣を身に着けている。ある首里の御殿内出身の女性の談話として、彼女の父親は清から持ち帰った絹物の優れた布を母親(妻)にではなく、辻の詰めジュリ(妾)の所へ持っていったという。琉球王府の時代にファッションの中心は首里ではなく、辻遊里や仲島、渡地だったのですね!
『性と聖』を見ると日本のエロスが中国の摸倣性を多く持っているのだということに驚いた。性=聖である。弦楽器をかなでる遊女と交わる中国の男性の19世紀のスケッチなど、ヘタイラそのものの象徴だ。道教と儒教の違いにも驚く。インドの神話世界はまたエロスに満ちている。今気になっている両性具有性は神話の根になっている。琉球もまたそうだ。それが表象レベルまで透徹していると言えるのだろう。もっと書きたいがI have to go to YANBA
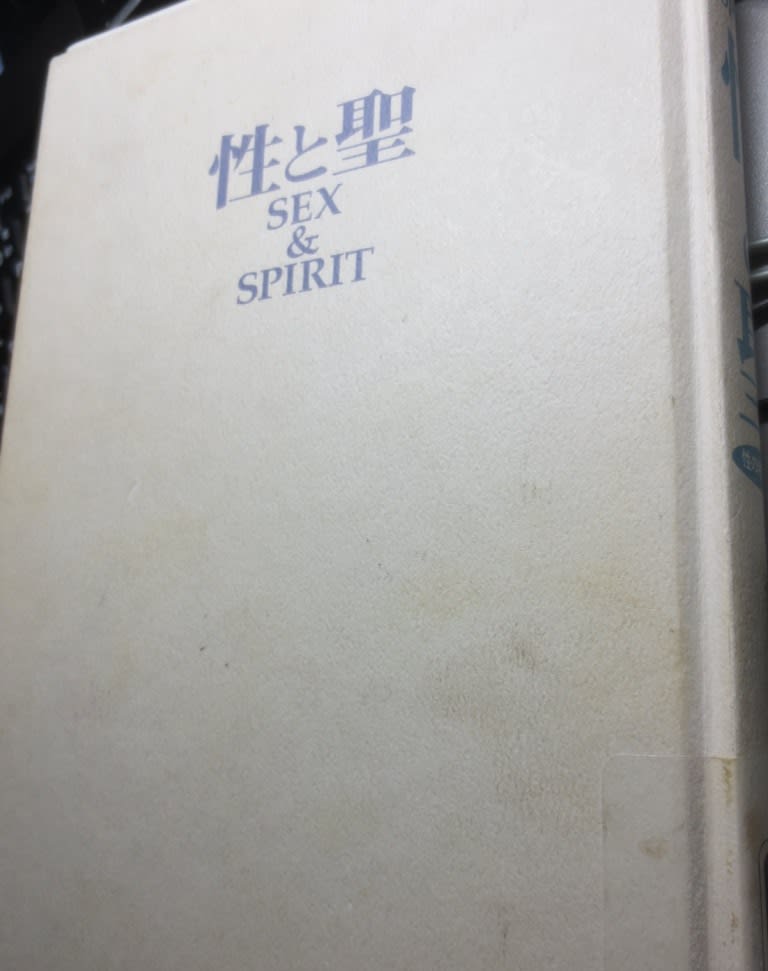
中身は性そのものの絵画や挿絵なども多く関心を引き付ける。「辻遊郭開祖の墓」の「遊郭」までとってしまった那覇の現状だが、性なりセクシュアリティの根源を歪める行為であり、歴史を見据えないという姿勢をただ示しているだけだ。性=聖でエロスとタナトスの両輪の中に生きている私たちだね。
 これはチェンバレンが明治26年に沖縄に来た時、一月いて、沖縄の上流階層の夫人に一度もお目にかからなかったという事実に重なる。秘匿された女性たちがいた。一方で遊里があった。チェンバレンは遊里に行く男性は多く、ジュリも多いと書いている。琉球芸能の『女形』の理由の根本もそこにある。「女性が性的オブジェクトであった」慣習に根差している。楽童子は性のオブジェクトにまた成り得たのである。遊里では少女たちの芸能が賞賛され、表では若衆=少年たちの芸が賛美された。異性装である。遊里の少女たちは二才踊りを踊っている。
これはチェンバレンが明治26年に沖縄に来た時、一月いて、沖縄の上流階層の夫人に一度もお目にかからなかったという事実に重なる。秘匿された女性たちがいた。一方で遊里があった。チェンバレンは遊里に行く男性は多く、ジュリも多いと書いている。琉球芸能の『女形』の理由の根本もそこにある。「女性が性的オブジェクトであった」慣習に根差している。楽童子は性のオブジェクトにまた成り得たのである。遊里では少女たちの芸能が賞賛され、表では若衆=少年たちの芸が賛美された。異性装である。遊里の少女たちは二才踊りを踊っている。

これは宜野座村松田、最も古い組踊り台本<1818年>が見つかっている村の踊り衣裳(紅型)である。

着物市場、古着市場は女性たちでにぎわっている。こうした商いは士族層の女性たちも手掛けていた。

沖縄の女性たちは高貴な身分から一般庶民まで機織りに従事してきた。糸を紡ぎ、布を作り、織って染めたのである。これは生きる生活の必然でその過程で女性たちの思いが織り込まれていった。

王族の高貴な衣裳は紅型と黄色、鳳凰のデザインなどでその誇りを明らかにする。衣服は重要なシンボリズムで、薩摩の在番は王家の上に位置し、その現地妻はまた王家の女性たちに勝るとも劣らない衣装を身にまとったことが絵画からわかる。また冊封使の随行員が辻の馴染みの美らジュリに金の簪や銀の簪、絹織物をプレゼントしたことも史実から見えてくるね。鮮やかな赤の胴衣を下着に紺地の絣を身に着ける雑踊りだが、赤に象徴されるfemininityを付きつめたい。疎かった衣裳について博論でも今書いている方がいて、多くの女性たちは関心をもっている。今までじっくり見て来なかったのが事実だ。琉球衣装史など読んだが、まだ血肉化していない知識である。衣裳のシンボリズムが表象としての『芸能』の中で大きな意味性をもっているのである。古典音楽や古典舞踊も含め研究者はあまりに辻遊郭などの実存・歴史的意義を無視していると思う。古典女踊り=上流階級の女性なんでしょうか?宜保先生はお怒りになっていたが、美らジュリですね。愛や恋の対象は美らジュリで『男性の欲望から秘匿された殿内の女性たち』ではなかった。「かせかけ」の女性ですが、ジュリもまた機織りしているのですね。まして恋は士族社会ではご法度だったのだ。遊里で士族男性の欲望や美意識は解放されていった。そこに芸能が満ち溢れたのですね。仮説ですが、男性からの御立腹が多く、若い学生などは協賛していると感じた。アンケートから。




















