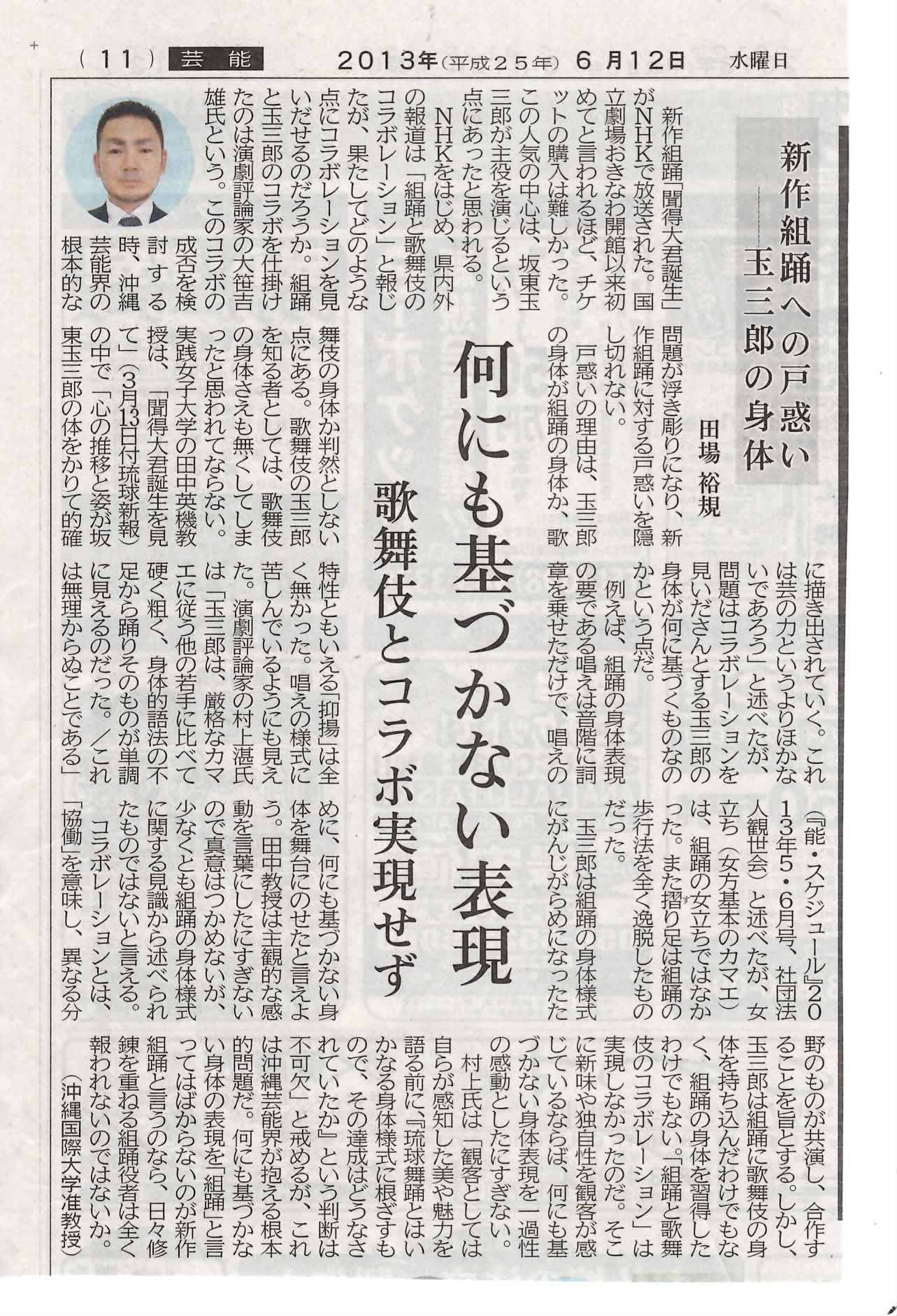
玉三郎さんの新作組踊への挑戦を批判的に見たエッセイが掲載された。どちらかというと組踊の身体は沖縄芝居の身体とも異なる、独自の身体性、様式があるとみなそうとする意向をもった田場さんである。視野が狭い、という印象を受けた。「歌舞伎とのコラボは実現せず」の見出しである。玉三郎さんがまぎれもなく歌舞伎の女形芸をになった人間国宝であり、歌舞伎役者の身体と感性を築き上げてきた第一人者があえて沖縄の新作組踊に挑んだ役柄であり舞台だった。そのアジア的な身体性や様式性を追求しているように見える玉三郎さんの女形芸は、不思議なコラボレーションの美に包まれていたのではないだろうか?全くの歌舞伎でもなく全くの組踊でもない、折衷(ハイブリッド)の美だったかもしれない。メイクそのものもすでにして、歌舞伎調と組踊調のハイブリッドであり、衣装も髪型もメイクもその折衷の美に見えた。短期間で琉球舞踊を習得し、同じく組踊女形の人間国宝の宮城能鳳さんから振付をしてもらった玉三郎さんの歌舞劇のような踊りの多さは格別に思えた。田場さんのエッセイはそうした沖縄を代表する組踊の身体技能≪様式≫を担った指導層の問題の指摘にもなっていると言える。→宮城能鳳さんの芸や指導の批判でもある。
不思議なハイブリッドの美に魅了されたのは事実だ。唱えは決して普段聞きなれた唱えには聞こえてこなかったが、それも含めて不思議な味わいがあったのは確かだと言える。新たな挑戦の美がそこにあふれていた。問題にするのならば、玉三郎の舞姿、その軽やかな動き(様式性を含め)、身体性や唱えだけではなく、脇役の沖縄の希望の☆たちの身体性や様式も共に問題にしていいと思う。
「日々修練を重ねる組踊役者は全く報われないのではないか」や「何にも基づかない身体の表現を《組踊》と言ってはばからないのが新作組踊と言うのなら」の言説は、全体を見ないで部分だけ見据える、どちらかというといわゆる組踊の身体性そのものの根拠さえ流動的な沖縄の現状の中で、あえて組踊独自の身体というガチガチな規範を持ち込もうとする趣向だと感じさせた。田場さんや狩俣恵一さんが規範とするスタイル(様式)はどの形態なのだろうか?王府時代のどの様式なのか?近代のどの様式をもって規範とするのだろうか?士族層の身体という言葉が最近見え隠れしている。組踊や古典女踊りの身体表象のモデルは士族層とその階層の女たち?わたしは古典女踊りのモデルは辻や仲島遊里の美しいジュリたちを含んでいると考えている。琉球士族の日常の身体表象はどうだったのか?そこまでどうやら問いただしている研究が始まっているのかもしれないが、それは興味深い。ヒエラルキーを求める家父長制度の極め付きの芸能=組踊ということになるのだろうか?作品そのものは仇討物を抜きにしても(その一部も含めて母子の愛情が勝っている。なぜ?)女、子供たちがけっこう登場する。士族層の女や子供たち(士族の下層の身体ですか。ジュリとして遊里に身売りされる士族の女たちもいた!)
名優たちは沖縄芝居を演じた身体で組踊を演じてきたのである。組踊の身体性なり様式や唱えを格上げすることにより、戦前からの芸能史の流れを原理主義に乗じて堅いコアを築き上げようとする思考性に見えた。沖縄芸能の優柔無碍≪雑多に歌舞伎や新派やもろもろを取り込んだ≫の近代の流れを無視できない。変節してきた組踊の様式なり身体である。王府時代の組踊や古典舞踊の身体性(様式性)が近代以降どう変節してきたのか、まずもって問われなければならない。玉三郎さんの挑戦は勇気を示してあまりある。彼こそが柔軟な精神をもっていたゆえに新作組踊に挑んだのである。アジア的な美=様式なり身体性を追及している求道者に見えた。何にも基づかない、ですか?歌舞伎の身体・感性・思想性が玉三郎そのものではないのだろうか?そして歌舞伎の美はアジア的な美や身体・感性・思想性をまた普遍的に具現する芸能だということだと考えるのだが、もっと考えてみたい。



















