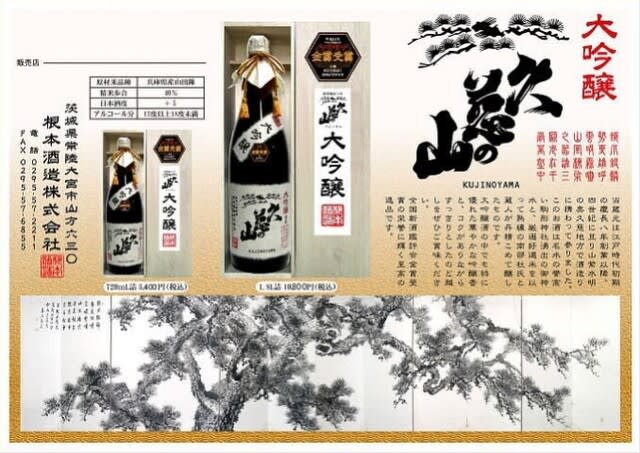「江戸木目込人形」
江戸木目込について
木目込とは、衣裳のひだや布切れの境となる部分に細い溝を彫り込み、そこに布を「きめこむ」ことからそう呼ばれております。
その発祥は、約270年前の元文年間(1736~41)に京都で生まれた木目込人形で、その人形づくりの技法が江戸に伝わり「江戸木目込人形」が誕生しました。
現在は経済産業大臣指定の伝統的工芸品の「江戸木目込人形」として東京・埼玉でつくられるものが有名です。
江戸木目込人形の歴史
木目込人形は、約270年前の元文年間(1736~41)に京都で発祥したと言われています。
通説によると、当時の上加茂神社の雑掌の高橋忠重という人が、余技で、神社の祭礼用の道具を作った余りで木彫りの人形を作り、それに神社の衣裳の残り裂を木目込んだのがはじまりといわれています。
この人形は当時、加茂人形・加茂川人形・柳人形と呼ばれ、のちに木目込人形と呼ばれるようになりました。
その後、江戸の発展と共に、京都から江戸に移り住んだ人形師により、木目込人形は「江戸風」に発達していきました。
明治の後期になると、木彫りの胴に裂張りという古来からの製造法から、桐塑を型抜きして胴体を作るという現在の製造法が行われるようになりました。
この技法により、多量生産や形態の多様化が可能になり、様々な種類の木目込人形が作られるようになりました。

お気に入りのお雛様と一期一会を果たしたい、江戸木目込人形
人形の街・岩槻では、たくさんの人たちの手によって愛らしい人形の数々が生まれ続けている。雛人形、五月人形、市松人形――健やかにたくましく、見目麗しく育てよと人形に託した親の思い。子供たちを取り巻く環境は大きく変わろうとも、その心は昔も今も変わることはない。
子供のため、そして自分のために人形を飾りたい
武州・岩槻といえば、名にし負う人形の街。城下町・宿場町として栄えたこの地には、日光東照宮の造営・修築に当たった工匠たちが定住し、人形づくりを始めたという。岩槻周辺は、もともと桐の産地である。工匠たちは、この桐の粉が人形の材料として、また当地の水が胡粉を溶くのに適していることを発見したのだった。
現在も、300人を数える人が昔ながらの分業体制の下、伝統的な人形づくりに携わっている。「最近では男の子をもつ20~30代の若いお母さんは、武器を連想させる鎧兜よりも、愛らしい木目込人形を好まれるようですね。また40代以上の女性でも、自分のためにと買っていかれる方が多いんです。節句に関係なく、小さめの立ち雛が人気ですね。経済的に余裕ができて、心にもゆとりが生まれたんでしょうか」とは、伝統工芸士・有松寿一さんの談。穏やかで木訥(ぼくとつ)な語り口のなかに、深い人柄が忍ばれる。
節句に関係なく根強い人気を誇る立ち雛。「自分のために買っていかれるお母さんも多いですよ」と、作者の有松寿一
今どきの子供たちも、木目込人形に首ったけ
筆描きされた上品なやさしい顔立ち、配色の妙を尽くした目にも絢なる絹の衣装、すっきり伸びやかな立ち姿。木目込人形は、大人が手にしても思わずため息が漏れるほど、精緻で美しく高級感あふれる工芸品である。
一方、子供たちも、別の意味で木目込人形に首ったけだ。有松さんは、小学校の体験学習で4、5年生を対象に人形づくりを指導したことがある。どの子も、人形の型抜き作業には瞳を輝かせて大喜び。「今、学級崩壊や多動性症候群などが盛んにいわれていますが、手を使うこと、体で覚えることに子供たちはすっかり夢中。これには、先生のほうがびっくりしていましたね。」
岩槻では、分業体制がしっかりと敷かれている。こちらは面相描きをしているところ。集中力がものをいう仕事だ
職人としての技、問屋としての経営感覚
有松さんは、中学生の頃から人形師の父を手伝っていたという。縁あって、15歳である親方の元へ。修行を始めて3年ほどで、経営も手伝うようになった。20歳のとき、親方が42歳の若さで急逝。遺された家族を放っておけず、人形づくりを一時中断して問屋業に精を出す。後に親方の息子へ経営をバトンタッチ、晴れて人形師として独立した。
「この道一筋、とはいかなかったことが、かえって視野を広げてくれたみたいです。」
今や世を挙げてのIT時代、有松さんもパソコンをフル活用している。写真撮影もデザインも自らこなしたパンフレットを制作して営業で活用、問屋の人たちからは機能的でかつ美しいと大評判だ。ホームページも自分で立ち上げた。が、こちらは啓蒙の意味合いが強い。
「あくまでメーカーとしての領分を守りつつ、問屋さんのじゃまにならないようにね」
経営時代に身につけた各方面への気配りとバランス感覚が、今ここで生きている。むろん、先を読む視点も忘れてはいない。将来、職人の数は確実に減っていくだろう。息子は跡を継がないと言っているし、無理強いするつもりもない。だからこそ、今まで自分が作ってきた木目込人形はかけがえのない財産。データベースとして保存し、後の代に人形を作りたいという人が出たとき役に立ってくれれば、という。
頭の取りつけ作業を行う有松さん。「衣装の選定にはとにかく悩みますね。毎年、京都の西陣織の展示会に顔を出しています」
人と人形にも一期一会がある
あるとき有松さんのサイトに、面識のない女性から一通のメールが届いた。それは、有松さん作の慶雲雛を購入した若い母親から寄せられたものだった。――店にはたくさんの作品が飾られていたのですが、どうしてもあなたが作られた慶雲雛へと目が吸い寄せられていくのです。子供のためにと求めたものですが、今では見るほどに愛着が湧き、このお雛様に出会えてよかったと、満ち足りた気持ちです。ありがとうございました。
一期一会、であろう。人の人との間だけでなく、人と人形との間にも、そう呼ぶべきものが存在するのかもしれない。人形師は、わが子を育てるかのごとく一体一体の人形と向き合い、その慈みで人形に魂を吹き込み、見る者の心を動かす。子を思う親の心ある限り、人形づくりの技が途絶えることはない。
御所風シリーズの一つ「吉祥果」。中国風の髷(まげ)が愛らしい。どの人形を見ても、衣装の柄と配色の妙はうっとりするほどの美しさだ。
有松さん作「初陣」。顔はぽっちゃりとしてかわいらしいのに、凛々しさをも感じさせる。
職人プロフィール
有松寿一
1941年生まれ。
目下、3Dソフトを人形づくりに活用すべく研究中。
一方で、テラコッタ(塑像)の技法を今なお学び続ける努力の人。
四季を愛でる日本人のこまやかな感性が息づく、江戸木目込人形
春夏秋冬、日本列島の自然は刻々と移ろっていく。その生命力の微妙な変化を受け取る感性が、木目込人形づくりにも大きく反映される。名匠の人形を通して、大人も子供も、日本人なら本来備わっているはずの感性を思い出し、大切に育んでいきたいものだ。
人形に託した親心
寒さがゆるみ桃の蕾もほころぶ春弥生、女の子の健やかな成長を願って飾られるお雛様。青々とした皐月の空に勢いよく泳ぐ鯉幟(こいのぼり)、たくましい男に育てよとの願いをこめて飾られる武者人形。時は移ろうとも、人形に託した親心は変わらない。
少子化の進む昨今、親御さんたちは子供が少ない分、一人ひとりにこまやかな愛情を注ぎ、この子のためにいいお人形を、という気持ちになるらしい。一昔前は、おじいちゃんおばあちゃんが初節句のお人形を贈るケースが多かったようだが、今は若いお父さんお母さんが自ら子供のために選ぶことが増えているときく。
「大空の夢」。今にも童たちの歓声がきこえてきそうだ
「邪まな心があったら人形さんは作れないよ」
人形師の柿沼東光さんは、15歳のときこの道に入った。もともと手先を使うことが大好き、仕事を覚える間も楽しくて、とくに苦労した覚えはないという。
「あたしはのんびりした性格だからね。だいたい人形を作る人は、温和で心静かな人が多いんじゃないのかい。邪まな心なんかあったら人形さんは作れないし、仮に作ってもお顔に現れてしまうだろうよ」生き生きとした動き、独創性あふれる意匠が、柿沼さんの作る木目込人形の真骨頂だ。熊を投げ飛ばす金太郎、お兄ちゃんに背負われて万歳する童、桃の上にちょこんと腰かけてこちらを見つめる童、竹の子の隣で成長を競うかのように体を伸ばす童、鯉幟にまたがるやんちゃ坊主たち。自然のなかで無心に遊ぶ人形たちは、どの子もかわいらしく、見ているだけで思わず口元がほころんでしまう。
柿沼さんの仕事部屋。「何だか世の中のテンポが早くなっちゃってねえ。昔は、気が向いたら仕事、そんな感じだったよ」
新しい時代のニーズに合った木目込人形を
お母さんの世代が交替していけば、必然的に人形の好みも変わってくる。柿沼さんは、伝統的な人形を作り続ける一方で、新しい時代のニーズに合った木目込人形をも手がけている。そのためには、あちこちを旅して各地の伝統工芸品に触れたり、日常のどんな些細なことにもアンテナをはることを忘れない。
最近、新しい感覚の雛人形セットを発表した。季節(五節句)によって人形や背景の飾り、台座などを取り替えて楽しむものだ。これが、世代を越えて好評なのだという。正月は、門松と鏡餅を飾り赤い毛氈(もうせん)の上で初春を祝う雛たち。背景には、雲間からおめでたいご来光が指している。桃の節句は、お内裏様とお雛様。その周りで、楽しそうに楽を奏で舞い踊る童たち。端午の節句は、男の童たちの饗宴。背景にはもちろん、鯉幟と花菖蒲である。七夕の節句は、織り姫と彦星のロマンスを祝うように、天の川のせせらぎで無邪気に戯れる童たち。中秋の名月の頃は、団子を囲んで月見する雛たち。隣にちょこんと兎が座り、薄の穂が秋の風情を醸している。
柿沼東光さん作、童人形。ほかにも動物に乗っている童たちの作は、どれもほほえましいものばかり
新しい感覚の雛人形セット、夢小雛「祭遊」
木目込人形を通して、季節の変化を楽しむ
「節句」はもともと、「節供」と書いた。「節」は季節の節目を表し、「供」は食物を供えるという意味。つまり節供は、季節の変わり目に八百万(やおよろず)の神々への感謝をこめて旬の食べ物をお供えし、人々も一緒にいただいて健康を祈る行事だったのだ。
お祭りや行事は晴れ(ハレ)の日、その日を思いきり楽しむことで生命力が再生産され、翌日からの日常生活が活力に満ちたものとなる。そう、暮らしにめりはりがあったのだ。
「だけど今は、年中行事そのものも、それがもつ深い意味合いもだんだん忘れられて、日々の暮らしがのっぺらぼうになってしまったね。あたしは人形さんを通して、伝統文化の底に流れる日本人の細やかな感性を子供たちに伝えていきたいんだよ」
柿沼さんの手によって生み出された木目込人形たちは、愛くるしいなかにも溌剌とした生命力が秘められている。存在感が濃厚なのだ。大人も子供も一緒になって木目込人形を飾りつけ、四季折々の変化を感じて楽しむ――。そんな心のゆとりや豊かさこそが、今切実に求められているのではないだろうか。
「斑鳩(いかるが)聖星」。古代飛鳥の風を感じる作品
職人プロフィール
柿沼東光
1920年生まれ。
盛り上げ加工を施した手描き模様、金箔押し、螺鈿(らでん)など、常に新しい技術や感覚を取り入れている。
こぼれ話
江戸木目込人形のふるさとは、京都の上賀茂神社
上賀茂神社。じつはこれは通称で、正式な名前は賀茂別雷(わけいかずち)神社といいます
*https://kougeihin.jp/craft/1302/ より