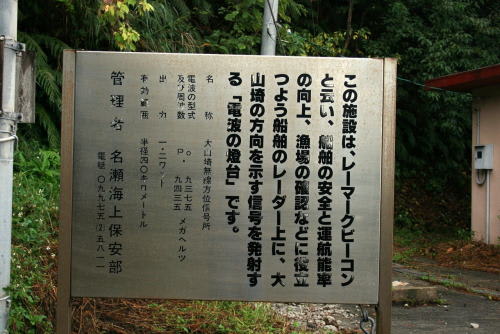高さは東防波堤灯台と同じ11mとなっている

灯台の沖合いに立神島が見える

灯台がある防波堤の上はかなり広くなっている

灯台の下部は防波堤の壁で隠れている

等明暗赤光で明3秒暗3秒の灯器

赤い塔に銀白色のハッチがやけに映える

東防波堤灯台が平成9年に対しこちらは元年と少し古い
灯台表番号 / 6941.8
ふりがな / なぜこうにしぼうはていとうだい
標識名称 / 名瀬港東防波堤灯台
所在地 / 鹿児島県名瀬市 ( 名瀬港西防波堤外端 )
北緯 / 28-23-57
東経 / 129-30-02
塗色 / 赤色
灯質 / 等明暗赤光 明3秒暗3秒
光度 / 1700カンデラ
光達距離 / 10.0海里
地上~頂部の高さ / 10.53m
平均水面上~灯火の高さ / 12.46m
地上~灯火の高さ / 10.1m
業務開始年月日 / 平成1年12月25日
現用灯器 / LC管制器Ⅱ型
名瀬港西防波堤灯台は、東防波堤灯台と向かい合ったように立つ灯台である。
東側が白に対してこちらは赤い色で塗られている。
灯台の高さはどちらも11mと同じ高さにあるが、
向こうの灯台が立ち入り禁止区域にあるのに対し、
こちらは写真のように灯台下で自由に釣りが出来る。
名瀬港西防波堤灯台へのアクセス
名瀬港防波堤灯台へは、名瀬港に向かって左側に
約1キロほど行った船着場の防波堤の外端になる。
灯台の近くに浄化センターなどの施設があるため防波堤の近くまで車で入って行ける。
駐車は、防波堤近くの空いたスペースに邪魔にならないように駐車した。