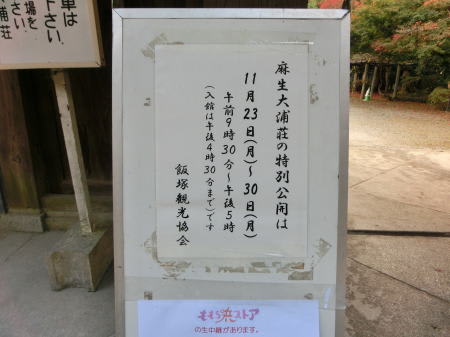福江教会の歴史は明治29(1896)年、
久賀島から最初の信徒が福江地区に移り住んだことから始まりました。
ペルー師が、堂崎教会を中心に下五島の各教会を巡回していた頃で、
当初はこの信徒宅でミサが捧げられていました。
その後福江地区では信徒数が徐々に増え教会ができるまでは
現在の中央町の家御堂でミサが捧げられました。
ペルー師が明治43(1910)年前後に、
当時公立病院の病棟が建っていた現在の教会敷地を建物と共に購入し、
建物を教会に改造しました。
これらの資金はフランスの篤志家がペルー師に与えたものと伝えられています。
大正3(1914)年4月には、それまで所属していた旧堂崎小教区から分離・独立し、
新たに福江小教区としての歩みをスタートさせました。
福江教会の特徴としては、江戸時代末期に大村藩領から
五島内の各集落に住み着いた潜伏キリシタンの子孫達が、
徐々に福江地区に集まってきて共同体を形作っていった点が挙げられるでしょう。
昭和4(1929)年、教会敷地内に現在の福江修道院の前身である奥浦修道院分院が設けられ、
共同生活をしていた数人の修道女達が精米所を開業しました。
前年には同じ敷地内で修道女二人が産婆の仕事も始めています。
五島病院と助産院の手伝いが主な仕事で危篤の嬰児に臨終の洗礼を授けることもありました。
精米所は精米、精麦、製粉のほか時間にゆとりのある時期を利用し製麺も行っていました。
“ 値賀の誉 ” と名づけられたそうめんはおいしと好評で、昭和30(1955)年まで行われました。
また太平洋戦争末期から終戦直後にかけて教会の一部が
軍 ( 五島兵団:混成旅団 ) の倉庫に使用されたこともありました。
福江教会信徒の長年の夢であり懸案であった新しい教会の建設は、
信徒らが資金を出し合い昭和36(1961)年3月着工、
昭和37(1962)年4月25日献堂という形で実を結びました。
その僅か5ヵ月後の9月26日未明に起こった 「 福江大火 」 は、
市街地の大部分を焼失するという長崎県内では戦後最大の大火災でしたが、
完成間もない福江教会は奇跡的に焼失を免れ、
焼け跡にそびえ立つ教会が復興のシンボルとして被災者を勇気づけました。
五島市の行政・経済の中心地に位置し、下五島地区では信徒数が最も多い教会で、
市内の教会の中心的な役割も担っています。
また福江教会の朝は早く、教会の門が開けられる午前5時頃から
三々五々信徒達が教会に集まってきます。
午前6時に始まる平日のミサまでの時間、ロザリオの祈りなどを捧げるためです。
また、平日であっても小学生の子ども達が交代で司祭のミサ司式を手伝う侍者をつとめるなど、
日々の生活の中で豊かな信仰がいまも受け継がれています。
福江教会は立地の良さから訪れる人の多い教会の一つで、
人々の祈りと安らぎの空間として今日もその歴史を重ねています。
所在地 / 長崎県五島市末広町3-6
教会の保護者 / イエズスのみ心