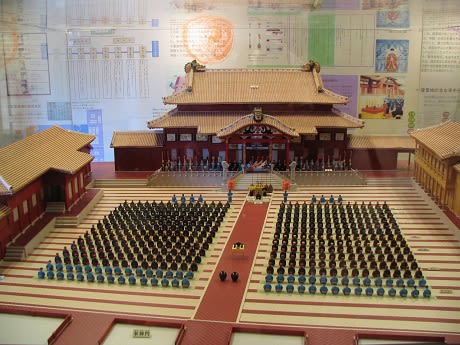糸数グスクの城門


糸数グスクの城壁


斜めに競り上がった城壁

識名園からの眺望

南風原町兼城にある 「 内嶺グスク 」

南風原の隣にある豊見城市嘉数にある長嶺グスクからの眺望
一般にグスク ( 城 ) は高台にあるから下界がよく見渡せる。
そういった意味からもハッとするような景色を見ることができる。
奄美や与論もワクワクして見たが、
それ以上に沖縄の景色を見ると気持ちがゾクゾクする。
多くのグスクや王墓や按司墓、そして石橋や文化財や灯台を巡ったが、
この場所に来らせるというか、呼ばれるのを感じて、その度に訪れた沖縄。
年に5回ほど通っていたから、40回に近い。
今日放映された津嘉山にも・・・
そんな沖縄の景色を見ると感情が抑えられないくらいである。