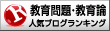よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
「うらそえ文藝」編集長の星雅彦氏が沖縄の知識人の中で誰よりも早い時期に、渡嘉敷島と座間味島で集団自決の生き残りの聞き取り調査をしたことは、当日記で再三紹介した。
ご本人はその当時の心情を「うらそえ文藝」(14号2009.5)の上原正稔との一問一答で次のように吐露している。

うらそえ文藝 第14号 (2009年5月発行)
特別企画 薩摩侵攻400年
座談会 琉球文化の交流と成熟
-薩摩侵攻から琉球以上は-
田名真之・豊見山和行・小野まさ子・星雅彦
特集 集団自決
対談 上原正稔VS星雅彦
星 (略)
「また、四〇年ほど前に渡嘉敷島と、座間味島に宿泊して、私は当時の村長と駐在巡査と宮城初校に会って話を聞いたわけです。そのとき何かしっくりせず隠しているなと感じたものです。隊長命令があったとは誰も言わなかったし、なかったとも言えないふうに、非常に曖昧だった。私は七一年の「潮」に「集団自決を追って」という文章を物語風に書いたけれど、わざとぼかして書いた。ある程度の確信はあったが、あの私の逃げ口上的な表現に対しては、今でも忸怩たるものがある。(略)」(タイムスを恫喝した男 2012-06-27 )
さらに当時の取材の模様を雑誌「潮」(1971年11月号)に寄稿しており、集団自決の真相を知るための貴重な資料として当日記でも何度か引用させてもらった。
例えば過去ブログの沖タイの歪曲記事、故赤松大尉直筆の手紙を届けるでは次のような一節を紹介している。
《村の指導者たちやその家族や防衛隊の幾人かは、そろって無事で、その集団にまじっていた。みんなひどく興奮していて、狂人のようになっていた。村長は狂ったように逆上して「女子供は足手まといになるから殺してしまえ。早く軍から機関銃を借りてこい!」と叫んだ。その意志を率直に受けて、防衛隊長の屋比久孟祥と役場の兵事主任の新城真順は、集団より先がけて日本軍陣地に駆けこみ、「足手まといになる住民を撃ち殺すから、機関銃を貸してほしい」と願い出て、赤松隊長から「そんな武器は持ち合わせてない」とどなりつけられた。(注・比嘉喜順、伊礼蓉子らの証言。その点、米田惟好は米軍に決死の戦闘を挑むつもりだったと、異議を申し立てている)(雑誌「潮」1971年11月号・星雅彦)》
☆
慶良間島で起きた集団自決研究の第一級資料とも言える星雅彦著の雑誌「潮」(1971年11月号)掲載手記が、ヒジャイ出版の季刊誌「沖縄内なる民主主義5号」にその全文が掲載されている。
雑誌「潮」が入手困難な現在、今回の収録は今後の集団自決の検証にとってきわめて貴重な資料になる。
さらにその全文をヒジャイ出版の又吉義隆さんがブログで公開したので、当日記も早速これを全文紹介させて頂いた。
以下は「沖縄に内なる民主主義はあるか」の引用です。
星雅彦氏は一九七一年に軍命はなかったことを書いていた

星雅彦氏は一九七一年に軍命はなかったことを書いていた
「沖縄内なる民主主義5」の「軍命はなかったのになぜ集団自決は起きたか」から転載した。
星氏が軍命令はなかったことをすでに知っていたことが分かる。
集団自決について掲載しているサイトを探していたら、偶然、星雅彦氏が一九七一年に書いた「集団自決を追って」を掲載しているサイトを見つけた。「集団自決を追って」を読んで驚いたのは、集団自決は軍の命令ではないと書いてあることだった。一九七一年は前の年に「沖縄ノート』(著者:大江健三郎)が出版されて「集団自決」は軍命令であったと沖縄の人たちに広がっていた時である。その時に、軍命令はなかったことを沖縄の作家が書いていたのだ。驚くべき事実である。
私はWEBで「集団自決を追って」の出所を調べた。すると一九七一年十一月号の雑誌「潮」に特別企画・「沖縄は日本兵に何をされたか 」に掲載されていたことをつきとめた。同時に掲載してあったのが前号の「沖縄内なる民主主義4」に掲載した赤松嘉次氏 (元海上挺進第三戦隊長)の「私は自決を命令していない」である。前号でも赤松戦隊長が自決命令を出していなかったことを証明したが、星雅彦氏の「集団自決を追って」でも赤松戦隊長が自決命令を出していないことを書いている。それだけではない。赤松隊長が自決命令を出していなかったにも拘わらず村民が集団自決をしたいきさつも書いてある。非常に貴重なドキュメントである。
私は星雅彦氏にお願いして、「集団自決を追って」をこの本に掲載させてくれるようにお願いした。星さんは快諾してくれた。それだけでなく、「雑感」を書いてくれた。
雑感
私が沖縄戦に関心を抱き、執筆するようになったのは、一九六九年の夏頃からだ。県資料室長の名嘉正八郎から「沖縄県史」戦争記録の仕事の依頼を受けたのがきっかけである。早速「沖縄県史第九巻 沖縄戦記録1」に収めるための録音・テープお越し、文章化の仕事などに取り掛かった。
そのためには事務局の方でセットした各市町村へ出向き、戦争体験者たち数人が区長宅へ集められ、座談会形式で戦争体験を収集するところから始めなければならない。
多くの話者は痛ましい話ながら坦々と語ったが、ためらいがちに訥々と語る人や、思い出しながら切羽詰って涙ながらに語る人も居た。それでも話し終わった人々の顔は、すっきりとした安堵感が漂っていたと思う。
現在も証言集の作成は続いているが、四十年前とはかなり違っているようだ。昨今、戦争の話の中に政治やイデオロギーが絡み合って複雑な話し手の心境が伺えるのだ。
例えば、何かの話の内容に疑惑が入り込んでいたり、虚構性の対象にされたりする。事実らしく書いてあっても事実でない場合があったり、嘘っぱちを書いていながら、事実として受け取られる場合が少なくない。
その点からすると、昔の「潮」(一九七一年十一月号)に私が執筆した「集団自決を追って」は率直そのままの記録だと思う。ただ、周辺の革新系の友人たちに多少気兼ねがあったようで、ふがいなくも私は若干逃げ口上を記してしまった。「悲劇の再現とは、口はばったい言い種である。ただひたすら二十六年前(一九四五年)の悪夢を想像してみたままである」と付記したが、それでもその説話スタイルの中に真実が込められているだろうと自負している。
数年前のある日、大田昌秀氏から電話があって、「あの内容は現地で調べて書いたのか」と問われた。私は「泊りがけで調べました」と答えた。大田氏との対話はそれっきりである。
集団自決を現地で調べた私には一種の使命感があった気がする。
星雅彦
雑誌「潮」一九七一年十一月号
特別企画・沖縄は日本兵に何をされたか
集団自決を追って
ドキュメント
集団自決を追って
星雅彦(作家)
(本稿は私が当時の村長や駐在巡査や若干の村民から取材した集団自決の内容を、私なりにまとめ、悲劇の再現を試みたものである。いな、悲劇再現とは、口はばったい言種である。ただひたすら二十六年前の悪夢を想像してみたまでである)
目次
砲弾とどろく渡嘉敷島
米軍上陸で動揺する村民
闇の雨中を西山盆地へ集結
"玉砕するしかない"
「みんな一緒に死のうね」
修羅場と化した西山盆地
二十六年前(一九四五年)に、沖縄戦の最初の上陸地点、慶良間列島の中の渡嘉敦島で、想像を絶するような陰惨な悲劇があった。それは、日本の末端の皇国の民の、玉砕という名のもとに引き起こした"集団自決。である――
砲弾とどろく渡嘉敷島
集団自決があったのは、前夜の雨がやんだ後のくもり空が、茂った木の葉の間から見える西山盆地の雑木林の中で、三月二十八日の午後一時ごろだった。
三月二十三日には、初めての本格的な空襲で、村の役場や郵便局が焼けたので、ほとんどの村民はそれぞれの壕に避難したり、荷物を運んだりした。二十四日も空襲で、二十五日には、艦砲射撃も加わって、島は遠く近く砲弾のとどろく音と地鳴りにあけくれた。
夜になって、無気味な静けさの中で、防衛隊が二人、壕の入口まできて、ウシ(三十七歳の主婦)に向かって「阿嘉島にアメリカーが上陸したそうだ」「阿嘉島の人たちは、みんな玉砕したそうだ」と知らせてくれた。三人の子供をかかえたウシは、この渡嘉敷島の暗い運命を予感して、大変なことになったと思った。
古波蔵村長(三十三歳)は、在郷軍人であった。このさい、日本軍に協カして戦いたい気持ちもあったが、日本の特幹隊は遠くトカシクに本部をおいていて、すぐに行けもせず、また彼は家族といっしょに壕に避難していたので、家族のことも気になって、何度も壕を出たりして、若い青年たちを走らせ情報をキャッチすることに努めていた。が、阿嘉島がやられているとは聞いたが、玉砕したとは聞いてなかった。
安里駐在巡査(二十九歳)は、沖縄本島に妻子を置いて単身一月下旬に赴任したばかりで、島の地形も日本軍のこともよくわからなかった。しかし彼は二、三日前から、赤松隊長を探し出すために、トカシクの山の中を歩き回っていた。日本軍の動きはあわただしく、阿波連に向かって移動していたので、馴れぬ山道をあっちこっち歩いたが、二十五日も二十六日も赤松隊長には逢えなかった。
大本営からの阿嘉島は玉砕した(注.誤報であった)という情報は、安里巡査の耳にも入っていた。誰から聞いたかは憶えてないが、とにかく、巡査よりも村民のほうが先に、戦況やそうした近海の米軍の動きなどをよく感じ取っていた。
敵の軍艦が慶良間海峡に侵入していることは山の上から見ればすぐわかったが、大町大佐が阿嘉島から阿波連の海岸に立ち寄ったということは、極秘中の極秘のはずだが、防衛隊が彼に教えてくれた。安里巡査はあせっていた。小学生まで陣地構築に協力してきた村民が、これから先どうあらねばならぬか、安里巡査は赤松隊長に相談したかったのだ。村長も一刻も早く隊長と相談してこいということだった。
翌二十七日も砲弾のとび交う中を、腰にぷらさげたサーベルをカチャカチャ音させて歩き回り、やっと西山のほうへ移動したばかりの赤松隊長の居所をつきとめた。その間に、出会った防衛隊や朝鮮人軍夫や村民から、特攻舟艇の破壊作業のことや、米軍の上陸や、日本軍が迎撃する交戦の模様を、伝え聞いた。
支那(北支から中支)で軍隊生活をおくった経験のある安里巡査は、これまでに阿度か軍隊生活を話題にし、日本軍が「こっぴどく支那人をやっつけた」ことを話したことがあったが、あの残虐なことが、あすはわが身にふりかからねば幸いだがと、ふと不安に思った。なにしろ兵隊たちの間から、米軍の捕虜になったら間違いなく戦車で礫き殺されるという風聞が出ていて、それは疑う余地がないようだった。
ただ一方には、日本が最後には勝つ、という信念があった。がしかし、それは惨澹たる道程の果てに、最終的に勝利の結果を産むという、悲壮な意味を含んでいて、自分たちは犠牲にならねばならぬかもしれぬという気持ちが同居していた。そうした心情は村民の一般的傾向であった。
米軍上陸で動揺する村民
三月二十六日の朝、米軍が阿波連から上陸したことが村民に知れたったとき、村民のほとんどは動揺し、壕から壕へ移動した。
ウシは子供たち(長女十二歳.二女七歳.長男三歳)を連れて、屋敷内の壕から、港に向かって西側の川向こうの山の麓の壕に行った。そこにはすでに二家族が入っていた。その家族の中の十六、七歳になる少年たち二人が、あわただしく出たり入ったりして落ち着かず、しきりに死ぬ覚悟で何かしなければならぬといったりしていた。竹ヤリを持ち歩く姿は、頼もしい感じであった。ウシたちは、ガテカル(嘉手刈)の壕で一夜をあかした。
翌二十七日になると、敵が攻めてくるのが感じられたし、阿波連から避難してきた人たちも敵が押し寄せてきていると話していたので、ウシたちは、ウンナガーラ(恩納川)近くに叔父たちが掘った壕があるのを思い出して、そっちへ向かった。その途中で、山のほうのミーヤーの上のところで、アメリカーが何やら作業しているのが見えた。
ウンナガーラのイチャチチというところの壕に着いたら、叔父や十八歳になるその息子は「いざとなったら、天皇陛下万歳をいって死ぬんだ」と語し合っていた。けれども、敵機の爆音は、ひっきりなしに聞こえるし、遠くから砲弾の炸裂音が近づいてくるように聞こえるので、みんなひどくおぴえていた。ウシは「死ななくても、すむよ、友軍がついているから大丈夫よ」と逆に元気づける始末だった。
安里巡査は、朝から敵機に見つからぬよう隠れたりしながら、午後も夕方近くなって、やっと西山の谷間の日本軍の陣地を探しあてて、そこではじめて赤松隊長と逢った。そこへたどりつくまでに、空襲ですっかり焼けたや山林の中を歩いているとき、安里巡査は沖縄本島にいる妻子の安否を思った。渡嘉敷に赴任してから、一度は宇久校長(沖縄本島出身)といっしょに御真影を保管するために沖縄本島に渡ったことがあったが、あのとき帰ってこなければよかったと、彼は後悔したりもした。
西山のトトンジャーラ(イシッピ川)の奥地の日本軍の陣地は、移動してきたばかりで何もできてなくて、朝鮮人軍夫や兵隊たちが、盛んにタコ壷を掘っていた。陣地壕はまだほとんど掘られてなかった。赤松隊長は、陣地構築の指図をしていた。(注・防衛隊や軍夫や村民の幾人かは、集団自決の後日、壕掘り作業に出ている―小嶺善吉らの証言。二十七日に地下壕内で将校会議か開かれたという記録は間違いで、将校は分散したタコ壺の中か外で戦闘配置についていた。村民をどうこうするという会議を開く余裕はまったくなかった―知念朝睦〈少尉〉の証言)
そこで安里巡査は、赤松隊長に向かって、村民はあっちこっちの壕に避難して右往左往しているが、これからどうしたらよいかわからないので、軍のほうでなんとか保護する方法はないものか、どこか安全地帯はないものか、と相談を持ちかけた。
そのとき赤松隊長は、次のようにいった。島の周囲は敵に占領されているから、誰もどこにも逃げられない。軍は最後の一兵まで戦って島を死守するつもりだから、住民は一か所に避難していたほうがよい。場所は軍陣地の北側の西山盆地がいいだろう(注・比嘉喜順、旧姓・安里、元駐在巡査の証言)。そこで安里巡査は早速、居合わせた防衛隊数人に対し、村民に西山盆地に集合するよう伝達してくれと告げた。彼自身も、各壕を回っていい伝えて歩いた。
防衛隊の一人は、古波蔵村長にいち早くほば正確な伝達をした。そして村長からも、同様の伝達が出た。それは人の口から人の口へ、すばやくつぎつぎと広がって伝わっていったが、村民のあるものは赤松隊長の命令といい、あるものは村長の命令だといった。
注(又吉) 四十二年前に、星氏は、赤松隊長が「島の周囲は敵に占領されているから、誰もどこにも逃げられない。軍は最後の一兵まで戦って島を死守するつもりだから、住民は一か所に避難していたほうがよい」と言ったと書いている。このドキュメントを多くの沖縄の人々か読んで居たら、「集団自決」に対する認識は違っていただろう。
闇の雨中を西山盆地へ集結
ウシたちの壕には、防衛隊の一人がきて、「村長命令だ、ウンナガーラから西山にのぼれ」といった。そこで迷いながらも、ウシたちはともかく出掛けるしたくをしていた。こんどは三人の防衛隊がきて「もうすぐそこに敵がきている」「みんな西山に登ってください」「村長命令です、西山に集まってください」と口々にいった。その三人の防衛隊は、ウシの弟、モリスケ叔父、ミサトの叔母の妹の夫で、三人とも輿奮してせきたてていた。村長命令とあらば、どんなことでも従うほかはないと、ウシは思った。
ウシたちが恩納川を登って行くうちに、雨はどしゃぶりになった。ウシは三歳の息子をおぶって、七歳の二女の手を引いて歩いた。十二歳の長女(本誌119ページの安座間豊子さん)は、三日分の食糧(米と黒砂糖とカツオ節)を入れたランドセルを背負って、ウシの後につづいた。ウシたちは、ずぶぬれになって暗い谷川のふちを歩き、ときどき滑って水の中へ落ちこんだりした。ぬれた赤土はよく滑るし、もう夜になっていて、何も見えなかった。
ざわめくような足音や、親子の名を呼び合う人声で、多数がぞろぞろ西山へ向かっていることが判った。ウシは長女に三日分の食糧だけを持たせてあったが、一日か二日、西山に避難するつもりだった。後でわかったことだが、ある人たちは、クワやナタやカマを持っていた。それらの農具は、西山で壕や小屋をつくることを予想して持ち運ぱれたのだ。多数が持っていた一メートルほどの棍棒は、荷物を肩にかけて持ち運ぶときに使われた。
恩納川の上流の谷間の上のほうが、西山の盆地だった。日本軍の最後の本部となった陣地は、小高い山を一つ隔てた小さいもう一つの谷間(トトンジャーラの上流)にあった。この二つの谷間の川は、渡嘉敷からは別々に並行しているが、上流に行くにしたがって接近し、西山高地に達するところで、深い谷底に小さい溝のようになって消えていた。西山の頂上の平たんな雑木林は、この二つの谷間の北方にあった。そこが西山盆地で、戦後、村民が玉砕場と称するところである。
その日の、雨の降りしきる夜半、渡嘉敷村の約三分の二の人たちが、ウンナーガーラ(恩納川)にそって苦心しながら北上した。そして、ほとんどが、上流の谷間の林の中で一夜を明かした。そのあたりには、以前に建てた避難小屋が三軒あったが、大多数は身を隠す場所が見つからず、野ざらしであった。ウシたちは、大きな木の葉を手探りで集めて、それを敷いてその上に横になり、眠るともなくうつらうつらしていた。
そのころ、阿波連の人たちは、約一時間遅れて西山にようやく到着していた。その多数は、阿波連から上陸した米軍に追われて渡嘉敷へ向かっている途中で、人々の口から「西山に集まれという村長命令が出ている」と聞かされ、渡嘉敷の人たちの後につづいたのだった。阿波連の人たちのほとんどは、それぞれ山の壕に避難していたが、食糧や衣類などは壕に残したまま、荷物らしい荷物は持たず、手ぶらの人も少なくなかった。また、壕やトカシクの野戦病院に、ケガ人を残してきた人もいた。
一方、渡嘉敷村の女子青年団は、不断から日本軍に献身的につくしていたので、いざとなったら皇国のために死ぬ覚悟ができていて、それぞれ懐中にカミソリを隠し持っていた。また防 衛隊の過半数は、何週間も前に、日本軍から一人あて二個の手榴弾を手渡されていた。いざとなったら、それで戦うか自決せよということであった。
注(又吉) 明治維新により琉球王国から沖縄県になったが、まだまだ古い封建社会のしきたりが強い社会だった。特に地方は琉球王国時代の豪族が明治以後も村の長であった。ウシのような平民にとって村長はリーダーであり支配者であった。村長の命令には従わなければならなかった。今のように自由というものは村民にはなかった。
玉砕するしかない
三月二十八日は曇天だった。木の葉の間から、チラチラと朝の光が見え、まどろんでいた村民は起きて、雨で黄色く濁った谷川の水で顔を洗ったり水を飲んだりした。ウシは弁当箱に水をくんできて、子供たちに飲ませたり黒砂糖をなめさせたりした。食事らしい食事は誰もしなかったし、そんな準備をする余裕も元気もなかった。みんな打ち沈んでいた。こんもりと潅木のおい茂っているその谷間いったいには、見渡すかぎり村民が終結していた。朝の七時ころになって、防衛隊の数人がどなるように、「みんな上のほうに集まれ」「西山盆地に集まれ」と叫んだ。それで村民は命令どおり、そこからわずか二百メートルほど離れた平たんな場所に移動した。
ウシたちが、そこの雑木林にたどり着いたときには、すでに多数の渡嘉敷の人たちが入りこんでいて、みんな十人か十五人ぐらいずつかたまって、地べたにすわっていた。しぜんに肉親を中心に親族同士が寄り集まっていた。後から後からぞろぞろと、阿波連の人たちもつづいて入ってきて、およそ千人の集団となった。それから約三時間、集められた村民はそのまま放ったらかされていた。
その間、集団の一角に、村長を中心にして、郵便局長や校長や助役や巡査や役場の人たちと防衛隊の幹部ら、約十数人が寄り集まって、何やらしきりに協議していた。そのころになると、上空には敵の偵察機がぐるぐる回っていた。茂った木の葉から、ときどき敵機がよぎって行くのが見えた。「これからどうするかという意見を出し合ったが、話し合っていくうちに、玉砕するほかはない、という結論になってしまった。しぜんに、玉砕ということになって、その恐怖感から逃れられなくなった」(比嘉喜順らの証言)
そこで気丈夫な古波蔵村長は、具体的にどういうふうにするか、と話を進展させた。あれこれ意見が出たが、結局、みんなが死ぬにしては、手榴弾が足りないということになった。一人の防衛隊が、「友軍の弾薬貯蔵庫から、手榴弾を取ってきましょうか」と申し出たことから、それに一決して、不断から親しく兵隊と接触している防衛隊三人が出掛けることになった。
それから一時間後に、防衛隊によって、ひそひそと村民に「玉砕する」話がひろめられた。村の指導者たちは、バラバラになって、それぞれの家族や親戚の人たちに、「やさしく説得するように」玉砕のことを話した。阿波連の防衛隊たちは、少し離れて散在しているの人たちに、もっと中心に寄り集まるようにいい伝えた。
集まった村民は、恐怖に打ちおびえながらも、静かに親族同士で輪になってすわった。渡嘉敷の人たちは、比較的に荷物を持ち運んできていたので、死ぬ覚悟を決めて着替える人が少なくなかった。が、集団のはずれにいる人たちの中には、まだ暖昧な気持ちで、これから何が起こるか、何もわからず、集団自決を予想だにしない人たちがいた。
古波蔵村長は、次のような理由から、駐在巡査を通じて赤松隊長から玉砕命令が出たにちがいないと、ひそかに思っていた。西山にきて協議の緒果、いわぱ自発的に玉砕することになりはしたが、昨日、安里巡査一人が赤松隊長に逢ってきた結果、集合が決まったこと、それから安里巡査は一人死ぬのを避けるふうに、「自分は村民の玉砕を見とどけて、軍に報告したい」(米田惟好<当時の古波蔵村長>の証言)といって、いざというときには少し離れたところに彼一人立っていたというのである。(注・米田惟好の解釈―軍は持久戦を考えて食糧確保のため、村民に対し「ロベらし」「足手まとい」だと思ったにちがいない)
注(又吉) 村長、郵便局長、校長、助役、巡査、役場の人たち、防衛隊の幹部らが協議して集団自決を決めている。村長など地位ある人たちの多くは武士の子孫であっただろう。日本軍が勝利するためには村人が自決したほうがいいという選択をしたのはあり得ることだった。
「みんな一緒に死のうね」
「アメリカーが上陸して、家も焼かれてしまったし、帰るところもないし、どうせ死ぬならみんないっしょのほうがいい」とウシの弟の防衛隊が話しているとき、安里巡査がきて、「手榴弾が破裂するときは手にしっかり握っていたほうがよい」と助言した。それから間もなくして、古波蔵村長がみんなの中央に立って、「敵にとり囲まれてもう逃げられないから、玉砕しなければならない。大和魂をもって天皇陛下万歳をとなえ、笑って死のう」と、声をふるわせながらいった。
急にしーんと静まり返った。ウシはその気になって、誰かが持ってきた茶わんに水を入れて、みんなの前に差し出し、「みんないっしょに、あきらめて、死のうね」といい終わるか終わらないうちに、遠くで誰かが「発火用意、打て!」と叫ぶと同時に、ぱあーんぱあ-んぱあーんと、つづいて手榴弾の炸裂音が聞こえた、ウシはわなわな震えがきて、水をこぼしたとき、急に耳を強く打たれたようになって、何が何やらわからなくなった。
ウシが気がついたときには、彼女自身は三歳の子供を抱いたまま僻せになっていた。目の前に倒れている二人の娘も無傷でねぼけたような顔で起き上がった。が、手榴弾を持っていた弟は、断末魔の様子で、血だらけの片手をがたがたふるわせて倒れていた。その背後には、弟の妻が、両眼をほおの上にとび出させたまま、死んでいた。
ウシはわが目を疑い、からだをまるめて俯せたままで、まわりをながめた。と、たくさんの死体がころがっているのを見届けると同時に、まったくとつぜん、鳥が泣き叫ぷようないやな声が入り乱れて聞こえてきた。
「アキサミヨーアキサミヨー」(感嘆詞)「母ちゃんよー母ちゃんよー」「アンマーヨーアンマーヨー」(母親の呼称)と悲痛におおぜいが叫んでいた。頭上からはブーンブーンブーンと敵機の爆音が響いていた。ウシは動転し、しばらく目をとじていた。が、ふたたび周囲を見まわした。手榴弾を破裂させた弟は死に、そのすぐ側にいた自分たちは無事だったのだ。そして、まわりにいた親族の七、八人は即死していた。それからウシは、何やらうめきながら逃げて行く集団を見た。
赤い血を鮮明につけたケガ人たちや、恐怖のあまり泣き叫ぶ女子供たちをまじえて、約三百人あまりが、わさわさ押し合うようにしてそこから立ち去って行くのだった。その逃げて行く集団の中に、郵便局長と村長がいるのがはっきり見えた。
……集団自決の場所から群をなして立ち去ってきた約三百人は、日本軍の陣地のほうへ向かってなだれたが、三百メートルも行かぬうちに、米軍の迫撃砲の攻撃を受けた。米軍の砲弾は、どこからくるのか判然としなかったが近くでどんどん炸裂した。その破片にあたって即死したものが幾人かいた。弾にあたって郵便局長の妻も倒れて死に、局長は子供を背負わなければならなくなった。その集団は、そこで立ち往生したまま、騒いでいた。
村の指導者たちやその家族や防衛隊の幾人かは、そろって無事で、その集団にまじっていた。みんなひどく興奮していて、狂人のようになっていた。村長は狂ったように逆上して「女子供は足手まといになるから殺してしまえ。早く軍から機関銃を借りてこい!」と叫んだ。その意志を率直に受けて、防衛隊長の屋比久孟祥と役場の兵事主任の新城真順は、集団より先がけて日本軍陣地に駆けこみ、「足手まといになる住民を撃ち殺すから、機関銃を貸してほしい」と願い出て、赤松隊長から「そんな武器は持ち合わせてない」とどなりつけられた。(注・比嘉喜順、伊礼蓉子らの証言。その点、米田惟好は米軍に決死の戦闘を挑むつもりだったと、異議を申し立てている)
おりしも助けを求めてなだれこんだその集団は、日本軍陣地の百メートル近くまできていた。日本軍は戦闘配置についていたが、発砲は自滅に等しいとみて、ただ敵の様子をうかがっていた。そこへ泣き叫ぶ村民がなだれこんできたので、追い払うために、将校は一様に抜刀して威嚇した。たちまち村民は悪夢からさめたように静まりかえり、恩納川の谷間へと散り散りに去って行った。
修羅場と化した西山盆地
一方、西山盆地では、ほとんど無傷でいた阿波連の人たちの間から、無残な殺し合いが始まっていた。それは三百人の集団がアラシのように立ち去った直後だった。遠くで、迫撃砲が激しく炸裂するのを、生き残っている多数の村民は上の空で聞きながら、ある人たちはナタやガマを借りて生ま木を切って棍棒を作っていた。その側で、母や妹や弟を、青年になった息子が、ベルトでつぎつぎと締め殺していた。また手榴弾で死にそこなった渡嘉敷の人たちの間では、持ってきた農具がそのまま凶器に変わって、血縁へ向かって理解しがたい怨念を打ち出すように、妻子を惨殺しはじめた。
ウシたち親子四人は「ここは地獄だ、早く逃げよう」と、いったんそこから立ち去りかけたが、血相をかえた阿波連のお婆さんたちが下のほうからきて「下からオランダー(外人)が登ってくるよ、いまに耳や鼻を切り取られるよ」といわれ、こわくなって舞い戻った。アメリカ人につかまることへの恐怖感がつのった。ちょうど十メートルぐらい離れたところに、夫の妹たちが生き残っていて、茫然とすわっていた。そこには、ケガして歩けない人たちが二十人ぐらい集まっていた。ウシたちはそこへ助けを求める気持ちで行った。すぐ側で、イノハさん(医者)は、不発弾の手榴弾を何度も石にたたきつけていた。
彼はあきらめて、それを投げ捨て「何かないか」とキョロキヨロしていた。そのとき小学生の息子が、「お父さんポク肥後ノ守があるよ」と小刀を出した。するとイノハさんは、「お母さんからね」というとすぐ、自分の妻の首を切り、それから息子と娘の首も、つぎつぎと切って、見ているまえで、彼は木の股に小刀をはさんで、自分の首を押しあててずっと刺しこみつづけた。そして急にガクンとぐったりなってころがり倒れた。
それが契機となって、隣の家族は、急に殺気立って、妻がおびえている夫を叱った。「日本人じゃないの! あんた男のくせに殺しきれないの!」と中年の女は、ナタを振り上げ、すわっている四、五歳の女の子の頭をめった打ちにして殺し、それからうなだれている夫を、「エイ、エイ、エイ」と叫びながら同様に打ち殺した。すると連鎖的に、老人が孫の頭をつかんで、カマでその頸動脈をかき切った。血が倒れた首から噴き上げた。
「アキサミョー」(感嘆詞)「私も殺してください」とウシは思わず叫んだ。だが老人は、振り向きもせず黙って木に登り、首つりのしたくをするのだった。
ウシが気が変になったように、「クルチ、クミソウリ」(殺してください)と小声で繰り返し言っているとき、七歳になる二女は「死にたくない、死にたくない」と泣き叫んだ。長女は妹を腹の下に隠すように押えつけ、ただ恐ろしさのあまりじっとしていた。そのとき、阿波連の青年たちがワイワイ騒ぎ立てながら走ってきた。血の気のない顔で、彼らは何やら奇声をあげ、まだ生きている人を探し出しては、持っている梶棒で撲殺するのだった。
その中の金城重明(現牧師)という十六歳の少年がウシの側へ近寄ってきた。学校で成績がよいと評判の少年だった。彼は立ち止まった。と、いきなり直径十センチぐらいの棍棒を振り上げ、「まだ生きているのか!」と叫び、妹を抱き押えて後込みしている長女の頭へたたきつけた。ギャツという声が短く走り、頭から血が流れた。少年はもう一度たたきつけた。娘たちは動かなくなった。それから少年は血走った目をむいて、ウシを見た。ウシは祈るように、「重明……」と小声でいって目を閉じた。ガーンと頭が割れるような音がした。ウシは額の上を二度叩きつけられるのを感じた後、意識を失った。
何時間かたって、ウシも長女も意識を取り戻した。夕方間近くなっていた。周囲は死者ぱかりだった。首つり自殺をとげた死体が、十五、六人、潅木にぶらさがっていた。二女は痴呆状態になってすわっていた。ウシが抱いていた子供は、口がほおのところへ移って顔がゆがんでいた。ウシの額に振りおろされた棍棒は勢いあまって子供の顔にもあたったようである。
ウシは急にわれに返って、娘に、「水をくんできて」と叫んだ。娘はふらふら立ち上がり、ころがっている薬カンを拾って、水をくみに行った。その間、ウシは自分の顔いっぱいについている血糊をソデでふき、割れた前頭部からまだ血か流れるのを防ぐために、湿った赤土を取って傷口に塗りこんだ。それから娘がくんできた水を、抱いた子供の顔にかけた。すると子供は全身ひきつらせ、顔をぶるぶるけいれんさせて、元に戻った口から血のアワを出した。「生き返ったよ」と、ウシは思わず笑顔になった。
それからウシたち親子四人は、なんとか生きようと思い、谷間のほうへ下りて行った。
終わり
星雅彦氏のドキュメントは集団自決の現場の人物をリアルに描いている。集団自決をした理由はそれぞれの立場や思想や感情の違いがあり複雑であった。
〇古波蔵村長(三十三歳)
「玉砕しかない」「敵にとり囲まれてもう逃げられないから、玉砕しなければならない。大和魂をもって天皇陛下万歳をとなえ、笑って死のう」
古波蔵村長は在郷軍人であった。彼自身が熱烈な軍国主義者であっただろう。彼にとって戦争に勝つのが最大の目的であった。勝つためには日本軍の足手まといになる村人は自決しなければならないと考えた。
〇ウシ
「みんな一緒に死のうね」「アキサミョー」(感嘆詞)「私も殺してください」
軍国主義の教育を受けていない。あるいは影響を受けていない人であった。しかし、上の人の命令は絶対であると考える琉球王国時代の農民の思想を持った人である。ウシにとっては村長の命令は絶対であった。村長の命令があったから自決しようとしたのである。しかし、ウシには自決しなければならない理由を心から理解することはできなかった。ウシにとっては強制された死であった。強制された死では自決することはできない。だから人に殺してもらおうとした。
〇村の女
「「日本人じゃないの! あんた男のくせに殺しきれないの!」
軍国主義教育の影響を受けた人である。国のために死ぬのが日本人としての誇りであると教えられ、それを信じた彼女は日本人になろうとして自決をしたのである。
〇医者のイノハさん
「何かないか」「お母さんからね」
エリートであるイノハさんは軍国主義国家では軍国主義に従わなければならないと考えていただろう。エリートであるがゆえに軍国主義を理解し、軍国主義に従ったのである。
〇渡嘉敷村の女子青年団
不断から日本軍に献身的につくしていたので、いざとなったら皇国のために死ぬ覚悟ができていて、それぞれ懐中にカミソリを隠し持っていた。
軍が政権を握ってからは軍国主義教育はますます強化されていく。若い人たちほど軍国主義教育の影響を強く受け、国のために自決する思想は強かった。
〇防衛隊
何週間も前に、日本軍から一人あて二個の手榴弾を手渡されていた。防衛隊員も女子青年団と同じであった。
〇金城少年
「まだ生きているのか!」
成績が優秀であったがゆえに軍国主義教育をうのみにし軍国主義少年になった。国民は天皇ため、国のために死ぬと教えられ、それを心の底から信じていた。教育の責任の重さを知らなければならない。
〇赤松隊長
「そんな武器は持ち合わせてない」
マルレで敵艦に特攻して死ぬために渡嘉敷島に来た赤松隊長は若干二十五歳の若き日本軍将校であった。軍人は天皇陛下と国のために戦うという信念の強い彼は米軍と戦うことしか念頭になかった。国民である村人は軍隊が守るという考えだったから集団自決は赤松隊長にとっては考えられないことだった。
渡嘉敷島の集団自決が起こったのは軍命令があったからではない。日本が軍国主義国家になったこと、軍国主義教育が浸透していったこと。米国との戦争で敗北していったこと、渡嘉敷が離島であったこと、沖縄の古い思想が残っていたことなどが複雑に絡まって起こったのだ。集団自決の場では多くの人間模様があり、自決の原因もそれぞれに違う面があった。
日本の勝利のためには「村人の玉砕しかない」と村人を集めて、真っ先に自決しようとした古波蔵村長であったが自決に失敗した。その後は再び自決をしようとはしないで戦争を生き延びている。人間には死の本能はない。生の本能がある。「命どぅ宝」である。自分で自分を殺すというのは人間の本能に逆らうことであり、そのためにはぎりぎりまで自分を追い詰めなければできないことである。大変なエネルギーが必要である。自決に失敗した村長たちにもう一度自決をするというエネルギーは残っていなかった。だから生の本能によって生き延びたのである。
軍国主義思想、軍国主義教育、沖縄の古い思想が入り混じった離島社会に米軍が進攻して起こった悲劇が慶良間島の集団自決であった。軍命令で集団自決をしたというような単純なものではなかった。集団自決の現場は自殺と殺害が交錯した凄惨な修羅場であった。
集団自決の深層に素直な目で入っていきそれを受け止めることが私たち沖縄人のやるべきことである。
最近、沖縄二紙やマスコミでは「『集団自決』(強制集団死)」という表現をするようになった。強制集団死とは軍が強制したから「集団自決」をしたのだという意味である。「集団自決」という表現では、自ら死んだという印象が強く、軍の強制で死んだというイメージが弱いと考え、軍の命令で死んだという印象を強くするために(強制集団死)を使っているのだろう。
自決の思想を浸透させた戦時中の教員、公務員、政治家、識者などの責任を回避し、集団自決の真実から目を背け、なにがなんでも日本軍に責任を押し付けようとして(集団強制死)という文言がつくられた。
自決は人間の生の本能を断ち切る極限の決断であり非常に重いものである。(集団強制死)は日本軍の命令に自決した人々がロボットのように従った印象を与えるものであり、集団自決の真相に蓋をするものである。人間の生の本能を軽視するものである。
(集団強制死)が集団自決を軽視した残酷な文言であるあることを知るべきである。
 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

新発売・「かみつく5」は県内書店で発売中
狼魔人日記でネット全国販売しています。
申し込みはメールでできます。
ブログ 狼魔人日記
メール ezaki0222@ybb.ne