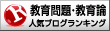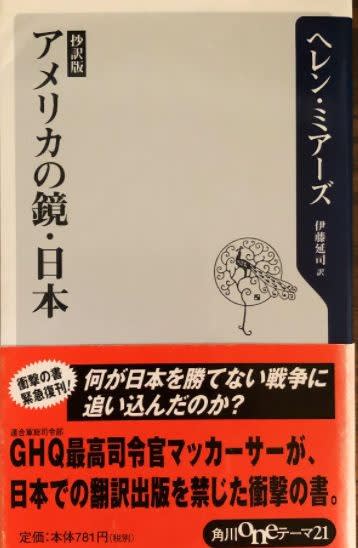[大弦小弦]「島守の塔」を見る
公人を評価する軸は、業績か人柄か。公開中の映画「島守の塔」は、そんな問いを生む。沖縄戦に協力した島田叡知事と荒井退造警察部長の苦渋を描く
▼北部疎開という棄民政策を進め、学徒を戦場に送った2人の内務官僚は人格者だった。同様に、日本軍の牛島満司令官も「温厚篤実」と評された。では、牛島を「いい人」とたたえる映画は成立するか。人柄は責任を洗い流さない
▼映画化は荒井の地元栃木県の下野新聞社と、島田の地元兵庫県の神戸新聞社が呼びかけた。2人は郷土で「偉人」とも呼ばれる
▼製作委員会には沖縄タイムス社と琉球新報社も参加した。作品は沖縄の人々が身をもって知った「軍隊は住民を守らない」事実も伝えるが、全体の基調は「戦場に咲いたヒューマニズム」。結果、日本の加害、沖縄の被害という構図はぼやけた
▼監督は「沖縄戦を知るきっかけに」と話す。学ぶ目的を、考えてみる。お年寄りが、身を削るように体験を語ってくれた理由を。それは次の戦争を止めるためではなかったか。止めるためには、惨劇が起きた原因の解明が欠かせない
▼劇中、うそだらけの新聞発行を終えた記者が言う。「次に新聞を作る時は、戦争の事を、何が起きたかを、本当の事を、報道したい」。負の系譜の末端に連なる者として、責任のありかを問い続ける。(阿部岳)
GHQの東京裁判史観にからめとられた沖縄タイムスは、『鉄の暴風』が説く「残虐非道なに日本軍」というイデオロギーを脱皮できず、現在でも日本軍極悪説を主張し続けている。
中国の工作員と噂の高い阿部岳記者は、『鉄の暴風』の初版の「まえがき」に記載された「人道的な米軍」を今でも信じているのだろうか。
以下過去ブログの再掲です。
改訂版・沖縄戦、厚生省に引き継がれた「特別のご高配」(援護法の解釈)2019-08-23
沖縄の学童疎開船・対馬丸が米軍の魚雷を受け撃沈。8月22日で75周年になる。
今日23日の沖タイは一面トップを含む合計三面を使って大発狂である。
■一面トップ
対馬丸 鎮魂の祈り
撃沈75周年 慰霊祭に550人
■第二社会面トップ
幼い兄に平和誓う
島袋さん、自ら遺影を掲示
■社会面トップ
75年 癒えぬ悲しみ
「戦いは絶対許せない」
対馬丸慰霊祭 生存者ら継承誓う
沖縄戦対馬丸撃沈の記憶の継承という建前に異論はない。
だが、沖縄メディアが沖縄戦を語るとき、他県には見られない特徴がある。
あたかも沖縄戦は日本軍と沖縄住民の戦いだったかのような論調で「残虐非道な日本軍」を執拗に告発するのだ。
対馬丸を撃沈したのは米軍の潜水艦であり、日本軍ではない。
明らかに米軍による民間人虐殺だ。 沖縄タイムス編著『鉄の暴風』が説く「人道的米軍」とは対極のジェノサイドだ。
しかし、沖縄2紙が「対馬丸」を報じるときは加害者はあたかも日本軍であるかのような印象報道をする。
曰く「食糧難の当時、口減らしのため学童を強制疎開させた、そのため多くの犠牲者が出た」という印象操作だ。
「石油の一滴は血の一滴」と言われた石油不足の戦時中、戦火を避けるための疎開を悪意に満ちた歪曲報道で県民を煽るのが沖縄2紙の常道だ。
その一方で敵の米軍は、沖縄住民を解放するため沖縄戦に臨んだという印象報道。
沖縄の地上戦突入前、学童疎開は老幼婦女子の避難というより、(1)戦闘の邪魔にならないようにする(2)食料確保のための口減らし(3)明確に示されていないが次の戦闘員確保-という軍事的な戦略として行われた。背景に1937年、日中戦争の本格化の中で改正された軍機保護法がある
■援護法と歴史捏造
沖縄戦の真実を追究するといつも行く手に立ちふさがる大きな壁に行き当たる。
「援護法」のことだ。
本来軍人・軍属にしか適用できない同法を当時の厚生省が「拡大解釈」で無理やり沖縄の民間人に適用した。
その善意が逆に「残虐非道な日本軍」と言う神話を捏造した。 軍の命令による民間人の戦争被害は準軍属扱いで同法の適用可としたのだ。 「壕を追い出した」のも日本軍の命令であり、「食糧強奪」も日本軍の命令と政府は「指導」した。
その結果沖縄だけは民間人も援護法の適用を受けるという恩恵に浴した。
「沖縄県民かく戦えり」で知られる大田海軍司令官が、「県民に対し後世特別のご高配を」と結んだ長い電文は沖縄県民の奮闘をを知る故に、沖縄に対する深い敬愛や同情もあってのことと思われる。
沖縄戦史が歪曲・捏造された原因が「援護法」の「拡大解釈」にあることは、少しでも援護法と沖縄戦の関係を知るものにとってはよく知られた事実である。
「援護法と歴史捏造」について触れた過去記事から選んで引用する。
★
63年前の昭和20年6月6日。
大田実海軍少将は、沖縄県南部の海軍濠から長文の電文を海軍省に送った。
そして、その最後を次のように結んだ。

<沖縄県民斯く戦えり。
県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを。>
打電を終え、大田実海軍少将はその一週間後、現場で自決する。
享年54歳。
なお現場の大田司令官が打電した相手の多田武雄海軍次官は終戦の8年後、62歳で没している。
沖縄戦の現場で県民と共に戦い、県民の蒙った惨状を見かねて戦後の県民の行く末までも心配して打電後自決した大田実少将。
この大田少将に対する県民の態度は冷たい。
これも地元メディアの影響か。
戦後、日本軍批判の先鋒を担いだ『鉄の暴風』(沖縄タイムス刊)と言う言葉の原型は大田少将の「沖縄島は形状が変わるほど砲撃され草木の一本に至るまで焦土と化した」と言う電文に伺い見れる。
「鉄の暴風」で沖縄島の地形を変える程の焦土作戦を行こない無差別に住民を殺戮したのは米軍であることは間違いのない事実。
ところが何故か、戦後この言葉は日本軍人を糾弾するキーワードと化す。
県民は「鉄の暴風」の艦砲射撃で県民を爆撃した下手人の米兵の顔を直接見ていない。
米軍は沖縄住民を日本人から分断する占領方針から、沖縄住民には「優しく」対応するように努めていた。
沖縄住民は、やっと命が助かりほっとした時に、年寄りや子供に手を差し伸べる優しい米兵の顔だけしか見ていない。
艦砲射撃という「鉄の暴風」を吹き荒れさせ、住民を無差別殺戮し、学童輸送船を撃沈させた米兵のもう一つの酷薄な顔を見ていないのだ。
一方、沖縄県民を守れず、食料補給もままならず、痩せこけて、圧倒的物量の米軍の前に醜態を晒した敗残兵としての日本兵の顔を沖縄住民は現場で見ていた。
そしていつしか「鉄の暴風」を実行した米軍ではなく、そういう状況に沖縄住民を陥れた日本軍こそ敵、と言う理屈に一気に飛躍する。
食べ物をくれた米軍は解放軍。
「鉄の暴風」を防止できなかった日本軍は敵軍、という理不尽な論理だ。
その結果が、復帰後続く「物呉ゆしどぅ我御主」、「命どぅ宝」の伝説である。
県民と共に戦い、県民の行く末を案じつつ現場に散った大田司令官と海軍将兵の霊に、
合掌。
|
*

■厚生省に引き継がれた「特別のご高配」
大田少将の電文の遺言ともいえる「県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを」は、厚生省に引き継がれ、
「沖縄の特殊事情」或いは、「沖縄に特段の配慮を」
と形を変えて戦後の沖縄のいろんな場面に登場する。
意味は全く違うが、最近でもこんな例もある。
⇒「沖縄に特段の配慮」 唯一県名挙げる 国民保護方針(2005.3.27)
◇
■「特段の配慮」による「援護法」の民間適用■
大田少将の遺言は、厚生省の本来軍人対象の「援護法」を沖縄住民へ適用するという形で姿をあらわす。
日本政府は「1952年(昭和27年)6月、米軍占領下の沖縄に政府出先機関である南方連絡事務所を設置する。 今でいえば沖縄開発庁の先駆けのようのものである。
そして教職員組合と遺族会の強力な後押しによって、琉球政府でも翌53年4月に援護課を設け、援護法と恩給法に基づく復員処理事務に着手することになる。
54年には琉球政府職員照屋昇雄さんが援護課に異動配属となっている。
慶良間島の「集団自決」に関しても、村役場の総務課が地元の窓口となり、総務課長の宮村幸延氏が「援護法」の住民への適用のため奔走する。
「援護法」は講和条約発効直後の1952年7月に制定されたが、沖縄には1年遅れて適用が制定された。
■「軍命」の持つ意味の変化■
「集団自決」は、1952年(昭和27年)前後から、その持つ意味に変化が起き始める。
「集団自決」が軍命令であるという記述は1950年(昭和25年)に発刊された『鉄の暴風』に見られるが、
それまでの「軍命」は、「援護法」のための口裏あわせというより、親族や縁者を手にかけた生存者が、遺族の糾弾や贖罪意識を逃れる為、「軍命でやむを得なかった」という言い訳のための「軍命」だった。
つまり生き残った者が、死んだ相手や世間に対して言い訳するための「軍命」であった。
少なくとも、当時の座間味村助役の山城安次郎氏が、「渡嘉敷島の赤松の暴状」を訴えて沖縄タイムス大田記者の取材を受けた昭和25年前後には、
「集団自決」の「軍命」は援護法のためというより、むしろ死者へ対する贖罪意識のために必要だった。
ところが、琉球政府援護課や村役場の担当課が、厚生省援護課と交渉していく過程で「集団自決」の「軍命」は別の意味を持つようになる。
元来「援護法」は「復員処理」の目的があり、対象者は戦地での戦死者か外地からの引揚げ者で、しかも対象は軍人・軍属と限られていた。
そこで琉球政府援護課と村役場が、地上戦が行われ戦場となった沖縄に「特別の配慮」をするようにとの運動を展開する。
だがこれには問題が生じてきた。
たとえば、本土の場合、東京空襲や広島、長崎の原爆で死亡した一般市民の場合は援護法の対象にもならず、沖縄の一般住民に「特別の配慮」をした場合の齟齬が問題になったのだ。
日本政府は「政令」を連発するという非常手段でこれを乗り切った。
政令とは、行政府の命令のひとつで内閣が制定する成文法のことで、行政機関が制定する成文法である命令の中では優劣関係で最も高い位置づけになる。
日本政府は復員事務を処理する必要から、沖縄本島を中心とする南西諸島は政令で「戦地」と認定した。
元々軍人・軍属を対象にした「援護法」を沖縄の民間人に適用させるために政令を連発したが、それでも足りない場合は「援護法」の拡大解釈を行った。
一例を挙げると、地理に不案内な軍に道案内をした場合でも、結果的にその住民が戦死しておれば、「軍命」とされ「準軍属」扱いで遺族は年金の対象になった。
軍の命令というお墨付きが付けば「集団自決」は勿論のこと、他にも「食料供出」や「漁労勤務」という名目でも「準軍属」扱いとなった。
かくして、1983年には軍の命令が理解されるとは思われない0歳児から6歳までの幼児も「準軍属」扱いとされるようになる。
■宮村幸延総務課長の奔走■
座間味島の助役で、事実上「集団自決」を命令したとされる宮里盛秀氏の弟で、戦後村の総務課長として「援護法」の適用に奔走した宮村幸延氏は、この0歳児以下の適用に功績があったとして村で表彰されている。
ちなみに宮村氏は梅澤元隊長に「侘び状」を書いていながら「酔わされて書いた」として前言を翻した人物である。
また、昨年の法廷尋問のわずか一ヶ月前に証言して、宮城晴美氏の考えを変えた宮平春子氏は宮里盛秀、宮村幸延両氏の妹である。
「集団自決」に「軍命があった」ということは「事実の如何」を問わず、戦後の村にとっては、どうしても押し通せねばならぬ真実を超越した、必要欠くべからざる「証言」であった。
宮平春子氏の証言「動画」
⇒ 『日本軍の強制による集団自決 はあった!』証言2.3.4
■本土と沖縄の齟齬■
本土の場合、東京空襲や広島、長崎の原爆で死亡した一般市民の場合は援護法の対象にもならなかった。
一方、沖縄の一般住民は「特別の配慮」で援護法の対象になった。
静岡県浜松市在住の上原宏日本戦災遺族会理事長は、本土における一般戦災者に補償がない点を、
沖縄タイムスの取材に答えて次のように語っている。
[戦闘参加者とは誰か](18)
日本戦災遺族会
一般戦災者に補償なし
被害の規模が実現阻む
太平洋戦争で、日本の各都市が空襲に襲われ、一般被災者約五十万人が犠牲になったとされる。その補償を求めて、一九六六年に「全国戦災死没者遺族会連合会」が結成された。七七年には「日本戦災遺族会」と名称を変更、事務局を東京都千代田区に置き、現在全国二十地域に約二千人の会員がいる。
理事長の上原宏さん(84)=静岡県浜松市=は、浜松市戦災遺族会の会長を務める。
浜松市は、多数の軍需工場や軍施設が集中していたため、米軍の空襲が反復して行われ、約三千五百人もの死者が出た。上原さんは、この空襲で女学校二年生だった妹を自宅の防空壕で亡くしている。「空襲は、非戦闘員を狙った消滅作戦だった」と憤る。
一般被災者の場合、戦時中は「戦時災害保護法」で、住宅焼失は三百五十円、負傷は治療全額補償がなされていた。ところが、戦後、一般被災者への補償はなされていない。日本の戦災補償は、軍人軍属を補償した援護法が軸になってきたからだ。
援護法は、国との雇用関係が前提。しかし、法運用の中で、対象の「軍人軍属」の枠は次第に拡大されてきた。五八年に沖縄戦の「戦闘参加者」、全国でも五九年「学徒動員」、六三年「内地勤務軍属」、六九年「防空監視隊員」など。
そうした流れから、上原さんは「最後に残ったのが一般戦災者だ」と強調する。「現状は、けがの状態から、障害福祉年金などを受けている。しかし、それはけが人としての補償である。戦争による同じ『死』でも、差があるのは納得いかない」
また、上原さんは「私は一般被災者は約八十万人とみている。空襲時の戦死だけでなく、その後に戦病死、戦傷死が続いたからだ」と指摘する。この一般被災者の被害の多さが、補償が実現しない要因でもある。
連合会の前身「全国戦災死没者遺族会連合会」の時代、戦災各都市での慰霊行事への国費支出、弔慰金支給を国会と自民党に要望した。しかし一般被災者への弔慰金支給は実現していない。
連合会が七七年に社団法人化した時に、一般戦災者の戦災実態の調査研究、慰霊行事や慰霊碑の管理などを主に掲げ、補償要求は掲げることはなかった。
届かない補償要求。上原さんらが、力を入れているのは、戦争体験の継承だ。自らも、満州(中国東北部)、フィリピンの従軍、マニラへ向かう途中撃沈され、仲間を失った体験を「語り部」として小学生に話してきた。「遺族は高齢化し、消えていく。私たちの体験を伝えるために、会員それぞれが語り部活動をやっている」
一方で、「浜松空襲で亡くなった妹のことはつらくて話せない」という。遺族が向かい合う悲しみは戦後六十年たっても、何も変わらない。「遺族は本当は、補償をしてほしい。戦後六十年の節目に、扶助と慰霊を同時にしてほしいんです」と訴える。(社会部・謝花直美)(2005年3月26日 沖縄タイムス)