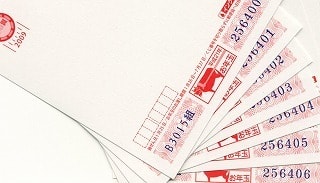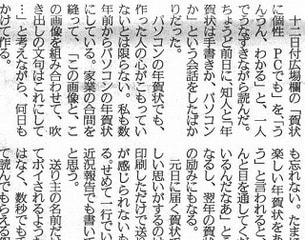
今日の中国新聞広場、「12日付け広場欄の『賀状に個性 PCでも』を『うんうん、わかる』と、1人でうなずきながら読んだ。ちょうど前日に、知人と『年賀状は手書きか、パソコンか』という会話をしたばかりだった」という、広島市西区にお住まいの方の投書が掲載されていた。
その投書は「心感じる賀状を送ろう」というタイトルで載っている。文面は続けて、数年前からパソコンの年賀状にしている。画像と画像の組み合わせ、吹き出しの文句の工夫など、完成までの悩みや楽しみが述べられている。受け取った方の喜びの声が嬉しい、とも書かれている。
この投稿を促した12日掲載分の投稿者としては嬉しい反応だ。投稿のきっかけは、PCで年賀状を作成される熱心な講座受講者の姿を知っていたからでした。ブログやメール、電話などでも感想をもらった。今朝も遅くなったがと感想が電話で届いた。
そのなかで「どうしてもちょっと引き気味になっていたパソコン年賀状を、時代の流れを背景に、見事にメジャーに引き上げた」というコメントを頂いたが、いささかくすばゆい感じもした。熱心な受講者がその牽引役であったことをもう1度付け加えます。
年賀状は年に1度の挨拶や近況を知らせたり受け取ったり、先の広島市西区の投稿者は「数秒でも手にとって読んでもらえる賀状を出すよう心掛けたい」と結んでおられる。同感するだけでなく実践をしたい。
(写真:賀状への心構えが書かれた投稿の1部)