

「私たちは患者ではなく人です」、朝日連載「認知症」に元気をもらった
朝日新聞に連載されている「ニッポン人・脈・記」に、「認知症とわたし」が、9月27日から不定期で10回にわたって掲載された。一昨日・12日が最後の回だった。その時々の掲載は目を通していたが、それまで切り抜いていたものを昨日ゆっくりと纏めて読んだ。
この10回の「認知症とわたし」を読み、今深い感動を浸っている。人間は素晴らしいし、「認知症」になっても人間らしく生きて行けると。これまでは老いとともに、「認知症」への恐怖がいつも頭の中にあった。それは、家族へ迷惑をかけたくないという思いからだ。家族に迷惑をかけることは否定できないが、それでもネガティブに考えテいたことを深く反省もした。
朝日が取り上げている方々は、みなさんとても素晴らしく、みんながみんなそのような生き様を可能とはしていないことは間違いない。それでも、そうした可能性があることを知れただけでも、とても嬉しい。朝日新聞が原発に対しては屈服しているのは怒りを禁じ得ないが、それでも文化面を含めて「直接的に政治的でない」記事は充実していると思ったりもする。
新聞記事の中で、見つけた素敵なフレーズを紹介する。「私たちは患者ではなく人です。私たちが病と向き合う力を奪わないで、励まし元気づけてください」、「認知症でもできることはあると知ってもらいたい。病気になっても隠さなくていい社会になってほしいから」。
今、認知症の患者は300万人と言われている。ご近所力と介護の力があれば、住み慣れた家で暮らせることを、この連載は教えてくれた。大いに元気をもらった。



「復興のために負担を」と増税しておきながら、その使途を聞いて怒り心頭だ
昨日、日本年金機構から「大切なお知らせ」のハガキが届いた。年金の支給額の変更以外には、今は連絡がない仕組みとなっており、何だろうと開けた。内容は「介護保険料の特別徴収額が変更になり、個人住民税が特別徴収されたことによる、年金払い込み額の通知」だった。
介護保険料も住民税も、わずかな年金から遠慮会釈なく引いてくる。ダメとは言えない仕組みを作って、取り外れのないようにしている。それにしても、国保料も含めて、税や社会保険料の高さには、ほとほとほ参ってしまう。もう暮らしを切り詰めるのも限界が来ている。
そんなにしてまで納付しているのに、その税金の使途について考えてしまう。現在の民主党政権は、「11年夏に政府が決定した復興基本方針で『5年で少なくとも19兆円』が、被災地の復旧・復興に必要な予算と見積もった。そしてその財源を捻出するため、所得税や住民税などを臨時増税し、10兆5千億円をまかなう」ことと決定している。つまり私たち国民から増税して、それを「被災地の復旧・復興に充てる」筈だった。

ところがである。昨日・13日付け朝日新聞のトップ記事には「復興予算 被災地中心に 官庁・国道整備認めず」とあり、三面では「復興『便乗』 緩む財布」とあり、「被災地以外で復興予算が使われる主な事業」が列挙されている。九段合同庁舎や海上保安学校の耐震改修、沖縄・未使用トンネル周辺工事、北海道・月寒刑務所や埼玉・川越少年刑務所での職業訓練のためのパワーショベルカー計4台。さらには、今日の報道では防災対策費で自殺対策に37億円が使われているとのことだ。こうした「復興予算」の使われ方を知って唖然として、怒りがふつふつと湧いている。
「5年間で19兆円」との大枠は、現実には13年度予算の概算要求を含めると、3年間で22兆円に達する見込みという。被災地や被災者のために実際に有効に使用されているのなら、予算超過は大いに歓迎する。ところが、寄ってたかって、「『復興』を名目に、予算獲得に狂奔する各省庁」。そしてそれにOKを出す政府・財務省という構図が見えてくる。こうしたことを絶対に許してはならないと考える。
その使われた予算が、苦しい国民生活にも知らん顔で搾り取った増税による税金だということを、政府・民主党はどう考えるのだろうか。いい加減にして欲しい。そして、一刻も早く被災地の真の復興と被災された方々の生活再建のために、「被災地に寄り添って」必要な予算を適切に支出して欲しいと願う。



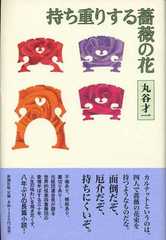
私に「浅学非才」さを痛感させた『裏声で歌へ君が代』の著者が亡くなられた
「豊かな教養を背景に『笹まくら』や『たった一人の反乱』など、知的で明るい物語性に満ちた小説を書き続け、評論や翻訳でも知られた作家の丸谷才一(まるや・さいいち、本名・根村才一=ねむら・さいいち)さんが13日、心不全のため東京都内の病院で死去した。87歳」。作家丸谷才一氏が、昨日亡くなられた。新聞各紙が、その死を報じているし、様々な関係者の談話なども掲載されている。
丸谷才一はほぼ10年ごとに書き下ろしの新作を発表し続けてきた。実質上のデビュー長編『笹まくら』(長編第二作、河出書房新社)を発表した翌年の1968年に、「年の残リ」で芥川賞受賞を受賞。その後1972年に長編小説第3作『たった一人の反乱』(1982年・講談社刊)で谷崎潤一郎賞受賞。以来、『裏声で歌へ君が代』(新潮社刊)、『女ざかり』(1993年・講談社刊)、『輝く日の宮』(2003年・講談社刊)、そして最後の書き下ろし長編となったのが『持ち重りする薔薇の花』(2011年・新潮社刊)だ。


丸谷才一の長篇小説は『笹まくら』以降は、全て我が書棚に並んでいる。その丸谷才一の著作の中で自分自身の「浅学非才」さを痛感させられたのが、『裏声で歌へ君が代』だ。「西欧の文学と日本の古典文学への膨大な博識を後ろ盾にした知的なユーモア」に、全くついて行けなかった。「知識のなさ」を思い知らされ、途中でキブアップした。
その次の『女ざかり』は楽しく読み、丸谷才一の作品には珍しく、吉永小百合の主演で映画にもなった。我が手元には、その映画のスチール写真もある。
人全てみな、いつかは鬼籍に入るが、丸谷才一の死はそれにしても惜しい。「一連の著作は、日本近代文学での主流だった、とかく深刻で陰鬱なムードを漂わせる私小説的な伝統との闘いの歴史そのもの」との評もある、丸谷才一のようなスケールの大きな小説を書く作家は、もう現れないのではと思ったりもする。合掌。

















