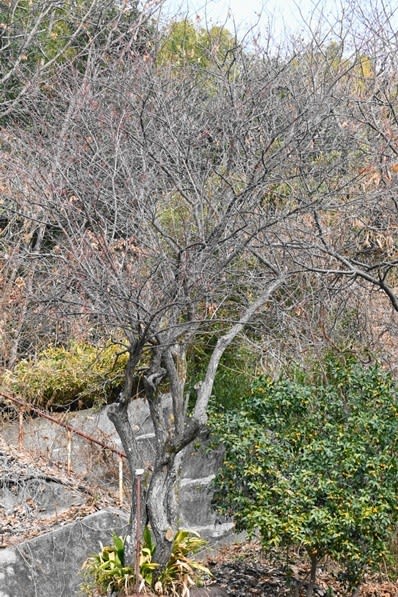一昨日は山、昨日は川原の周辺を歩いてきました。
太田川にかかる安佐大橋の周辺です。
太田川にかかる安佐大橋の周辺です。
川原に下りてみると・・・
昨日11:00過ぎ頃写したものです。河川敷を歩いていると・・・

中に入れそうだったので川原に下りて、草の部分の向こうへ行ってみました。
石ころが見事に集まった川原になっていました。

上流方向です。左向こうの山は9年前(2014年)の8月、大土砂災害を起こした阿武山です。

下流方向です。安佐大橋(市道)と山陽道の太田川橋が見えました。

ズームアップしてみました。手前が安佐大橋です。

山陽道は広島インターの1㎞手前でした。


中に入れそうだったので川原に下りて、草の部分の向こうへ行ってみました。
石ころが見事に集まった川原になっていました。

上流方向です。左向こうの山は9年前(2014年)の8月、大土砂災害を起こした阿武山です。

下流方向です。安佐大橋(市道)と山陽道の太田川橋が見えました。

ズームアップしてみました。手前が安佐大橋です。

山陽道は広島インターの1㎞手前でした。

石の川原を歩いてみると、縞々模様や面白い模様の石が目につきました。


目についたものを少し集めてみると・・・



目についたものを少し集めてみると・・・

縞々模様の石がたくさんあることに気づきました。
何でこんなに縞々模様の石が!? 不思議でした。
帰ってネットで調べてみると、「岩石の縞模様について」次のような記述がありました。
何でこんなに縞々模様の石が!? 不思議でした。
帰ってネットで調べてみると、「岩石の縞模様について」次のような記述がありました。
河原の岩石の表面には縞模様が見られることがある
でき方は主に以下の4通り
○堆積物が堆積してできた縞模様(層理)
○地下深部で岩石が圧力を受けてできた縞模様(片状組織)
○マグマが流れつつ冷えて固まってできた縞模様(流理組織)
でき方は主に以下の4通り
○堆積物が堆積してできた縞模様(層理)
○地下深部で岩石が圧力を受けてできた縞模様(片状組織)
○マグマが流れつつ冷えて固まってできた縞模様(流理組織)
○岩石の割れ目に熱水やガスが入り込み鉱物が沈殿してできた縞模様(鉱脈)
どれに当たる石だったのか? 複数あったのか? よくは分かりませんでしたが・・・
どれに当たる石だったのか? 複数あったのか? よくは分かりませんでしたが・・・
川原にゴロゴロ、不思議でした。