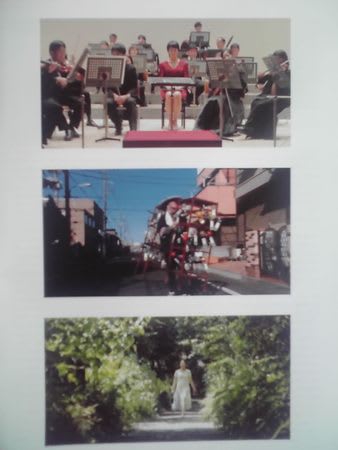21日(火)。わが家に来てから24日目を迎えたモコタロです 

かぼちゃのおばけにのっかっちゃたよ、あとがおとろしぃ

 閑話休題
閑話休題 

所沢高校のクラス会の通知が届きました 前回開いたのは3年前、東日本大震災のあった年の5月でした。このブログを始めたのはその年の2月です
前回開いたのは3年前、東日本大震災のあった年の5月でした。このブログを始めたのはその年の2月です 通知には11月29日(土)午後3時から埼玉県所沢市内の中華料理店となっています。実はこの日、午後2時から、かつしかシンフォニーヒルズで韓国のヴァイオリニスト、シン・ヒョンスのヴァイオリン・リサイタルを聴く予定が入っているのです
通知には11月29日(土)午後3時から埼玉県所沢市内の中華料理店となっています。実はこの日、午後2時から、かつしかシンフォニーヒルズで韓国のヴァイオリニスト、シン・ヒョンスのヴァイオリン・リサイタルを聴く予定が入っているのです クラス会は約2時間として5時頃終了するでしょう。一方リサイタルの方も約2時間として4時頃終了するでしょう。青砥から所沢まで1時間くらいはかかるでしょうから、クラス会が終わる頃に会場に着く計算です
クラス会は約2時間として5時頃終了するでしょう。一方リサイタルの方も約2時間として4時頃終了するでしょう。青砥から所沢まで1時間くらいはかかるでしょうから、クラス会が終わる頃に会場に着く計算です
リサイタルを聴いてからクラス会に滑り込むか、2次会から参加するか、あるいは、事故にでも遭ったと思ってコンサートを諦めて最初からクラス会に出席するか・・・・内山田洋とクールファイブの心境です。思案橋ブルース、古ッ よーく考えて結論を出そうと思います
よーく考えて結論を出そうと思います

 も一度、閑話休題
も一度、閑話休題 

「METライブビューイング2014-15」のチケットが発売されています これは米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ映像を世界的に配信・上映する企画で、日本では現地での上演日の約1か月後に公開されます
これは米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ映像を世界的に配信・上映する企画で、日本では現地での上演日の約1か月後に公開されます

今シーズンは11月1日から来年5月29日までの7か月間に全10作品が上映されます ラインアップは次の通りです(上映はすべて土曜日に始まり翌週金曜日に終わります)
ラインアップは次の通りです(上映はすべて土曜日に始まり翌週金曜日に終わります)
①ヴェルディ「マクベス」 11月1日~11月7日
②モーツアルト「フィガロの結婚」(新演出) 11月15日~11月21日
③ビゼー「カルメン」 12月13日~12月19日
④ロッシーニ「セヴィリアの理髪師」 1月24日~1月30日
⑤ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 2月7日~2月13日
⑥レハール「メリー・ウィドウ」(新演出) 2月21日~2月27日

⑦オッフェンバック「ホフマン物語」 3月7日~3月13日
⑧チャイコフスキー「イオランタ」(MET初演)、バルトーク「青ひげ公の城」(新演出) 3月28日~4月3日
⑨ロッシーニ「湖上の美人」(MET初演) 4月11日~4月17日
⑩マスカー二「カヴァレリア・ルスティカーナ」(新演出)、レオンカヴァッロ「道化師」(新演出)
5月23日~5月29日

今回の10作品の中で私が期待しているのは、『楽しいオペラ』として「フィガロの結婚(新演出)」、「セヴィリアの理髪師」の2作品。『歌手で選ぶオペラ』として、アンナ・ネトレプコの歌う「マクベス」「イオランタ」(MET初演)、”METのディーヴァ”ルネ・フレミングの歌う「メリー・ウィドウ」(新演出)、ジョイス・ディドナートの歌う「湖上の美人」(MET初演)といったところです。もちろん全作品を観るつもりです
東京都心の上映会場は新宿ピカデリー、東銀座の「東劇」、TOHOシネマズ六本木ヒルズです
チケット代は1作品につき一般3,600円、学生2,500円ですが、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」だけは一般5,100円、学生3,600円となっています なお、特別鑑賞券(3枚綴り:9,300円)が販売されています。1枚当たり3,100円の計算で、3作以上観る場合は絶対にお得です
なお、特別鑑賞券(3枚綴り:9,300円)が販売されています。1枚当たり3,100円の計算で、3作以上観る場合は絶対にお得です ただし「マイスタージンガ-」には使えません。チケットは上映劇場のほか、ローソンチケット、イープラス、セブンチケット、チケットぴあでも販売されています
ただし「マイスタージンガ-」には使えません。チケットは上映劇場のほか、ローソンチケット、イープラス、セブンチケット、チケットぴあでも販売されています
映画とはいえ、超一流の歌手陣によるオペラを観るチャンスです。METライブビューイングでオペラデビューはいかがですか














 新宿の「ビックロ」で試着してブルーとブラックの2着を買いました
新宿の「ビックロ」で試着してブルーとブラックの2着を買いました
 1週間前に第3回『傑作の森』を聴いたばかりです。今回のプログラムは①ピアノ・ソナタ第30番ホ長調、②ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調、③ピアノ・ソナタ第31番変イ長調、④チェロ・ソナタ第4番ハ長調、⑤ピアノ・ソナタ第32番ハ短調です
1週間前に第3回『傑作の森』を聴いたばかりです。今回のプログラムは①ピアノ・ソナタ第30番ホ長調、②ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調、③ピアノ・ソナタ第31番変イ長調、④チェロ・ソナタ第4番ハ長調、⑤ピアノ・ソナタ第32番ハ短調です

 それでも1階16列24番、センターブロック右通路側席を押さえました。会場は8割方埋まっている感じです
それでも1階16列24番、センターブロック右通路側席を押さえました。会場は8割方埋まっている感じです ベートーヴェンの後期ピアノ・ソナタは普段聴く機会がないので曲がすんなりと頭に入ってきません。予習不足を認めざるを得ません
ベートーヴェンの後期ピアノ・ソナタは普段聴く機会がないので曲がすんなりと頭に入ってきません。予習不足を認めざるを得ません
 演奏者によってずい分印象が違うものだと思いました
演奏者によってずい分印象が違うものだと思いました

 演奏はチェロ=藝大教授・河野文昭、ピアノ=藝大非常勤講師・大田佳弘です。何度か河野文昭のチェロを聴きましたが、朗々と響かせる美しい音色が素晴らしいと思います
演奏はチェロ=藝大教授・河野文昭、ピアノ=藝大非常勤講師・大田佳弘です。何度か河野文昭のチェロを聴きましたが、朗々と響かせる美しい音色が素晴らしいと思います
 30番、31番と違って、32番は私にとって比較的なじみのある曲です
30番、31番と違って、32番は私にとって比較的なじみのある曲です 第1楽章冒頭の強烈な和音から入りますが、これがベートーヴェンだ
第1楽章冒頭の強烈な和音から入りますが、これがベートーヴェンだ という力強い曲です。次から次へと様々なメロディーが現われ、他の作曲家にない独特の世界を形作っていきます。何と美しく、何と力強いのか
という力強い曲です。次から次へと様々なメロディーが現われ、他の作曲家にない独特の世界を形作っていきます。何と美しく、何と力強いのか
 ベートーヴェンの素晴らしいところは、改良が加えられていくピアノの性能に応じて、ピアノの表現領域を広げていったところです
ベートーヴェンの素晴らしいところは、改良が加えられていくピアノの性能に応じて、ピアノの表現領域を広げていったところです

 オケは通常の東響の態勢です。左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという配置です。コンマス・水谷晃の合図でチューニングが行われ、指揮者を待ちます
オケは通常の東響の態勢です。左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという配置です。コンマス・水谷晃の合図でチューニングが行われ、指揮者を待ちます まだ曲が始まったばかりなのに、あなた寝てましたね
まだ曲が始まったばかりなのに、あなた寝てましたね その後、ヴァイオリンの名手ヨアヒムのアドヴァイスを受け改訂を重ね1883年に楽譜を出版しています
その後、ヴァイオリンの名手ヨアヒムのアドヴァイスを受け改訂を重ね1883年に楽譜を出版しています すぐそばで聴いていた弦楽セクションの演奏者たちも、曲が終わるや否や、ため息をつきながら拍手を送っていました。プロも認める実力者ですね
すぐそばで聴いていた弦楽セクションの演奏者たちも、曲が終わるや否や、ため息をつきながら拍手を送っていました。プロも認める実力者ですね










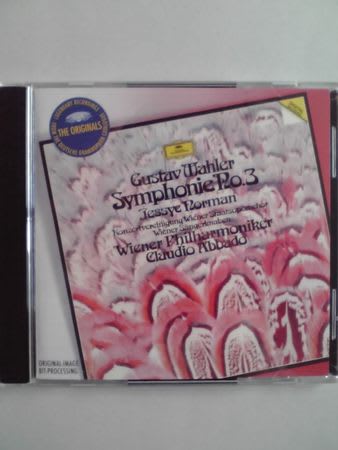


 従者のレポレッロと逃走する途中で、かつての妻で捨てた女ドンナ・エルヴィーラに追い回されながら、結婚直前の村娘ツェルリーナを誘惑したりして放蕩の限りを尽くす
従者のレポレッロと逃走する途中で、かつての妻で捨てた女ドンナ・エルヴィーラに追い回されながら、結婚直前の村娘ツェルリーナを誘惑したりして放蕩の限りを尽くす やがて一連の悪行がばれて、騎士長が眠る墓場に逃げてくるが、そこで騎士長の石像を晩餐に招く約束をする
やがて一連の悪行がばれて、騎士長が眠る墓場に逃げてくるが、そこで騎士長の石像を晩餐に招く約束をする 石像は招かれた館でドン・ジョバンニに放蕩生活を反省し心を入れ替えるよう説得するが、彼はそれを拒み、地獄に落とされる
石像は招かれた館でドン・ジョバンニに放蕩生活を反省し心を入れ替えるよう説得するが、彼はそれを拒み、地獄に落とされる
 躍動感溢れる二重唱、三重唱の魅力に満ち溢れています
躍動感溢れる二重唱、三重唱の魅力に満ち溢れています
 今回もきびきびした演技とともに深みのあるバスを聴かせてくれました
今回もきびきびした演技とともに深みのあるバスを聴かせてくれました



 プロフィール欄の写真をトラ
プロフィール欄の写真をトラ  連城三紀彦は1948年、名古屋市生まれ。早稲田大学政経学部を卒業。81年に「戻り川心中」で第34回日本推理作家協会賞を、84年に「宵待草夜情」で第5回吉川英治文学新人賞を、「恋文」で第91回直木賞を受賞しました
連城三紀彦は1948年、名古屋市生まれ。早稲田大学政経学部を卒業。81年に「戻り川心中」で第34回日本推理作家協会賞を、84年に「宵待草夜情」で第5回吉川英治文学新人賞を、「恋文」で第91回直木賞を受賞しました 2013年10月に逝去しています
2013年10月に逝去しています







 モコタロがわが家に来てから17日目を迎えました
モコタロがわが家に来てから17日目を迎えました 

 ケーキは巣鴨駅に入っている高野のフルーツケーキです。紅茶は賞味期限さえ気にしなければ味は最高でした
ケーキは巣鴨駅に入っている高野のフルーツケーキです。紅茶は賞味期限さえ気にしなければ味は最高でした

 )、ピアノから出てくる音は侮れません。実にメリハリのある素晴らしい演奏を展開します
)、ピアノから出てくる音は侮れません。実にメリハリのある素晴らしい演奏を展開します
 とブラボーの後、この日の出演者全員が再度登場し別れを告げます。私はこの日と翌週日曜の連続券を買っているので1回あたり2,500円と格安です。来週がまた楽しみです
とブラボーの後、この日の出演者全員が再度登場し別れを告げます。私はこの日と翌週日曜の連続券を買っているので1回あたり2,500円と格安です。来週がまた楽しみです