 北京大学版 中国の文明 第1巻 古代文明の誕生と展開<上>の感想
北京大学版 中国の文明 第1巻 古代文明の誕生と展開<上>の感想今巻は新石器時代から殷周時代、春秋・戦国時代までの文明の発展と青銅器文化の概説が中心。考古学による発掘の成果や、甲骨文・金文といった出土文献の内容を、伝世文献の記述を証明するための手段として用いる、王国維以来の二重証拠法をフル活用しており、良くも悪くも中国古史学の総まとめ的な仕上がりになっている。
読了日:8月3日 著者:
 残夢の骸 満州国演義九 (新潮文庫)の感想
残夢の骸 満州国演義九 (新潮文庫)の感想全9巻の大作もいよいよ完結。終盤3巻は舞台が東南アジアに広がり、満州国演義というより大日本帝国演義のような感じになっていたが… 今巻の読みどころは、特攻隊に関して『永遠の0』の舞台裏というか「理想と現実」が描かれている部分。あの作品に関して著書も色々思う所があったのだろう。
読了日:8月7日 著者:船戸与一
 ハーバードの人生が変わる東洋哲学──悩めるエリートを熱狂させた超人気講義 (ハヤカワ・ノンフィクション)の感想
ハーバードの人生が変わる東洋哲学──悩めるエリートを熱狂させた超人気講義 (ハヤカワ・ノンフィクション)の感想しょっぱなから「トロッコのジレンマ」の問い自体を否定したりして、同じハーバードのマイケル・サンデルに一発噛ませているが、サンデルの講義の方がまだ哲学らしいことをしている。良くも悪くもアメリカナイズされた先秦思想の概説。古典文献はやはり書かれた時代の文脈に合わせて読むべきものだと認識させられた。人文系の学問が過度に「役に立つ」ことを求められた結果がこれなのかなと思った次第。
読了日:8月8日 著者:マイケル・ピュエット,クリスティーン・グロス=ロー
 中世倭人伝 (岩波新書)の感想
中世倭人伝 (岩波新書)の感想再版を機に再読。『朝鮮王朝実録』を主要な史料として、環シナ海域の「倭人」や「倭寇」たちを、日本にも朝鮮にも中国にも帰属せず(あるいはそのすべてに帰属しうる)、その境界に生きる「マージナル・マン」と位置づける。当時「中世」が陸の外にも飛び出していたことと、特に後期倭寇が俗説によく言われるような、「中国人が日本人を偽装した」などという単純な存在ではないことがわかる。
読了日:8月10日 著者:村井章介
 「怪異」の政治社会学 室町人の思考をさぐる (講談社選書メチエ)の感想
「怪異」の政治社会学 室町人の思考をさぐる (講談社選書メチエ)の感想室町的な怪異のありようと、その衰退に至るまで。桜井英治の『贈与の歴史学』を読んだ時も思ったが、副題にもある「室町人の思考」というのは現在の我々とはどこかで断ち切れてしまった異世界の住人の思考だなと。本書の第六章と「むすびに」ではなぜ「異世界の住人の思考」のようになっていったのかを簡単にまとめているが、ここを膨らませていくことが今後の課題ではないかと思った次第。
読了日:8月13日 著者:高谷知佳
 英語と日本軍―知られざる外国語教育史 (NHKブックス No.1238)の感想
英語と日本軍―知られざる外国語教育史 (NHKブックス No.1238)の感想士官学校など、戦前の軍関係の学校での英語教育について追っていく。戦前の士官学校などでの外国語教育のメソッドが戦後の英語教育にも強い影響を与える一方で、文法・長文読解重視か会話重視かという議論や、特定の言語の教育のみを重視する(陸軍ならロシア語・ドイツ語、海軍なら英語、戦後は英語一辺倒と言った具合に)といった問題点もそのまま引き継いでいるのが興味深い。
読了日:8月16日 著者:江利川春雄
 日本陸軍と中国: 「支那通」にみる夢と蹉跌 (ちくま学芸文庫 ト 16-1)の感想
日本陸軍と中国: 「支那通」にみる夢と蹉跌 (ちくま学芸文庫 ト 16-1)の感想佐々木到一ら支那通軍人の活動を通して戦前の日中関係の推移を追う。彼らは三国志のシミュレーションゲームのような感覚で謀略にのめり込んだ。彼らの口にする「中国は近代国家ではない」とか「中国は法治国ではない」なんて理屈は今でもよく言われるものであり、国民政府や蔣介石の力の軽視や憎しみは、そのまま現在の中国共産党政権に対する見方にスライドできるだろう。江藤淳は著者に、彼らには中国が他者であるという認識が欠けていたと言ったとのことだが、それより寧ろ中国の近代化を日本が指導すべきという思い上がりが問題ではないか。
読了日:8月19日 著者:戸部良一
 中国の論理 - 歴史から解き明かす (中公新書 2392)の感想
中国の論理 - 歴史から解き明かす (中公新書 2392)の感想古代から近現代まで中国の歴史を辿りながら、「士」と「庶」の乖離、「華」と「夷」の別、古典古代への附会という形でしか進められなかった近代化など、「中国の論理」を解説する。伝統的に「正史」の記述も含めて史学は経学から独立自立した学になりきっていないという点など、「正史」を過大に評価しがちな俗流中国論を覆すような内容も含まれているが、著者のこれまでの一般書『中国「反日」の源流』や『近代中国史』に比べて食い足りない印象を受けたのは残念。
読了日:8月20日 著者:岡本隆司
 天下と天朝の中国史 (岩波新書)の感想
天下と天朝の中国史 (岩波新書)の感想「華夷秩序」から見る中国通史。「拓跋国家」「東部ユーラシア」「澶淵体制」、漢文史料以外の言語による史料から見る「イェケ・モンゴル・ウルス」など、近年の研究の成果も自在に取り込みながら、現代の中国の世界観・外交観がどのようにして形成されていったのかを追う。中国史学の成果を知るうえでも、現代の中国及び日本などの東アジア諸国のポジションを考えるでも、多くの人に読まれて欲しい概説書。
読了日:8月24日 著者:檀上寛
 戦国の陣形 (講談社現代新書)の感想
戦国の陣形 (講談社現代新書)の感想本題は当然戦国時代の陣形の実像ということになるわけだが、それ以前の古代から中世前期の話を面白く読んだ。日本で中近世の陣形や戦術の研究が途絶えたのは、敗戦の影響というよりは、もともと分野として内容が空疎だったからではないか、今風に言えば「役に立たない」と見なされていたからではないかと思う。
読了日:8月25日 著者:乃至政彦
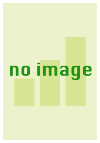 白川文字学の原点に還る 「甲骨金文学論叢」を読むの感想
白川文字学の原点に還る 「甲骨金文学論叢」を読むの感想白川静の学術書のうち、『甲骨金文学論叢』所収の主要な論考の導読。『字統』などの字書や一般書に記述されている結論だけを取り出して称揚・批判がなされがちな「白川文字学」だが、どういう手続きや論証によって漢字の字源が導き出されたのかをわかりやすく解説しており、「白川文字学」批判派にとっても意義のある書籍だと思う。
読了日:8月28日 著者:高島敏夫
 「今」こそ見るべき海外ドラマ (星海社新書)の感想
「今」こそ見るべき海外ドラマ (星海社新書)の感想新旧のアメドラ作品の紹介のほか、業界事情やhuluなどの動画配信サービス登場のインパクトについても述べられており、アメドラは片手で数えるほどしか見ていない私でも楽しめた。私がよく見る中国ドラマの制作方式(テレビ局がドラマを制作するのではなく、制作会社が放映権をテレビ局に売るという形式をとる点など)がアメリカの方式を模していることが窺えたりと、韓国など欧米以外の地域のドラマファンにも参考になる点が多々あるだろう。
読了日:8月29日 著者:池田敏


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます