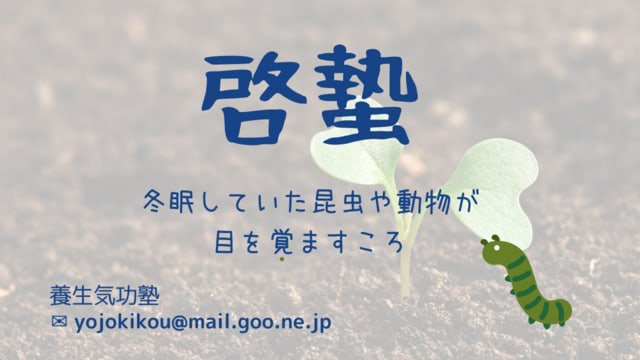3月6日は二十四節気「啓蟄」です!
「啓蟄」は・・・
「冬籠りの虫が這い出る」(広辞苑)
という意を示すそうです。
虫や動物たちが活発になるころ
なのでしょうね。
順番にいろいろなものが目覚め
動き出し活発になっていきます。
人民中国さまより
毎年、太陽暦の3月5日前後が24節気の啓蟄である。「蟄」は「隠れる」の意味があり、動物が土にもぐって冬眠することを「入蟄」という。彼らは翌春、地上へはい出して活動する。古人はそれが春雷に驚いて目を覚ましたと考えて「驚蟄」とも呼んだ。この時期中国の大部分の地区で、すでに春耕が始まっている。華中地域の農家のことわざに「啓蟄過ぎれば、春耕を止めず」というのがある。
啓蟄の時期の民俗
啓蟄になると、民間ではナシを食べたり、「掃虫」「炒虫」といった虫除けの行事や、白虎を祭ったりするなどの習俗がある。中国語の「梨」は別れの意味を持つ「離」と同音のため、多くの祝日にはナシを忌み避けるが、啓蟄に梨を食べる。害虫を遠くに追いやり、変わりやすい気候の春だけに病気を身から遠く離したいと願うからである。
浙江省の寧波では、農家はこの日、竹ぼうきを持って田畑に行き虫を掃く儀式を行う。ほかにも、各地で「虫を炒める」という習わしがある。除虫を忘れないように、虫の代わりにゴマやダイズなどを炒めて「虫炒め」「虫除け」の意味をあらわす。広東では、農民は啓蟄に百毒を駆除する獣王の白虎を祭って、雷に驚いて目を覚ました蛇や虫やネズミやアリに農作物が害を受けないように祈る。
啓蟄の養生
啓蟄の時期の養生は、自然の気候風物や自身の体質に合わせて調整する。啓蟄を過ぎると、だんだん暖かくなるが、気温は一定せず、とくに朝晩の温度差が大きいため風邪を引きやすい。お年寄りはあまり薄着をしないよう心がける。この時期は、酸っぱい食品を少なめに、甘い食品を多く摂る。野菜は、甘味のあるニンジン、カリフラワー、ハクサイ、ピーマンなどをよく食べる。タマネギ、セロリ、ニラなども多く食べた方がよい。
以前のブログはこちらから
<啓蟄>
啓蟄・・・えっ!?呪いの日??
二十四節気「啓蟄」