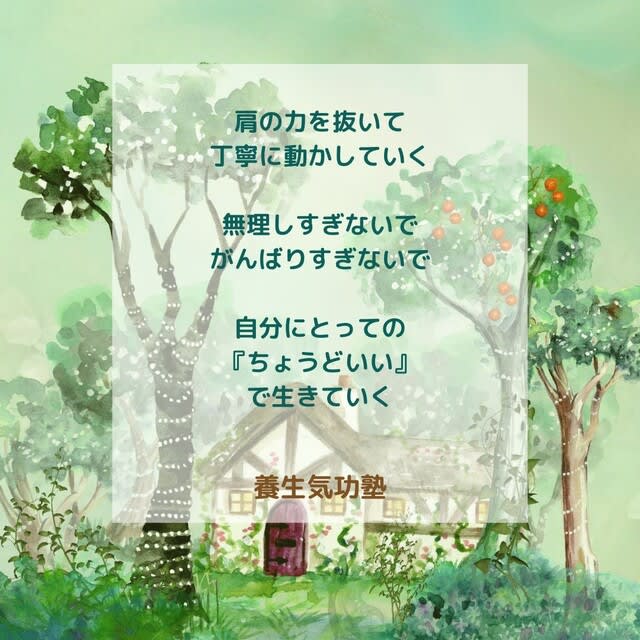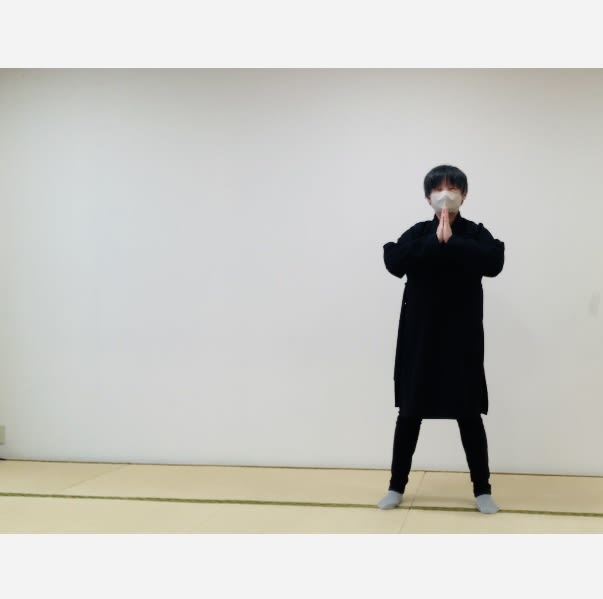以前もご紹介したものですが再度。
気功では
「バランス」を大事にしています。
そのヒントになれば。
ーー
(津村喬さんの記事より)
陶弘景(456-536)は養性延命録などの本をたくさん書いた気功家である。
大きいことはいいことではないと主張し続けた。
これは老子を継承するものである。
人生のコツは少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少楽、少喜、少怒、少好、少悪だという。
少なく思うとは、あれこれ悩んだり妄想したりしてもほとんど何の訳にも立たないのだから、思いは少なくした方がいいということだ。「思いすぎると神(私の中の最も高級な精神活動)が危うくなる」と言っている。
少念も同じことだ。「念が多すぎると志が散じてしまい、自分が何をしたいのかを忘れてしまう」。
少欲は欲望を膨らませない方がいいということだが、もっと勉強したいとかもっと向上しようと言う「良い欲望」も自分を損なうことが問題だ。「多欲は志を損なう」先ず自分の存在を肯定してはじめて「志」を活かせるようになる。
少事はあまりいろんなことをするなということだ。「多事即形疲」からだが疲れてしまうだけでなく、上にあるように志も拡散してしまう。
少語はおしゃべりをやめること。どうでもいいことをしゃべって時間をつぶさないこと。「多語則気争」とはおしゃべりだとしなくてもいい論議をして消耗すること。
少笑は「いつも楽しく微笑みを」というのには背くが、内面から笑うのでなく他人のために笑いすぎると「内臓を損なう」と断言している。
少愁は哀しみすぎない。悲しい時には泣けばいいが、こだわって悲しむと、心を害することになる。
少楽と言われると楽しんで生きて何がいけないのかと反論したくなるだろうが、「意が溢れる」といういいかたをしている。自分が見えなくなるのだ。
少喜は「忘錯昏」という。喜びすぎると気が上がって、自分がなくなると言っている。
少怒と怒りすぎると「百脈不定」だという。「内臓を損なう」と同様身体的効果を強調している。怒るのは肝臓が怒っていて、喜んでいるのは心臓が喜び、憂えるのは肺が憂えているので、それが過ぎると内臓に問題が出やすいのだ。
少好は「多好は専迷不治」と説明している。好きなことが多いと道に迷う。
少悪は悪いことばかり考えているといらいらして心が落ちつかず、喜びがない。
無思とか無欲とかいわずに、少思、少欲といっていることに注意して欲しい。思、念、欲、笑、怒などは心の自然で、自然でいればどんどんエスカレートして行くことはない。エスカレートさせてしまうのは何かのコンプレックスが作用している。
自分の心とつきあうには、何がいい,悪いと決めないで、ただある偏りが膨らみすぎないようにするだけでいい。
これはキリスト教やイスラム教との大きな違いだ。世界を救うには気功がいいと思うのだが、押し付ける訳にも行かない。