住職でもある作者は、
これは布教活動のひとつでもある、とおっしゃっていましたが。
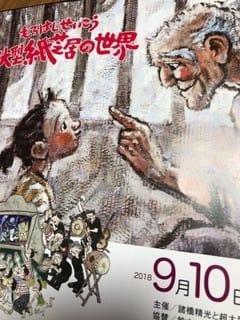
一昨日、「もろはしせいこう 超大型紙芝居の世界」という公演を
池袋の あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)
という所で 見てきました。
東池袋駅から、もう、ほんと、すぐ! です。
超大型紙芝居、というのは、もちろん、紙芝居です(笑)。
超大型というのは、どのくらいの大きさかというと、
130cm × 90cm です。
P60の キャンバスのサイズだそうです。
このサイズの 段ボールに描いた絵を、
語りに合わせて 動かし、引き抜きます。
ステージも客席も暗く、
絵にスポットライトが当たっているので、
心は 別世界に飛んで行ってしまいます(笑)。
なにしろ、朗読(「語り」とよんでいます)がスゴイ!
引き込まれてしまいます。
面白いのは、効果音!
ギターもありますが、
お寺の楽器、総動員! という感じ。
そういえば、吉祥寺の住職も、
「お寺には 楽器がいっぱいある」
といつも言ってます。
この公演では 法螺貝を吹き鳴らし、
銅鑼や太鼓を 叩き、
チ~~~~ン。。。
なんてのもありました。
今回は
「茂吉のねこ」「月夜とめがね」「くもの糸」「注文の多い料理店」「モチモチの木」
の五作品が上演されました。
私は 松谷みよ子原作の『茂吉のねこ』は 知りませんでした。
読んだ事はあって、忘れたのかもしれません。
『月夜とめがね』は 小川未明、
『モチモチの木』は 斎藤隆介。
あとは、皆さんもご存知でしょうか?

ロビーには 『茂吉のねこ』に出てくる妖怪のオブジェも。
いただいたパンフレットによると、
絵本は世界中にありますが、
紙芝居は 日本にしかない 独自の表現形式なんだそうです。
想像以上にその世界は深淵です!

絵本は ドアを開くようにめくる。
紙芝居は ふすまを引くように場面展開する。

ふすまの向こうに 見知らぬ世界が隠れていて、
開けるたびに 次の部屋が現れる。
時には途中で止めて隠す。
そういえば、紙芝居を引き抜くときには
途中で止める他に、
「ゆっくりと引く」「さっと引く」
という技法(?)が ありますね。

ギャラリートークでの諸橋精光師。
ロビーでは、すずき出版が 諸橋師の紙芝居(ふもちろん、フツーの)や
絵本や カレンダーを販売していました。
心が素直な童に還って、気持ちよく帰宅できました。
これは布教活動のひとつでもある、とおっしゃっていましたが。
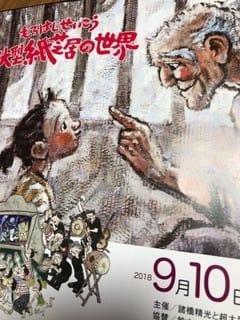
一昨日、「もろはしせいこう 超大型紙芝居の世界」という公演を
池袋の あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)
という所で 見てきました。
東池袋駅から、もう、ほんと、すぐ! です。
超大型紙芝居、というのは、もちろん、紙芝居です(笑)。
超大型というのは、どのくらいの大きさかというと、
130cm × 90cm です。
P60の キャンバスのサイズだそうです。
このサイズの 段ボールに描いた絵を、
語りに合わせて 動かし、引き抜きます。
ステージも客席も暗く、
絵にスポットライトが当たっているので、
心は 別世界に飛んで行ってしまいます(笑)。
なにしろ、朗読(「語り」とよんでいます)がスゴイ!
引き込まれてしまいます。
面白いのは、効果音!
ギターもありますが、
お寺の楽器、総動員! という感じ。
そういえば、吉祥寺の住職も、
「お寺には 楽器がいっぱいある」
といつも言ってます。
この公演では 法螺貝を吹き鳴らし、
銅鑼や太鼓を 叩き、
チ~~~~ン。。。
なんてのもありました。
今回は
「茂吉のねこ」「月夜とめがね」「くもの糸」「注文の多い料理店」「モチモチの木」
の五作品が上演されました。
私は 松谷みよ子原作の『茂吉のねこ』は 知りませんでした。
読んだ事はあって、忘れたのかもしれません。
『月夜とめがね』は 小川未明、
『モチモチの木』は 斎藤隆介。
あとは、皆さんもご存知でしょうか?

ロビーには 『茂吉のねこ』に出てくる妖怪のオブジェも。
いただいたパンフレットによると、
絵本は世界中にありますが、
紙芝居は 日本にしかない 独自の表現形式なんだそうです。
想像以上にその世界は深淵です!

絵本は ドアを開くようにめくる。
紙芝居は ふすまを引くように場面展開する。

ふすまの向こうに 見知らぬ世界が隠れていて、
開けるたびに 次の部屋が現れる。
時には途中で止めて隠す。
そういえば、紙芝居を引き抜くときには
途中で止める他に、
「ゆっくりと引く」「さっと引く」
という技法(?)が ありますね。

ギャラリートークでの諸橋精光師。
ロビーでは、すずき出版が 諸橋師の紙芝居(ふもちろん、フツーの)や
絵本や カレンダーを販売していました。
心が素直な童に還って、気持ちよく帰宅できました。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます