5月だというのに、すっかり真夏の陽気を感じさせる令和元年の皐月。
夏の小学校では朝顔とともに育てる定番だったのが『へちま』

朝顔が小学生の低学年ならば、へちまはどちらかといえば高学年で育てていました。
私の通った小学校では木造校舎の縁側に当たる箇所に栽培するスペースがあり、そこでへちまを育てていたものです。

もしかしたら、私の通った学校では、たまたまへちまを育ててる菜園が近い教室が高学年の教室だからってことかもしれませんが・・・(笑)。
それはさておき、この『へちま』

栽培するのはいいのですが、利用方法といっても「へちまタワシ」やら「へちま水」くらい。
とくに食べたとかって記憶もありません。
なんで育ててるんだろう??と小学生当時から疑問に感じておりました。
そう思って、いつもながらお世話になっている「ウィキペディア」先生にて検索してみると・・・。
台湾や沖縄、南九州では料理にも利用されているようです。いわゆる『ゴーヤー』とはまた違う品種で、苦味が強いのを我慢して食べると食中毒症状になるとか(ウィキペディア参照)。
へぇぇ、やはり料理に利用する場合もあるようです。
で、ウィキペディアによると、学習教材に使用される理由が次のとおり。
「学習教材1年で発芽、開花、受粉、結果、枯死し、雄花と雌花によって他家受粉することから、日本では小学校の理科教材として使用される。」
ウィキペディア参照。
年間を通して植物の生長を観察できることから、教材に持って来いなのでしょうね。
プロの料理人のマンツーマンレッスン!【RIZAP COOK】



長年の疑問がようやく解けました。
なんとなく小学生の頃に育てていた『へちま』。ちなみに日本には室町時代頃に中国から渡来してきたそうです(ウィキペディア参照)。
調べてみると、意外な真実に辿りつけました。
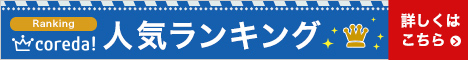

SAPIX・日能研・四谷大塚の中学受験専門プロ講師が運営。
ご相談後、お子様に合ったプロ家庭教師を派遣。

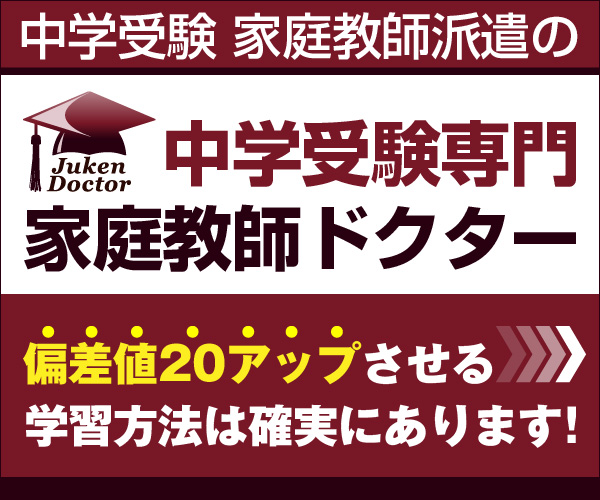

夏の小学校では朝顔とともに育てる定番だったのが『へちま』

朝顔が小学生の低学年ならば、へちまはどちらかといえば高学年で育てていました。
私の通った小学校では木造校舎の縁側に当たる箇所に栽培するスペースがあり、そこでへちまを育てていたものです。

もしかしたら、私の通った学校では、たまたまへちまを育ててる菜園が近い教室が高学年の教室だからってことかもしれませんが・・・(笑)。
それはさておき、この『へちま』

栽培するのはいいのですが、利用方法といっても「へちまタワシ」やら「へちま水」くらい。
とくに食べたとかって記憶もありません。
なんで育ててるんだろう??と小学生当時から疑問に感じておりました。
そう思って、いつもながらお世話になっている「ウィキペディア」先生にて検索してみると・・・。
台湾や沖縄、南九州では料理にも利用されているようです。いわゆる『ゴーヤー』とはまた違う品種で、苦味が強いのを我慢して食べると食中毒症状になるとか(ウィキペディア参照)。
へぇぇ、やはり料理に利用する場合もあるようです。
で、ウィキペディアによると、学習教材に使用される理由が次のとおり。
「学習教材1年で発芽、開花、受粉、結果、枯死し、雄花と雌花によって他家受粉することから、日本では小学校の理科教材として使用される。」
ウィキペディア参照。
年間を通して植物の生長を観察できることから、教材に持って来いなのでしょうね。
プロの料理人のマンツーマンレッスン!【RIZAP COOK】
長年の疑問がようやく解けました。
なんとなく小学生の頃に育てていた『へちま』。ちなみに日本には室町時代頃に中国から渡来してきたそうです(ウィキペディア参照)。
調べてみると、意外な真実に辿りつけました。
SAPIX・日能研・四谷大塚の中学受験専門プロ講師が運営。
ご相談後、お子様に合ったプロ家庭教師を派遣。




















