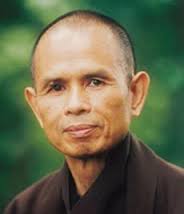
特定秘密法、絶対反対です! 民主主義と恣意的判断

もし、刑罰が恣意的に決められたら? 「あいつは憎たらしいから、盗みでも、懲役50年にしちゃえ」。そうなったら、そういう恣意的判断をするものが、≪絶大な悪の力≫...
ヴァン・デ・コーク教授のThe body keeps the score : brain, mind, body in the healing of trauma 『虐待されたら、意識できなくても、身体は覚えてますよ : 脳と心と身体がトラウマを治療する時どうなるか?』の第13章 Healing from trauma : Owing your self 「トラウマから癒されること :本当の自分を生きること」で、タッチ、触れられることを学んできましたでしょ。リシアさんの言葉からは、触れられることがいかに大事なやり取りと、やり取りがプレゼントしてくれる安心の元になるかを、教えられましたね。
今晩は、ティク・ナット・ハーンさんから、「もう1つのタッチ」をご一緒に学べたらと思います。
Peace is every step : A Practice for Our busy Lives, p.97
『平和は一歩一歩の歩み(にあります): 私どもの忙しい暮らしのためにしておきたいこと』p.97より
仏教で私どもが学ぶのは、もし私どもが、自分自身の痛みを理解することが出来れば、人の痛みも理解しやすくなる、ということです。ですから、まず初めにしなくちゃならないのは、自分自身の内側にある痛みに、触れてみる、タッチすることであって、内側にある痛みから、何とかして逃げ出そうとしたり、自分の気持ちに蓋をして、その痛みを忘れようとしたり、することではありませんからね。仏教では、最も根源的な教えが、4つの聖なる真理(訳注:四聖諦 ししょうたい)です。第1の真理は、≪いまここ≫にある痛みを理解することですし、第2の真理は、その痛みの本質をよくよく調べて、その根っこの原因をハッキリさせることです。
触れるといっても、内的な痛み、苦しみを、よくよく感じることが大事みたいですね。逃げ出したくなるのも人情かもしれませんが、逃げないで、自分の痛みに踏みとどまることが必要です。
ティク・ナット・ハーンさんの教えは、仏教に根差していますけれども、パウロや、シモーヌ・ヴェイユとも共通している不思議です。


もし、刑罰が恣意的に決められたら? 「あいつは憎たらしいから、盗みでも、懲役50年にしちゃえ」。そうなったら、そういう恣意的判断をするものが、≪絶大な悪の力≫...













 サリヴァン先生、セッスクする関係と、人を大事にする関係には違いがあることが分かったんですね。 p86の第3パラグラフ。 ...
サリヴァン先生、セッスクする関係と、人を大事にする関係には違いがあることが分かったんですね。 p86の第3パラグラフ。 ...
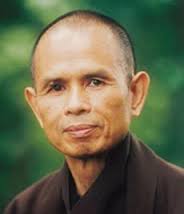


 観察単位は、個人ではなく、世代間関係で見るということは、臨床心理の基本中の基本です。家族心理学だけのものじゃぁない。愛着障害の子どもとその母親を相手にすること...
観察単位は、個人ではなく、世代間関係で見るということは、臨床心理の基本中の基本です。家族心理学だけのものじゃぁない。愛着障害の子どもとその母親を相手にすること...





