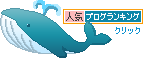「uzmetさーん!
毎年恒例なんですが、、、
伊勢の質問していいですかー??(´・ω・`)
外宮の横の道ってどこですか??
今年はそこ見てみたくて!」
......なんていうことで、
何かと質問を頂ける今日この頃。
なんだかとてもありがたいことでやんす。
そんな毎年恒例だという!?
伊勢大好き!なMaaさん(♀)からの質問ということで。
今回もこの時と同様に、彼女が行ってみたいと言っている伊勢、
外宮のマニアック・ポイントのお話を
ココにチロリと記しておこうかと思います。(^^)
今月末に行くということですので、
今日あたりのお返事というコトでよろしいでしょうかね。
ええ。ええ。
で、今回彼女が行ってみたいと言っている伊勢、
外宮の「横の道」というのは、
外宮の本殿の裏の方に伸びていく「トアル一本の道」のことで。
その道沿いには、実は外宮屈指の「圧倒的な」楠の大木が立ち並び、
二つばかりの摂社、末社がひっそりと佇んでもいます。
この道は神宮の「公式マップ」にも載っていなくて、
Maaさんのようによっぽど
「行こう!」
という明確な気持ちがない限り、
決して訪れるようなこともないであろう場所となります。
普通はマズ知らない場所のハズ、なのですが......
そんな外宮の公式境内マップがこちら......

まずわ、豊受大神宮というのが外宮の正式名称となります。
「トヨウケ」と読みます。
そして外宮。
「げぐう」と読んでいたりする人も多いようですが、
正式には「げくう」。
「くう」でございます。
神様は穢れ(けがれ)......「濁り」を嫌います。
「濁点」はできれば避けたい......という感じでしょうか。(^^)
「内宮」も正式には「ないくう」。
そういう感じ。
例の道は、上の地図では巫女さんの絵が描かれている、
御守りや御札の売場となっている中央の
「神楽殿=かぐらでん」から上の方に行った
「北御門鳥居=きたみかどとりい」と
「御厩=みうまや」の側に、
ヒッソリと細く小さな口を開けています。
北御門口の駐車場近くの鳥居から入った場合、
すぐ右手に見えてくる道。
「この小道には簡単には入らないようにね......」
と、
道の入口付近はそういう声が聞こえて来るかのような佇まい......

この道や、ここにある摂社や末社が
外宮の地図にちゃんと記載されていないのには、
キット「幾つかの理由」があるのだとは思いますが......
少なくとも、僕が歩いた感覚では、
このゾーンに関しては陰陽入り乱れる、
かなりカオスなエネルギーが満ちている様な場所で。
人によっては重々しく感じたり、キツく感じたり。
ハマりすぎて異様な力を感じてしまったり......と、
ナカナカ一般的とは言えないゾーンであることも
理由の一つになっているのではないかと思います。
他にも、現在の神宮ができる以前から伊勢の地を守り、
この地で神を祀ってきた氏族である
「度会氏(わたらいし)」
の祖霊を祀る社(やしろ)があるという事や、
あまりに強力なパワーを発する大木達に利己的で勝手な物やら何やら......
を置く様な人が後を絶たないという理由などで、
ココにはあまり人を入れたくないのかもしれません。
更には、この道の突き当たりには、
もしかしたら外宮で最も大切な場所の一つでは無いか?
とも思われる「上御井神社=かみのみいじんじゃ」がある
ということにも関係しているのかもしれません。
絶対に荒らせない神宮の水源
「上御井(かみのみい)」
伊勢神宮内に捧げられる全ての供物に使われる水は、
実は毎朝この井戸から汲まれ、運ばれているのです。
そして、地図にも載っていて、
誰でも訪れることのできる外宮境内の井戸が
「下御井神社=しものみいじんじゃ」
という名前のワケは、
この「上=かみ」があるからであって。
この道はそんな大切な井戸の真裏に出てしまう......
という、そんな道。
綺麗な水を保つため、
なるべく原生の植生をそのまま保ちたいという場所。
絶対に荒らされてはいけないエリア。
神宮を守る方々のそんな感覚も感じられます。
そしてこの道は、
その井戸の手前で錠前が厳重にかけられた扉と、
周囲を覆う金網の柵で行き止まりとなります。
金網の横にはこんな......
ちょっと絶句してしまうような大木さん達が
辺りの守護についています。
もう神様です。ええ。


こちらは、外宮と共に
「度会神道=わたらいしんとう」
の聖地とも言える「度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ)」。

上記もしましたが、
伊勢の地の宮は元々この外宮が最初であるのだと、
渡会氏は長年主張してきています。
現在の伊勢神宮が建立される以前より、
この地で神を祀り守り通して来た由緒ある氏族の大切な宮。
伊勢での参拝順序が
「内宮より外宮が先である」
とされているのはそういう訳でもあります。
もともとこの地にあった原初の神社が外宮なのです。
そこに、この地があまりに素晴らしかったため、
後に天皇家が内宮を建立したというわけです。
天皇家の祖神とされる「アマテラスオオミカミ=内宮」
を中心とする国家神道において、
あまり表立って語られることの無い歴史の真実でもあります。
この社(やしろ)には心して向かい合わねばいけません。
このゾーンではケータイとは言え、
まともにレンズを向けれないのであります.......
わたくし......
そんな地を通る道沿いにある異様な力を感じる大木さん達は......
やっぱり神様です。ええ。



できればそのままそっとしておいて欲しいとも思われ......
写真は人によってはあまりジーーッと見ないほうが良いとも思われ......
根元に何か置いたり、捧げたりするとかはやめたほうが賢明とも......
思われます。ええ。
エグいっす。
此方はこの道沿いにあるもう一つのスゲー社(やしろ)。
「大津神社=おおつじんじゃ」

内宮の中を流れる五十鈴川の河口にある、
港町の守護神でもある
「葦原神=あしはらのかみ」
を祭っています。
津とは海。
この辺りも古代、海に囲まれた葦の原だったことを思わせる
大切な社だと僕は思います。
そしてこの裏参道からは、
深い神宮の森越しに外宮の背中をチロチロと見ることもできます。
まさに裏道。
内宮を伊勢の表の顔とすれば、外宮は裏の顔。
そのさらに裏の道。裏の裏。
それは、もしかしたら表!?なのか。
そんな大木さん達と小さな神社さん達と小道さん。
———————外宮。
この地の神々がいかに古く、そして、
伊勢の大元の神々が住まう地だということを感じて頂けるでしょうか。
ここまで記したので、
折角ですので最後にもう少しだけ。
現在の伊勢神宮のさらに大元と思われる場所のことを
少しだけ記しておこうと思います。
それが、ここ。
「吾平山上陵=あいらのやまのうえのみささぎ」
またの名を
「あいらさんりょう」
「あいらさんじょうりょう」

場所は九州、鹿児島。大隅半島(おおすみはんとう)の中程。
日本列島の最南端といっても良いような場所。
宮内庁直轄の要地であり、常に厳重に管理されている所。
日向三代(ひゅうがさんだい)として日本神話にその名を残す
「ウガヤフキアエズ=天津日高日子波限建鵜草葺不合命」と、
その妻「タマヨリヒメ=玉依姫」の墓陵と比定されています。
「比定」と書くのは、
ウガヤフキアエズの墓陵としては他にも幾つかの候補があるからです。
現伊勢神宮を定めた倭姫命(やまとひめのみこと)は、
この時の記事に記した通り、
2世代の長きにわたって天照大御神(アマテラスオオミカミ)
が住まうのにふさわしい地を探し、西日本を転々とします。
何度も何度も場所を変え、移動し、
しかし、そんなことの裏には
「ここではないかもしれない......」
と、そう判断させる何かが......
理想像や物差しのようなものが......
あったのだと思うのです。
そんな物差しが明確であったからこそ、
今の伊勢に落ち着くまでに時間がかかった、
ということもあるでしょうし、
伊勢の地を見て
「ここだ!」
と確信的な決断も出来たのだとも思えます。
要は、一度でも伊勢神宮を訪れたことがある人が、
もしこの吾平山上陵に踏み込めば、
今の伊勢神宮の「造り」や「有り様」、「土地のイメージ」など、
その原型の全てがこの吾平山上陵にあることを誰でも、
明確に感じられると思うのです。
伊勢とあまりに似ている佇まいを実感できると思います。
日向三代を継いだ初代天皇「神武=じんむ」は、
九州の地から奈良に入った......と。
九州から関西に渡ってきたと。
神話にはそう記されているわけです。
更に禁断の話的エリアに踏み込むとすれば、
日向三代の話とは「赤」と「白」の話でもあり、
それはこの国の国旗の色でもあり、血脈の話でもあり......
伊勢においては外宮と内宮の色とも言えるもので......
......Maaさんのリクエスト話から、
こんなトコロにまで辿り着いてしまったので、
次回は、そんな日向三代のお話を少しだけ(^^)ええ。ええ。
どもども。
毎年恒例なんですが、、、
伊勢の質問していいですかー??(´・ω・`)
外宮の横の道ってどこですか??
今年はそこ見てみたくて!」
......なんていうことで、
何かと質問を頂ける今日この頃。
なんだかとてもありがたいことでやんす。
そんな毎年恒例だという!?
伊勢大好き!なMaaさん(♀)からの質問ということで。
今回もこの時と同様に、彼女が行ってみたいと言っている伊勢、
外宮のマニアック・ポイントのお話を
ココにチロリと記しておこうかと思います。(^^)
今月末に行くということですので、
今日あたりのお返事というコトでよろしいでしょうかね。
ええ。ええ。
で、今回彼女が行ってみたいと言っている伊勢、
外宮の「横の道」というのは、
外宮の本殿の裏の方に伸びていく「トアル一本の道」のことで。
その道沿いには、実は外宮屈指の「圧倒的な」楠の大木が立ち並び、
二つばかりの摂社、末社がひっそりと佇んでもいます。
この道は神宮の「公式マップ」にも載っていなくて、
Maaさんのようによっぽど
「行こう!」
という明確な気持ちがない限り、
決して訪れるようなこともないであろう場所となります。
普通はマズ知らない場所のハズ、なのですが......
そんな外宮の公式境内マップがこちら......

まずわ、豊受大神宮というのが外宮の正式名称となります。
「トヨウケ」と読みます。
そして外宮。
「げぐう」と読んでいたりする人も多いようですが、
正式には「げくう」。
「くう」でございます。
神様は穢れ(けがれ)......「濁り」を嫌います。
「濁点」はできれば避けたい......という感じでしょうか。(^^)
「内宮」も正式には「ないくう」。
そういう感じ。
例の道は、上の地図では巫女さんの絵が描かれている、
御守りや御札の売場となっている中央の
「神楽殿=かぐらでん」から上の方に行った
「北御門鳥居=きたみかどとりい」と
「御厩=みうまや」の側に、
ヒッソリと細く小さな口を開けています。
北御門口の駐車場近くの鳥居から入った場合、
すぐ右手に見えてくる道。
「この小道には簡単には入らないようにね......」
と、
道の入口付近はそういう声が聞こえて来るかのような佇まい......

この道や、ここにある摂社や末社が
外宮の地図にちゃんと記載されていないのには、
キット「幾つかの理由」があるのだとは思いますが......
少なくとも、僕が歩いた感覚では、
このゾーンに関しては陰陽入り乱れる、
かなりカオスなエネルギーが満ちている様な場所で。
人によっては重々しく感じたり、キツく感じたり。
ハマりすぎて異様な力を感じてしまったり......と、
ナカナカ一般的とは言えないゾーンであることも
理由の一つになっているのではないかと思います。
他にも、現在の神宮ができる以前から伊勢の地を守り、
この地で神を祀ってきた氏族である
「度会氏(わたらいし)」
の祖霊を祀る社(やしろ)があるという事や、
あまりに強力なパワーを発する大木達に利己的で勝手な物やら何やら......
を置く様な人が後を絶たないという理由などで、
ココにはあまり人を入れたくないのかもしれません。
更には、この道の突き当たりには、
もしかしたら外宮で最も大切な場所の一つでは無いか?
とも思われる「上御井神社=かみのみいじんじゃ」がある
ということにも関係しているのかもしれません。
絶対に荒らせない神宮の水源
「上御井(かみのみい)」
伊勢神宮内に捧げられる全ての供物に使われる水は、
実は毎朝この井戸から汲まれ、運ばれているのです。
そして、地図にも載っていて、
誰でも訪れることのできる外宮境内の井戸が
「下御井神社=しものみいじんじゃ」
という名前のワケは、
この「上=かみ」があるからであって。
この道はそんな大切な井戸の真裏に出てしまう......
という、そんな道。
綺麗な水を保つため、
なるべく原生の植生をそのまま保ちたいという場所。
絶対に荒らされてはいけないエリア。
神宮を守る方々のそんな感覚も感じられます。
そしてこの道は、
その井戸の手前で錠前が厳重にかけられた扉と、
周囲を覆う金網の柵で行き止まりとなります。
金網の横にはこんな......
ちょっと絶句してしまうような大木さん達が
辺りの守護についています。
もう神様です。ええ。


こちらは、外宮と共に
「度会神道=わたらいしんとう」
の聖地とも言える「度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ)」。

上記もしましたが、
伊勢の地の宮は元々この外宮が最初であるのだと、
渡会氏は長年主張してきています。
現在の伊勢神宮が建立される以前より、
この地で神を祀り守り通して来た由緒ある氏族の大切な宮。
伊勢での参拝順序が
「内宮より外宮が先である」
とされているのはそういう訳でもあります。
もともとこの地にあった原初の神社が外宮なのです。
そこに、この地があまりに素晴らしかったため、
後に天皇家が内宮を建立したというわけです。
天皇家の祖神とされる「アマテラスオオミカミ=内宮」
を中心とする国家神道において、
あまり表立って語られることの無い歴史の真実でもあります。
この社(やしろ)には心して向かい合わねばいけません。
このゾーンではケータイとは言え、
まともにレンズを向けれないのであります.......
わたくし......
そんな地を通る道沿いにある異様な力を感じる大木さん達は......
やっぱり神様です。ええ。



できればそのままそっとしておいて欲しいとも思われ......
写真は人によってはあまりジーーッと見ないほうが良いとも思われ......
根元に何か置いたり、捧げたりするとかはやめたほうが賢明とも......
思われます。ええ。
エグいっす。
此方はこの道沿いにあるもう一つのスゲー社(やしろ)。
「大津神社=おおつじんじゃ」

内宮の中を流れる五十鈴川の河口にある、
港町の守護神でもある
「葦原神=あしはらのかみ」
を祭っています。
津とは海。
この辺りも古代、海に囲まれた葦の原だったことを思わせる
大切な社だと僕は思います。
そしてこの裏参道からは、
深い神宮の森越しに外宮の背中をチロチロと見ることもできます。
まさに裏道。
内宮を伊勢の表の顔とすれば、外宮は裏の顔。
そのさらに裏の道。裏の裏。
それは、もしかしたら表!?なのか。
そんな大木さん達と小さな神社さん達と小道さん。
———————外宮。
この地の神々がいかに古く、そして、
伊勢の大元の神々が住まう地だということを感じて頂けるでしょうか。
ここまで記したので、
折角ですので最後にもう少しだけ。
現在の伊勢神宮のさらに大元と思われる場所のことを
少しだけ記しておこうと思います。
それが、ここ。
「吾平山上陵=あいらのやまのうえのみささぎ」
またの名を
「あいらさんりょう」
「あいらさんじょうりょう」

場所は九州、鹿児島。大隅半島(おおすみはんとう)の中程。
日本列島の最南端といっても良いような場所。
宮内庁直轄の要地であり、常に厳重に管理されている所。
日向三代(ひゅうがさんだい)として日本神話にその名を残す
「ウガヤフキアエズ=天津日高日子波限建鵜草葺不合命」と、
その妻「タマヨリヒメ=玉依姫」の墓陵と比定されています。
「比定」と書くのは、
ウガヤフキアエズの墓陵としては他にも幾つかの候補があるからです。
現伊勢神宮を定めた倭姫命(やまとひめのみこと)は、
この時の記事に記した通り、
2世代の長きにわたって天照大御神(アマテラスオオミカミ)
が住まうのにふさわしい地を探し、西日本を転々とします。
何度も何度も場所を変え、移動し、
しかし、そんなことの裏には
「ここではないかもしれない......」
と、そう判断させる何かが......
理想像や物差しのようなものが......
あったのだと思うのです。
そんな物差しが明確であったからこそ、
今の伊勢に落ち着くまでに時間がかかった、
ということもあるでしょうし、
伊勢の地を見て
「ここだ!」
と確信的な決断も出来たのだとも思えます。
要は、一度でも伊勢神宮を訪れたことがある人が、
もしこの吾平山上陵に踏み込めば、
今の伊勢神宮の「造り」や「有り様」、「土地のイメージ」など、
その原型の全てがこの吾平山上陵にあることを誰でも、
明確に感じられると思うのです。
伊勢とあまりに似ている佇まいを実感できると思います。
日向三代を継いだ初代天皇「神武=じんむ」は、
九州の地から奈良に入った......と。
九州から関西に渡ってきたと。
神話にはそう記されているわけです。
更に禁断の話的エリアに踏み込むとすれば、
日向三代の話とは「赤」と「白」の話でもあり、
それはこの国の国旗の色でもあり、血脈の話でもあり......
伊勢においては外宮と内宮の色とも言えるもので......
......Maaさんのリクエスト話から、
こんなトコロにまで辿り着いてしまったので、
次回は、そんな日向三代のお話を少しだけ(^^)ええ。ええ。
どもども。