◆富田和子 矢絣(木綿、経絣・経ずらし絣)

◆聖獣バロン

◆魔女ランダ
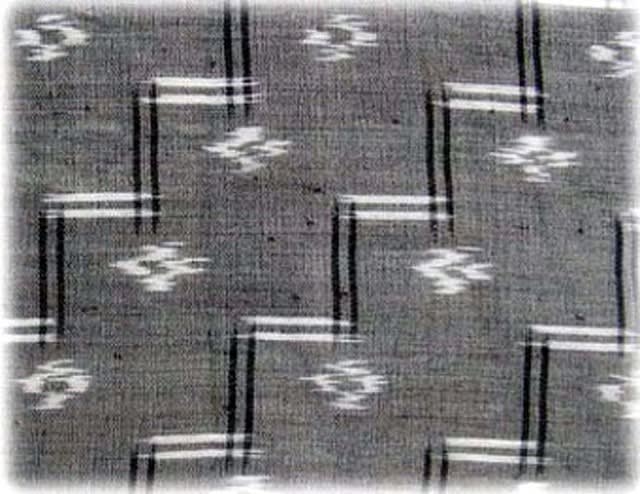
◆琉球絣(木綿、経絣・緯絣・緯ずらし絣)
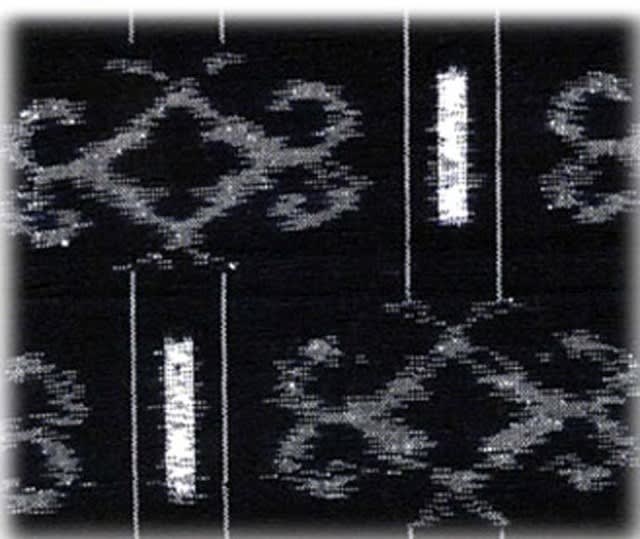
◆伊予絣(木綿、経緯絣・経絣・経ずらし絣)
2005年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 36号に掲載した記事を改めて下記します。
『インドネシアの絣(イカット)』-絣の魅力- 富田和子
2005年4月10日発行のART&CRAFT FORUM 36号に掲載した記事を改めて下記します。
『インドネシアの絣(イカット)』-絣の魅力- 富田和子
◆絣について
経糸と緯糸を組み合わせて布を織っていく…。織物を習い始めた頃は、色糸を組み合わせて縞や格子を作り出すことが楽しかった。自分で糸を染めることを覚えると、やがて絣の布を織ってみたいと思うようになった。織物を勉強した人、あるいは布に興味のある人ならば、絣に心惹かれる人も少なくないように思える。
絣はインドで発生したと言われている。アジャンタ石窟の壁画に矢絣風の模様が見られることから、少なくとも7世紀頃には絣が織られていたと考えられる。その後、絣技法はユーラシア大陸を通過し、世界各地に伝えられた。他の織技法に押されてあまり発展しなかった地域もあるが、インドから、インドネシアを始めとする東南アジア、そして日本へ至る地域では、各地各様の絣が展開していった。日本には14~15世紀頃、外国との交易が盛んに行われ始めた沖縄に絣の技法も伝えられ、当時の琉球文化圏で日本の絣の基礎が築かれた後、徐々に本土各地に分布した。日本の絣といえば、誰もが藍で染めた木綿の紺地に白抜きの絣模様を思い浮かべるほど、江戸時代以降、明治から大正時代にかけて、木綿の絣は広く日常着として活用され、日本人の生活には欠かせないものとなった。日本各地に絣の産地があり、また、絣模様を作り出す様々な技法があることからも、絣は日本人にこよなく愛された織物のひとつと言えるであろう。
ヨーロッパに絣技法が伝えられたのは日本よりも古く、中近東を経て10世紀頃と推定される。ルネサンスの初期である14世紀から、17世紀に至るまで、スペインやイタリアを始めとし、ヨーロッパ各地へと広まった。 日本の絣の技法のひとつに「ほぐし絣」がある。これは、粗く仮織りした糸に捺染(プリント)をして絣模様を作り出す方法であるが、元々はフランスの捺染絣という技法が明治の頃に伝えられたものである。東方の影響を強く受けながらも独自の技法を作り出したにも関わらず、ヨーロッパの絣は現代に受け継がれては来なかった。なぜアジアで、なぜ日本で、絣は好まれたのだろうか。
◆善と悪の終わりなき戦い-バロンダンス
神々の住む楽園と言われ、芸能・芸術の盛んなバリ島はインドネシア随一の観光の島である。島民の日々の暮らしは、バリ・ヒンドゥーへの信仰が基本に成り立っている。バリの伝統的な芸能文化である音楽、舞踊、絵画、彫刻などは、本来、全て神々に捧げるものであり、神々と交信する手段として代々受け継がれてきた。その中の一つに「チャロナラン/バロンダンス」という伝統舞踊がある。
善の象徴である聖獣バロンと、悪の象徴である 魔女ランダの戦いを物語るもので、魔女ランダが呪いや魔術をかけると、聖獣バロンがそれらを取り除くという戦いが繰り広げられるのだが、バロンとランダの力は互角で決着がつかない。どちらが勝つこともなくバロンダンスは幕を閉じる。
バリでは善(良い魂)と悪(悪い魂)とがいつも同時に存在していると信じられているという。 現在では観光用のお馴染みの舞踊だが、本来は 墓地のある寺での儀式と
して演じられ、その際にトランス(憑依)によって、あの世からのお告げや指導を仰ぐためのものでもあるというこのバロンダンスは、聖獣バロンと魔女ランダの姿を借り、両者の終わりのない戦いを通して、善と悪、聖と邪、生と死といった相対立する概念は常に同時に存在し、無限に続くというバリ人の世界観を体現している舞踊である。
当然のごとく勧善懲悪の結末を予想していたので、初めてこの踊りを見たときには、決着のない結末に衝撃を受けながらも、妙に納得し、感動さえした。確かに、一個人を考えてみても、誰もが善と悪とを併せ持っているし、そんな人間達が作り出す世の中もまた清濁混沌としたものである。長所と短所が背中合わせの表裏一体で存在するように、正義を振りかざしたとしても、見方や切り口を変えれば、その正義は悪に成り得ることもある。そんな曖昧な真実の上に世界は成り立っているのではないか。その曖昧さを是とするか非とするか。白黒はっきりと決着をつけないと治まらない民族と、曖昧なグレーゾーンでどのように折り合いをつけていくかを重要と考える民族の違いは、どこから来るのだろうか。宗教を一例に挙げれば、唯一絶対の神を信じることと、八百万の神々を受け入れることなど、宗教観や信仰心の違いとも重なるように思える。洋の東西を問うならば、東洋文化の中で絣もまた、はぐくまれ花開いた。
◆なぜ絣に心惹かれるのか…?
絣は、基本的には糸を括って染まらない部分を作り、模様を表すという非常に単純で素朴な技法である。だが、糸を模様通りに染めること、その模様を崩さぬように織機に準備すること、模様を織り合わせることなど、各工程において、長い時間と正確な技術が要求され、大変な作業である。しかも、確かな技術を持ってしても、絣模様を完璧に揃えることは難しい。明確な織模様を求めるならば、直接的な綴織や組織の変化で表す技法が適している。正確に模様を織りだそうと懸命に努力しても、絣模様はずれてしまったり、かすれてしまったりする。また、括った部分と括らない部分との境界線には、微妙な色の移り変わりがでる場合もある。しかし、それらが絣独特の美を生み出していることも確かである。自然に発生する不均一で曖昧な模様表現が、魅力あるものになっていることは不思議であるが、完璧でも絶対でもない曖昧な絣模様を美しいと感じる人は、絣に心惹かれてしまうのである。











