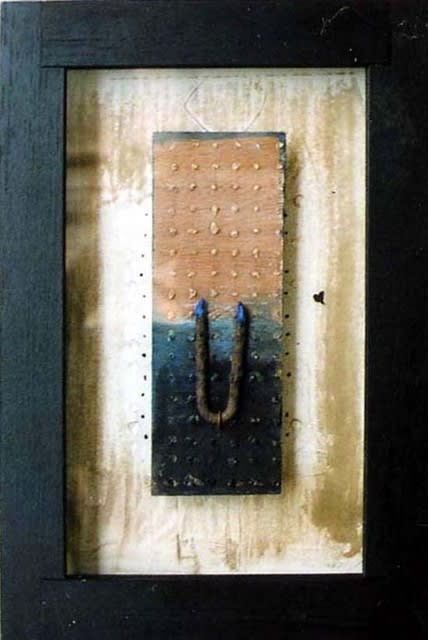
2007年7月10日発行のART&CRAFT FORUM 45号に掲載した記事を改めて下記します。
「まじめな時間」 榛葉莟子
こんなに晴れているのに富士山や遠く近くの山々、南アルプスや秩父連峰などが灰色の向こうに隠れて姿が見えない。八ケ岳でさえも白い紗を覆ったように霞んでいる。散歩の途中霞みの中に消えた山々をぐるり眼で追いながら、奇妙な不安にいつものふかい深呼吸をちゅうちょしていた。春先、遥か遠く中国大陸からの黄色い砂の嵐の余波、黄砂の影響は日本列島に及びます。有害物質が含まれ…云々と天気予報で知らされていたのが頭をよぎっていた。上昇した黄砂は天空をベールで覆い陽のひかりを遮断した暗がりの朝がテレビに映っていた。清々しさに欠けた晴天の朝の空気色の濁りは気のせいではなかったとその一端は想像できる。そして三日目位に上空のベールは一掃された様子でひかる青空を背景に山々の姿はくっきりと静かにいた。
それにしても、おもいっきりの深呼吸にちゅうちょするなんて事は黄砂に限らない。昨今の奇妙きてれつ、複雑怪奇の流れはなんなんでしょうか。複雑過ぎる情報過剰過多を挙げる意見は多い。ならば情報が少ない昔はどうだったのだろう。と比べてみても始まらないけれども、まじめな時間はたっぷりあったといえるかもしれない。その時間は知らず知らずの内に自分が自分を育てている。よりどころのような揺るがない静けさを心の内に養う「ひとり」の時間なのだ。それは特別な事ではなく誰もが当たり前の事として、お互いがお互いをじゃましない礼儀はそなえていたのではないか。まじめの入り口には自分に正直であり素直であるという当たり前のヒトの生の原点が必死に光っている。根底で自分を支えているその静かにひかる無垢の力に蓋をしてはならない。
いっときでも誰かとつながっていなくては不安でたまらないというサビシガリヤはますます増えている現実を耳にする。サビシイとさびしいと寂しいと淋しいと、こうして文字に書いてみれば微妙に違うさびしさが見えてくる。いつでも携帯電話を握り締めていては本の頁はめくれない。まじめな時間の足りなさはどうだろう。まじめな時間は足りているのだろうか。あえていままじめの言葉を使うのは、まじめはダサイとかカッコワルイなどというネガティブの意味にすり替えられてまかり通っていたもったいなくも、時間泥棒の侵入に気づいていない時代があったのはそんなに遠くない。なぜそんな流れが入り込んでしまったのだろう。それはイジメにもつながっていく道筋が見えてくる。まじめが誉め言葉の頃、いじめっこはいても「イジメ」というカッコでくくるワガモノガオの言葉はなかった。まじめという言葉にしてもいじめという言葉にしても、偏った意識を助長させてしまったようにも思う。字を書かなきゃ馬鹿になるよと、いつだったか詩人の大岡信氏の思わず発した警告を思い出す。
この村から村という名称が消えてからは、農村独特の田園風景や空気の変化や森羅万象さまざま触れた何かを文章に描写したいときあれっと流れが止まる時がある。村は町という字の名称に変わっただけで、山や川が消えてしまった訳ではないのに、まったくの創作の場合を除きもう村という字は使えない。村という字の響きは独特な響きだ。響きや雰囲気に連れ出されて、鉛筆の汽車に乗ってそれは遠くに旅をしてきた不思議な感覚の経験もあるし、何よりも村という字に感じる曲線のイメージは静けさにいつも寄り添われているような、それにとてもいい匂いの字なのだ。これからは町の字を好きになろうと思う。それにしてもおもしろいもので創作の場合など字から受けるイメージの色合いは村と町ではまったくちがう。町と街でもちがう。実際、今もどこかで村から町へさらに市へと、何だか路地裏の小路が消しゴムでさっさっと消されていくような事態は、平気な顔して起きていると思われる。名前そのものすら消えて何丁目とか数字の区分けになってしまい、残念とか惜しいとかの怒りの声は日本国中あると思う。あの黒門町なんて町の名がどうして何丁目だからにならなくてはいけないのか、その感覚がいまだに分からない。漢字の町の名前は歴史を語る語り部の役でもあるのに。この国は漢字の国なのになあ。そういえばベトナムはかって漢字の国だったということを最近知った。この現実はすでに哀しい過去形なのだった。知らなかった恥ずかしさを自分のこの国に結ばせたなら、なにかポロポロと平気な顔をしてこぼしているものが見えてこないだろうか。漢字に限らないけれども惜しいことばかりだなあとこの頃胸につかえる事は多い。
もう半年ほど前の事だけれど、夜窓の下で大きな声でなく猫の声に、何事かと見ると家の猫だった。出入りの戸までのジャンプができない瀕死の重症であることが分かった。家族に仲間入りしてまだ間もない若い猫は、覚えたばかりの私たちを頼りに夜遊びのどこからか必死に足をひきずってきたのだった。手術入院通院と治療の日々は三ヶ月を超え、心配をよそに今では走りまわっている。私たちを頼りに必死に戻ってきて声を限りに呼んでいたその姿に私は感動する。生あるものどうし生きたいという本能的な必死さは思い出してもまた感動する。生きるということの原点にぎゅるっと振り向かせられる瞬間であった。




















