
↑朝日新聞 デジタル「自分はつなぎの天皇」 陛下は友人に、そう語った」より
緒方雄大 2018年12月23日
昨日、平成天皇の最後の誕生日の会見動画を見ました。
日本の皇族として生まれ、象徴天皇制下の天皇の職務を30年間担ってきた
「あきひとさん」という正真正銘の一人の人間が、
日本の歴史と現在の中での自分自身の人生を語る中、
「戦争」「沖縄」「犠牲」「国民」「平和」という言葉で涙声になったとき、
(なんと残酷なポジションに生まれてしまったんだ、この人は)
と、本当に気の毒に感ぜずにはいられませんでした。
あきひとさんのお父さんは「天皇は神である」というシステムの下、
かけがえのない個人の多大な命を戦争で失わせ、
敗戦になるや、「いや、これからは人間です」と
自分を誤魔化すのも大変だったでしょうが、
それをすぐ傍で見てこざるを得なかった、
そして、戦争責任も取らず、意味不明の変化を為した天皇制システムの
主軸を担わなければならなかった「あきひとさん」にとって、
お連れ合いの美智子さんがいらっしゃらなければ、
一人でこの非合理性に耐えることはできなかったかも知れません。
「聡明な人ほど苦労する」の典型のようなあきひとさん。
「自分はつなぎの天皇である。
皇太子の代に明るい皇室となれば・・・・・・」
と1993年1月に友人に語ったそうです。
日本会議みたいな人たちが、また国民を天皇の赤子にしようと
時代錯誤の考えやムードを振りまいていますが、
それに同調することなく、
「象徴天皇制」を掲げて対峙しているのが
なんと、天皇家の人たちだということに
国民の一人として私は申し訳ない気持ちがします。
本当は、もっと自由に個人の人生を歩みたかったかもしれない
開明的な思想の持ち主が制度に自分の人生を制限されながら、
それでも押し潰されずに前を向き、
先代天皇の戦争責任を黙って背負い、
何とか次の時代にはよりマシな制度と社会になることを祈りながら
行動されていらっしゃったことに衷心から敬意を表すものです。
しかし、統治機関ではない象徴天皇制は非常に曖昧なものです。
天皇御本人が模索してこられた「弱き民に寄り添う」天皇像は
「ひでりのときは 涙を流し
寒さの夏は オロオロ歩き
みんなに デクノボーと呼ばれ……」
という宮沢賢治の詩の一節を思い起こします。
しかし、決定的に異なるのは、
「一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ」るのでも、
「野原の松の林の蔭の 小さな萓ぶきの小屋にい」るわけでもないところです。
天皇家は莫大な「天領」を持つ超資産家です。
その個人的に努力し稼いで増やしたのではない財産は、
戦後の民主化によって主権を持つようになった
日本の全ての民がO.K.と言ったものなのでしょうか。
敗戦後、農地改革(農地開放)によって、
地主の土地を没収し、農民の半数近くを占めていた小作農も
自分の土地が持てるようになりました。
そのおかげでそれまで小作農だった人が、
自分の農地で自分の農作物を生産し、市場に出荷できるようになりました。
それが日本の農村の近代化の主要因だったことは
誰しも認めるでしょう。
しかし、その時「天領」が没収されたとは聞いていません。
天皇が神様から転じて私たちの仲間の人間になったことの中には
それは含まれないのでしょうか。
「象徴天皇制」は戦後のどさくさで取りあえず拵えたシステムです。
私たちはそんなこともほったらかしで
戦後70年有余も放置してきたのですが、
天皇家の人々にとって、それは苦しみの70年だったと
「あきひとさん」の涙声は
私たちに告げているのではないでしょうか。
天皇陛下、平成最後の誕生日 涙声で「国民に感謝する」 会見全編










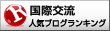

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます