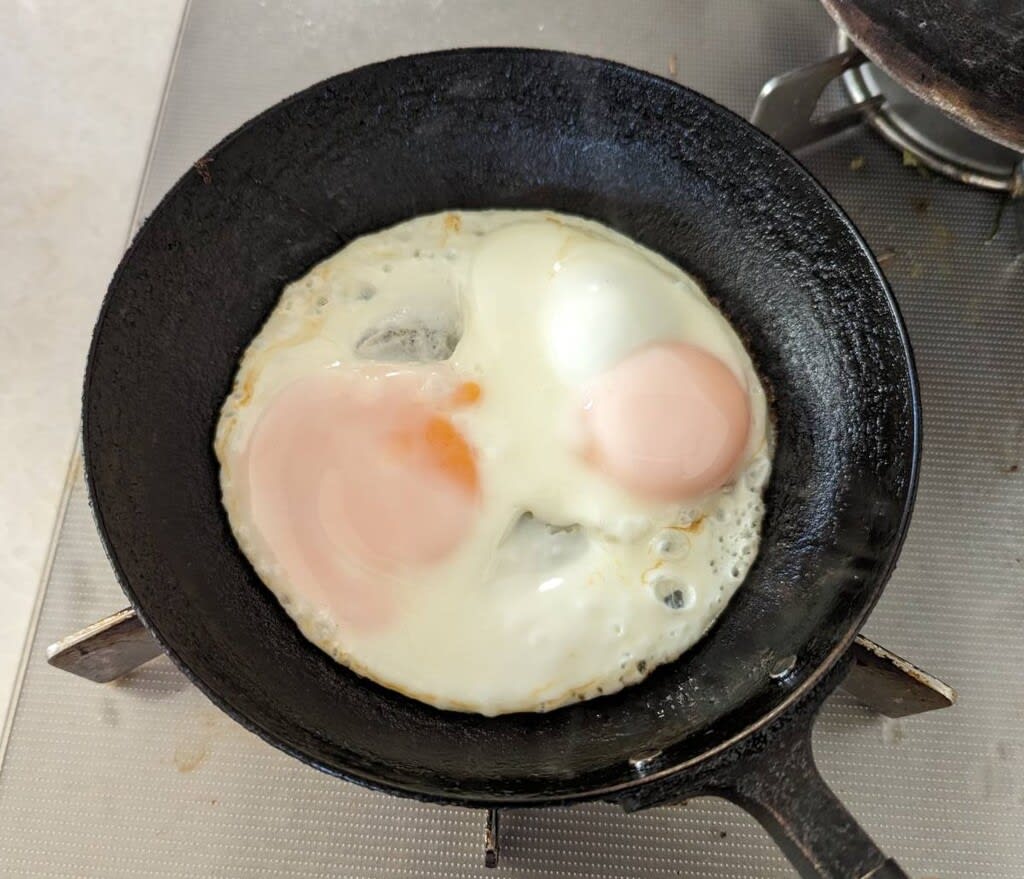
写真:卵を2つ使った目玉焼き(片目はやや失敗しました)
私の育った家では、物心ついたときから、朝ご飯はパン食でした。
これが当然と思っていたのですが、小学校の集団登校でいっしょに行く友だち(いろいろな学年が混じっていました)の話を聞いていると、どうもパンではなく、ごはんを食べている家が多そうだということがわかり、意外でした。
パン以外に何を食べるかというと、目玉焼きです。ただ、私の家ではこれを「目玉焼き」と呼ぶこともありましたが、「玉子焼き」ということのほうが多かったと記憶します。
ふつう、玉子焼きといえば、「厚焼き玉子」を意味するということがわかったのは、小学校高学年になってから。わが家でも頻度は少ないながら、遠足や運動会のお弁当では、いわゆる玉子焼きが入っていました。
目玉焼きも卵を焼いた料理に違いないわけですから、玉子焼きの一種といえるでしょうが。
ある日曜日、近所の友だちがわが家に遊びに来て、昼近くになったので、母が
「お昼ご飯は玉子焼きを作ってあげるわね」
と言いました。出された「目玉焼き」を見た友だちは、
「これ、玉子焼きじゃないよ」
といいました。その子の家では、目玉焼きを食べたことがないようでした。
話を聞くと、その子のいう「玉子焼き」は、「目玉焼き」でも、「厚焼き玉子」でもなく、「炒り卵」のことでした。
家によって、「玉子焼き」の指すものが違っていたのですね。
ところで、当時のテレビのクイズ番組に「クイズグランプリ」というのがありました。
視聴者参加の番組で、分野ごとにさまざまな問題が出題され、早押しで答えるものです。
あるとき、
「目玉焼きで使う卵はいくつ?」
という問題が出ました。
早押しで答えた参加者は「1つ」と答えましたが、不正解。
正解は「2つ」でした。そして司会の小泉博が、
「卵が1つの場合は『片目焼き』ですね」
と言ったのです。
これを見ていたわが家の家族は、声を揃えて
「えーっ! そうだったの?」
と驚きました。
いまだかつて、わが家で卵を2つ使った玉子焼きを作ったことがなかったからです。
「うちのは片目焼きだったんだ!」
もっとも、昔の卵は大きさが不揃いで、ときどきやけに細長いのが混じっていることがありました。そういうのはたいてい「双子」(黄身が2つ入っている)ですね。
それに当たった人は、ラッキーにも、「片目焼き」ではなく「目玉焼き」を食べることができました。
試みに、私が小学生だったころに発行された『新明解国語辞典』(初版、1972年)を引いてみると、
めだまやき【目玉焼】鶏卵を二つ落として、並べて焼いた卵焼き
となっていて、「卵を二つ」使うことが明記されていました。クイズグランプリの「正解」が正しかったことが裏付けられました。
わが家で毎朝食べていたのは、「節約型」の「片目焼き」だったわけです。(辞書に「片目焼き」の項目はありませんが)
続いて、最新の『三省堂国語辞典』(第八版、2022年)を見ると、
めだまやき【目玉焼】たまごの中身を、そのままフライパンに落として焼いたもの。黄身が目玉に見える。
となっていました。使う卵の個数については、言及がありません。
つまり、現代では、卵1個のものも、堂々と「目玉焼き」を名乗ってよいことになります。
調べてみると、目玉焼きの起源は明治時代に遡るということです。
そのころ、卵は高価だったでしょうから、家庭料理というより「洋食屋」のメニューだったと思われます。そのときに使われた卵の個数が2個だった。そして、それを真似した「裕福な家」の目玉焼きは2個だったが、私の生家のような庶民の家では、節約して1個にしたのでは…。
あくまで推測です。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます