PTA会長になってから、知らぬ間に多くの組織の参加者となってきている。
今まで知らなかったこととはいえ、あまりに複雑な成り立ちに困惑している。
が、整理してみたら多少は複雑さが緩和されるかもと思い立ち、どうせならこのブログ上で整理しておこうかと。
もしかしたら、今後同じような立場になる人が検索してくるかもしれないしね(そんなことはないか)
まずは基本的な位置づけとしては
子どもが通っている京都市立九条塔南小学校の「PTA会員」
これは、子どもの保護者であれば自然となる立場。
一応、学校の職員も「PTA会員」となる。
で、そこから学内の立場を表すと
「PTA会員」→「PTA本部役員」→「PTA会長」
ということですね。
ここはまず問題ない。
で、PTA組織としてさかのぼると
「PTA会長」=「単P会長」(単位PTA)→「南P連会長」(支部PTA連絡協議会)→「小P連理事」(京都市小学校PTA連絡協議会)
ここでは「支部PTA連絡協議会」の南ブロック(京都市南区)13校のうち、当番で南ブロック会長が当たっており、結果13校の単P会長の代表として「京都市小学校PTA連絡協議会」の理事となるわけですね。
で、組織としてはさらに
京都市の幼P連・中P連・高P連・総P連が集まって「市P連」(京都市PTA連絡協議会)があり、「日P」(日本PTA全国協議会)の所属していると。
さらにややこしいのは、京都の「市P連」は、「近畿ブロックPTA連絡協議会」と「政令指定都市PTA連絡協議会」の平行して所属しているという…
まぁ、私が会議などに参加するのは「小P連」までですが、全国大会・政令指定都市大会・近畿大会などのイベントには参加することがあるかもしれません。
と、この一本の道ならばまだ理解しやすいのですが…
「単P会長」の所属する地域として、中学校区ごとに「地生連」(地域生徒指導連絡協議会)というのがあります。
うちの場合は「九条中学校」の校区に「九条弘道小学校」「九条塔南小学校」があり、この3校で「九条中学校区地域生徒指導連絡協議会」となります。
で、こちらのほうも当番制で会長が決まるのですが、今年度は我が校が当番…ということで、私が会長ということに。
これも地域によってはさらにブロックでまとまるようなのですが、南区はブロックはなく、各中学校区の会長がいきなり「全市地域生徒指導連絡協議会」に参加となるようです。
「単P会長」(単位PTA)→「九条地生連会長」→「地域生徒指導連絡協議会」
この全市の方はまだ会合に参加してませんので、ここでも役割があたるのかどうかはまだ…。
もうひとつ学校がらみで行くと「学校運営協議会」というものがあります。
これは地域の自治連、社福協議会などの「学校評議委員」(PTA会長もこの理事になります)によって学校運営方針などを話合い、「学び」「豊かな活動」「安心安全」の3部会で活動していきます。
さらに「塔南自治連合会」にも参加各種団体長として「小学校PTA会長」が名を連ねています。
そして行政として「南区まちづくり推進会議」があります。
これは単P会長としては「自治連合会」に所属し、その「自治連合会長」が委員となっているので末端会員なんですが、「南P連会長」が委員になるということで…
と、書いてるだけで疲れてきましたが。
すでにいろいろな会議に参加してきましたが、単年度の役職ですと、今までの活動を理解するまでも行かず、新たな提案を発するまでに一年が経ってしまいそうですね。
実際、総会に出ても「意見・質問は?」と問われて応えられるものを用意できていませんし。
PTAがらみでも、学校側がお膳立てしていて、役職だけPTA会長が担うってのもありますしね。
でも、それだけで終わるのもなんか悔しいのですが。
あまり欲張ると大変なんで、まずは単Pとして内部の充実を優先しながら、「小P連」あたりまでは積極的に。
あとは窓口として、小学校の保護者からあがってくる要望・問題などがあるときに、その橋渡し役として地域や行政に絡んでいく立場かな。
しかし、「一年間、PTA会長をお願いします」という言葉を受けただけなのに、えらいことになってしまってますね。
単Pの方は、自分の都合も考慮して会議日程を決められるんですが、他の組織となるとなかなか思い通りに行かず、ミニカンや勉強会を休むことも増えるかもしれません。
そこはちょっと困ったもんですね。
とりあえず、スケジュール管理をしっかりしなくっちゃ。

















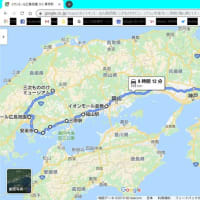


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます