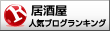電光掲示板で考えた
東京ツアーなどでJRをよく使わせていただいています。
その時に気が付いたことですが、静岡県内を走っている東海道線の電車にはほとんど電光掲示板がありません。
よって、ぼんやりしていると次がどこの駅なのかわからなくなったりします。
ところが熱海から先はほとんどすべての電車に電光掲示板が付いています。
と言ってもドアの上にある小さなものですが、これが次の駅や行き先を知らせてくれるので便利です。
さらに進化をすると、山手線などでは液晶のディスプレーがついていて、そこでコマーシャルなども流しています。
まあこれは掲示板というよりも宣伝媒体です。
さて、この電光掲示板ですが、東海道線のものはほとんどすべて「赤」「緑」と「オレンジ」の三色で、文字だけの掲示です。
駅に付いているものもこれが多いですね。
あとは浜松のバスにもこの掲示板が付いていました。
それを見ているうちにふと考えました。
どうして三色だけなのか?
ここから先は私の推理なので違っている部分があるかもしれませんがご了承ください。
この掲示板はたぶん液晶です。
表示は三色ですが、色の三原色のうち、「赤」と「緑」の二色の液晶を使っていると思います。
その二つの色が混ざるとオレンジになるわけです。
そして明るさの調節はなく、オンかオフの2制御なんでしょう。
2色、4種類の信号で文字を表現するわけですから、シンプルです。
ここに「青」を入れれば三原色が揃いますから、そこに輝度の条件を入れればすべての色が表示できることになります。
しかしそうすると経費が掛かるので単純なものにしたのではないのかとおもいます。
新幹線の電光掲示板は三色が入っていて、白色光もちゃんと表示できるのはその分設備にお金をかけているということですね。
そこで思い出しましたが、「青色の発光ダイオード」は遅れて開発されたということです。
たぶんこのタイプの電光掲示板が作られた時は、「青色」が高価だったんだと思います。
ですから二色にしたんではないかと推理します。
青色が加われば単純計算でも4色増えますから便利ではありますが、文字だけですからその必要性も少ないわけです。
かといって1色だけですと味気ないですからこのタイプが主流になったんではないでしょうか。
LEDもすっかり身近なものになってきて、価格も安くなってきましたから、これからはフルカラーのタイプが増えるとおもいます。
それはともかく、静岡県内の電車にすべて電光表示が付きますように祈っています。
東京ツアーなどでJRをよく使わせていただいています。
その時に気が付いたことですが、静岡県内を走っている東海道線の電車にはほとんど電光掲示板がありません。
よって、ぼんやりしていると次がどこの駅なのかわからなくなったりします。
ところが熱海から先はほとんどすべての電車に電光掲示板が付いています。
と言ってもドアの上にある小さなものですが、これが次の駅や行き先を知らせてくれるので便利です。
さらに進化をすると、山手線などでは液晶のディスプレーがついていて、そこでコマーシャルなども流しています。
まあこれは掲示板というよりも宣伝媒体です。
さて、この電光掲示板ですが、東海道線のものはほとんどすべて「赤」「緑」と「オレンジ」の三色で、文字だけの掲示です。
駅に付いているものもこれが多いですね。
あとは浜松のバスにもこの掲示板が付いていました。
それを見ているうちにふと考えました。
どうして三色だけなのか?
ここから先は私の推理なので違っている部分があるかもしれませんがご了承ください。
この掲示板はたぶん液晶です。
表示は三色ですが、色の三原色のうち、「赤」と「緑」の二色の液晶を使っていると思います。
その二つの色が混ざるとオレンジになるわけです。
そして明るさの調節はなく、オンかオフの2制御なんでしょう。
2色、4種類の信号で文字を表現するわけですから、シンプルです。
ここに「青」を入れれば三原色が揃いますから、そこに輝度の条件を入れればすべての色が表示できることになります。
しかしそうすると経費が掛かるので単純なものにしたのではないのかとおもいます。
新幹線の電光掲示板は三色が入っていて、白色光もちゃんと表示できるのはその分設備にお金をかけているということですね。
そこで思い出しましたが、「青色の発光ダイオード」は遅れて開発されたということです。
たぶんこのタイプの電光掲示板が作られた時は、「青色」が高価だったんだと思います。
ですから二色にしたんではないかと推理します。
青色が加われば単純計算でも4色増えますから便利ではありますが、文字だけですからその必要性も少ないわけです。
かといって1色だけですと味気ないですからこのタイプが主流になったんではないでしょうか。
LEDもすっかり身近なものになってきて、価格も安くなってきましたから、これからはフルカラーのタイプが増えるとおもいます。
それはともかく、静岡県内の電車にすべて電光表示が付きますように祈っています。