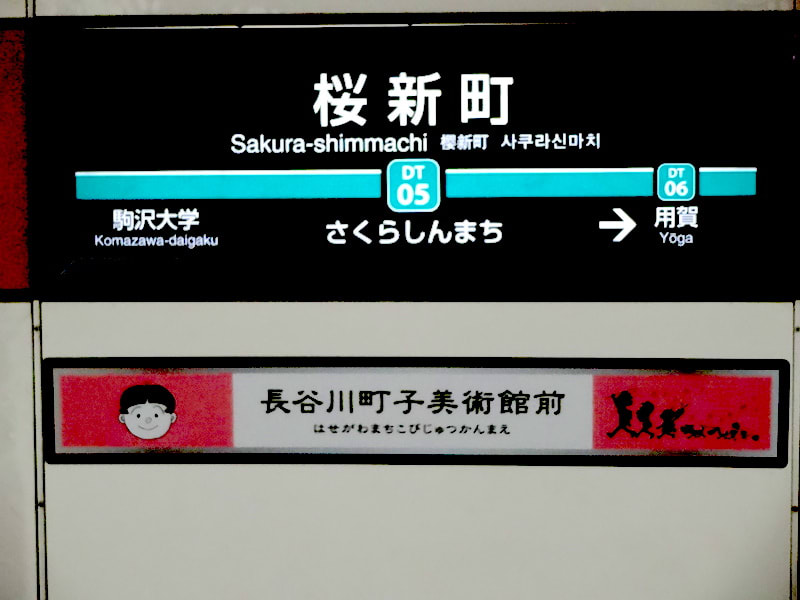私が住んでいる川崎市では「みなし適用」という制度を8月から実施しています。これは、川崎市のサイトに掲載されている「川崎市寡婦(夫)」控除のみなし適用の実施」の説明を借りると「ひとり親家庭の支援施策の一環として、未婚で20歳未満の児童を養育するひとり親家庭を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施」するというものです。今年の7月22日、「川崎市寡婦(夫)控除のみなし適用に関する運用を定める要綱」が市長により決裁され、8月1日から実施されています。
所得税法第81条には「寡婦(寡夫)控除」が定められており、同第1項で「居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する」とされています。「寡婦(寡夫)控除」は地方税法にも定められており、同第34条第1項第8号により都道府県個人住民税に、同第314条の2第1項第8号により市町村個人住民税にも適用されます。また、同第314条の6は「調整控除」を定めていますが、その第1号イ(3)および(4)にも「寡婦(寡夫)」に関する規定があります。
しかし、「寡婦(寡夫)控除」は、一度でも婚姻歴がある者にのみ適用されます。所得税法第2条第1項第30号は寡婦を次のように定義しています(地方税法第23条第1項第11号、同第292条第1項第11号もほぼ同旨)。
「イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの」
また、所得税法第2条第1項第31号は、寡夫を「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう」と定義しています(地方税法第23条第1項第12号、同第292条第1項第12号もほぼ同旨)。
以上により、婚姻歴の無い一人親には「寡婦(寡夫)控除」は適用されませんから、所得税や住民税において寡婦または寡夫よりも負担が重いことになります。また、話が租税法の領域に留まらなくなることにも問題があります。結局、深刻化するひとり親家庭(とりわけシングルマザー)の貧困問題に、租税法では対処のしようがない、と記すと行き過ぎかもしれませんが、限界があることは確かなのです〔現状などについては、赤石千衣子『ひとり親家庭』(岩波新書)が参考になります〕。
そこで、川崎市が「寡婦(寡夫)控除」のみなし適用を始めた訳です。市も断っているように、所得税法および地方税法の規定により「税法上の控除を受けることはできません」が、上記要綱の「別表第1(第2条関係)」によれば、対象事業は「市立保育園保育料等補助事業」、「日常生活支援事業」、「高等職業訓練促進給付金等事業」など、計34の事業について「寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等を行う」こととなります。
対象者は、市の上記要綱第3条により、次のように定められています。
「みなし適用の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、対象事業を利用する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)未婚の母又は父であること。
(2)前号に規定する未婚の母にあっては、扶養親族である児童又はその者と生計を一にする子を有し、及び現況日においても有していたこと。ただし、地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に定める控除を適用する場合には、扶養親族である子を有し、及び現況日においても有しており、かつ合計所得金額が500万円以下である者に限る。2人以上の子及び児童がいる場合においては、末子が20才未満であれば足りる。
(3)第1号に規定する未婚の父にあっては、生計を一にする子を有し、現況日においても有していたこと。2人以上の子がいる場合においては、末子が20才未満であれば足りる。」
用語の定義という問題もあるので、要綱の第2条も示しておきます。
「この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)子 他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない20才未満の子で、かつ、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(2)児童 20歳に満たない者で、かつ、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3)未婚の母 参照する税の課税年度(以下「課税年度」という。)の現況日(課税年度の前年の12月31日。以下「現況日」という。)以前に婚姻によらないで母となった女子であって、婚姻したことがなく、婚姻(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者及び現況日においても婚姻をしていなかった者をいう。
(4)未婚の父 現況日以前に婚姻によらないで父となった男子であって、婚姻したことがなく、婚姻(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者及び現況日においても婚姻をしていなかった者で、かつ課税年度の合計所得金額が500万円以下である者をいう。
(5)控除対象配偶者 地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第7号並びに第292条第1項第7号及び所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に定めるものをいう。
(6)扶養親族 地方税法第23条第1項第8号並びに同法第292条第1項第8号及び所得税法第2条第1項第34号に定めるものをいう。
(7)合計所得金額 地方税法第23条第1項第13号並びに同法第292条第1項第13号及び所得税法第2条第1項第30号ロに定めるものをいう。
(8)対象事業 みなし適用の対象となる事業をいい、別表第1のとおりとする。
(9)申請窓口 別表第1のとおりとする。」
以上ではわかりにくいかもしれませんので、再び「川崎市寡婦(夫)」控除のみなし適用の実施」から引用しておきましょう。
「所得を計算する対象となる年の12月31日及びみなし適用の申請時点において、次の1から3のいずれかに当てはまる人です。
ただし、4月1日に遡って適用する場合には、所得を計算する対象となる年の12月31日及びみなし適用の適用期間において、次の1から4のいずれかに当てはまる人です。
1 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者
2 1であり、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が、500万円以下である。【寡婦(特定)控除の対象】
3 婚姻によらずに父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者。ただし、父の合計所得金額が、500万円以下に限る。
4 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、20歳未満の税法上扶養する児童(合計所得金額が38万円以下)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者」
さて、実施から2ヶ月ほどが経過した「みなし適用」ですが、これについて、今日の3時付で神奈川新聞社が「『みなし適用』の申請23世帯のみ 未婚一人親世帯の寡婦控除」として報じています。
この記事によると、「みなし適用」の申請者数が10月20日の時点で23世帯であったとのことです。内訳は保育料23件と市営住宅使用料1件で、保育料については計189万円ほど、市営住宅使用料については5万9千円ほどでした。
市は保育料の減免に絞っても100世帯程度、全体では約750世帯と予想していたようで、利用料減免、補助金や給付金などの総額をおよそ1300万円と読んでいました。これは直近の国勢調査(2010年10月実施)の結果を基にしたものです。反響はそれなりにあったようですが、8月開始というのはいかにも中途半端な時期であるだけに、少なくとも現段階において見通しより少ないとしても仕方のないことでしょう。また、今年の4月に遡っての適用を申請できるのは今月までとなっていますが、事務処理上の問題もあるとは言え、短いような気もします。
もう一つ、上記神奈川新聞の記事に市の担当者のコメントとして「実際に申請するかどうかは各家庭の判断」と書かれていたことに気を留めておきたいところです。それ以上に踏み込まれてもいませんが、昨今の「福祉叩き」と表現すべき風潮、福祉制度の利用に対する批判的な論調が強い状況においては、申請がはばかられるということになるのではないか、と懸念されるのです。スティグマ(stigma.歴史的に烙印、焼き印を意味し、比喩的に汚名の意味をも有する言葉)を押されることを恐れるという傾向は、生活保護申請に対する「水際作戦」が示すように、肝心の行政活動によって助長されたりすることもあります。川崎市がそのようなことをせず、制度の趣旨を生かした運営を行うかどうか、注意深く見つめる必要があります。
自分がどのようにして生まれ、育ってきたかということは、多くの偶然が積み重なって出来上がることです。いつ親が死ぬかもしれませんし、いつ貧困に陥るかもしれません。常に我々は、たとえ現在は良い状況、恵まれた状況に置かれているとしても、いつ悪い状況に転じるかわからず、常にそうしたものと背中合わせになった状態で生きているのです。こんな簡単なことがわからないという人が多すぎるような気もします。
なお、川崎市は今年の6月に「ひとり親家庭の生活の安定に向けた寡婦(夫)控除のみなし適用実施方針」も策定しています。