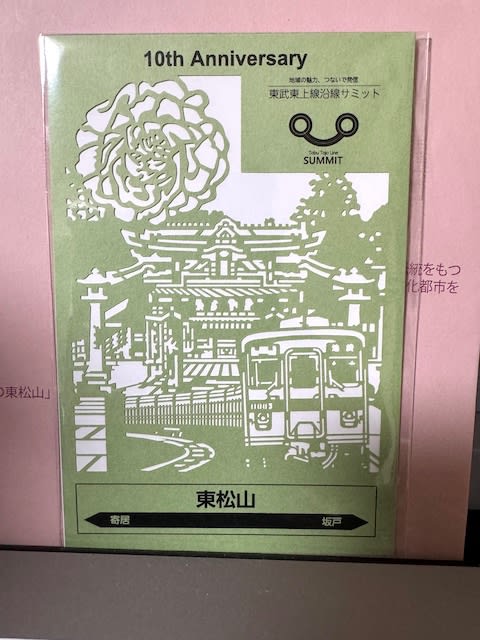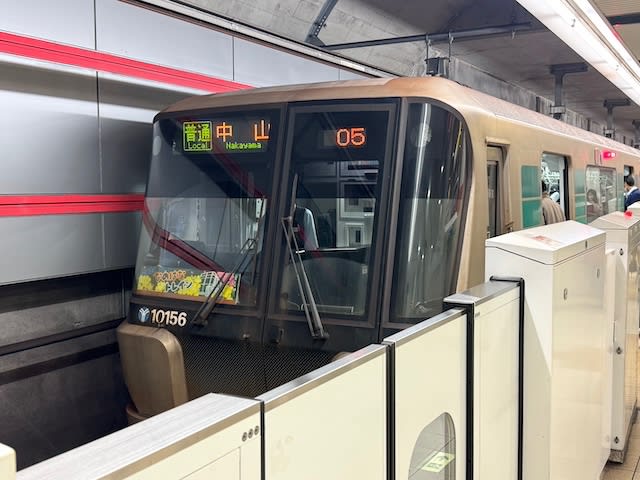2023年10月31日に「学校タブレット故障多発問題」という記事を載せました。今回はその続篇です。
2024年3月17日の10時30分付で、共同通信社の47ニュースに「後藤田知事も激怒、高校生に配備のタブレット「3年もたず半数超が故障」の異常 後手に回る教育委員会、中国メーカーからは返答なし」(https://nordot.app/1138751085466010550?c=39546741839462401)という記事が掲載されています。
「学校タブレット故障多発問題」においては「単純に計算すれば1台が48000円超であったということになります」と書きましたが、上記47ニュース記事には「1台あたりの価格は4万8950円だった」と書かれています。2021年に発売された第9世代のiPadは、仕様にもよりますが最低で39800円(64GBモデル。ちなみに、私は256GBモデルを買いました)でしたし、2020年に販売された第8世代のiPadは最低で34800円でした(アップル社の場合は学校関係者に関して割引があります)。どう考えても徳島県で問題になったタブレットは高すぎると思えます。安物買いの銭失いといいますが、その言葉が当てはまっているとも言えないだけに、問題となっているタブレットの仕様は一体いかなるものであったのかが気になります。
1万6500台が調達されたタブレットの半数超が故障するというのは異常な事態です。2021年4月から使用されているというので3年が経過しようとしていますが、その間に半数超が使えなくなるということは、あまり例がないでしょう。「修理したり予備機を使ったりして対応しているが追い付かず、現在も7千台以上が不足する。正常な状態に戻るのは9月ごろになるという」と書かれていて、そんな状態だったら新しい機種でも入れたほうがよいのではないかとすら思えてきます。予算の都合もあるでしょうが、早く対応すべきでした。「学校タブレット故障多発問題」でも書きましたし、上記47ニュース記事にも書かれていることですが、2021年5月24日、徳島県立城ノ内中学校で、ツーウェイ社のHi10Xというタブレットが焼け焦げた状態で見つかっており、バッテリーから傷が見つかったとのことです。この段階では他の端末に不具合が見つからなかったらしいのですが、一歩誤れば火災につながりますから、何らかの対策をとるべきでした。しかし、徳島県教育委員会は消費者安全法に基づいた消費者庁への通知を怠っていました(ちなみに、この通知は義務付けられています)。実際に連絡されたのは2023年11月のことです。
現在問題となっているのは、同じくツーウェイ社のUBOOKというモデルです。何時頃から導入されたのかわかりませんが、2023年7月に故障が急増したようです。上記47ニュース記事には「厳しい暑さが原因とみられるバッテリーの膨張が各校で続出した。約850台の予備機を投入しても間に合わず、1台の端末を複数の生徒で共有するなどしてしのいだ」と書かれていますが、この時点でいくつもの疑問が生じたはずです。大体、猛暑あるいは酷暑がバッテリー膨張の原因であれば、UBOOKに限らず、iPadなどでも同様の症状が多数発生するはずですし、徳島県だけではなく、例えば神奈川県に住んでいる私のiPadもおかしくなっていたかもしれないはずです。
ともあれ、故障が急増したのであれば、と考えるところですが、徳島県教育委員会が何かをしたのかといえば「県の知事部局に代替機を確保するための予算措置の相談をしていなかった」というのです。「約850台の予備機を投入しても間に合わ」なかったのであれば、授業などに支障を来していたことになるはずですが、教育委員会の担当者曰く、「学校が夏休みに入ってしまい、故障台数の集計に時間がかかった。故障の全体像が見えてきたのが9月下旬だった」。台数の把握や集計は後の問題だろうと言えるでしょうし、夏休み云々以前の話だろうとも考えられるのですが、11月27日に故障台数が6301となったというのも或る意味で凄い話です。
2023年11月30日、徳島県議会は補正予算を可決しました。その内容に「代替機6500台をリース方式で調達する費用7200万円」が入っていました。その上で「今年3月末までに納入業者の無償提供も含めて7千台を調達し、新年度が始まる4月には1人1台が配備できる算段だった」とのことですが、その算段は甘かったようです(上記47ニュース記事からの引用が多くなることを御容赦ください)。2024年に入ってからも「1月下旬、充電後にバッテリーが1時間未満しかもたない新たなトラブルの報告があった。教育委員会は充電器に接続しながらであれば使用できるため、外付けバッテリーの確保などで対応できないか検討している」。2月29日には県議会文教厚生委員会において県議会議員からの怒りが爆発しました。「納入業者やメーカーの責任を追及すべきとの声が相次いだ」のは当然の話です。
泥沼という言葉が当てはまるような話になっていますが、調達に何らかの問題があったのでしょうか。県の支出額からして入札が行われるのは当然であり、一般競争入札が行われたようです。ただ、その入札に参加したのは四電工徳島支店のみだったそうで、「四電工が複数の代理店に調達を依頼したところ、想定する仕入れ価格に見合うのがツーウェイ社の製品のみだったと説明する」と記事には書かれていますが、ここにも私は問題の所在を感じます。さらに、ツーウェイ社からは何の反応もないとのことです。
2月、徳島県監査委員が監査結果を公表します。徳島県のサイトを参照すると、2024年2月9日付の徳島県監査委員公表第3号が掲載されています。そこには、次のように記されています(引用文の後のかっこ書きは私によるものです)。
「県立高校分の入札は、令和2年9月28日に実施しており、1社のみ((株)四電工徳島支店)の参加で落札し、契約を締結した。県のアプリ調達が、入札不調により業者決定に3週間の遅れが生じたため、納入期限日を当初の令和3年3月31日から、4月30日に変更する契約を締結し、令和3年4月28日に徳島市との共同調達分を含めた17,500台のうち、県分の16,500台が納品された。」(県立中学校の分は省略しました。)
「県立高校分の端末の仕様については、文部科学省の標準仕様書に示されているストレージ容量『64GB以上』に対し、教育委員会教育政策課が作成した仕様書では『128GB以上』とされている。同課によれば、「納入後にOSの大型アップデートが想定されたことや多数のアプリを保存する必要があること等から、容量を増やした。』との説明があった。/この点については、その意思決定がなされた過程が分かる書類が不存在であったため、書面で確認することはできなかった。ただ、本県以外の3県がストレージ容量を『128GB以上』としていることから、ストレージ容量を増やしたこと自体が必ずしも適正さを欠いていたとは言い切れない。」(/は原文における改行箇所。求められるストレージ量のためにiPadが外されたということでしょう。しかし、私が第6世代iPadを2018年5月12日から2022年1月28日まで使用し、同日から現在に至るまで第9世代iPadを使っている経験からすると、タブレットのOSの大型アップデートがあるとしても128GB以上というのは高すぎる要求であるように思えてきます。iOS以外のものは相当に仕様や性能などが違うようです。)
「県立高校分の予定価格については、先に実施された県立中学校分の予定価格に加えて、県立中学校分の国庫補助額の算定には含まれていない『ネットワーク設定やウイルス対策ソフトのインストール及び動作確認等の初期設定を含めたものである。』との説明を受けたが、その積算根拠及び事前の参考見積りの徴収については書類で確認できなかった。また、本県と同様に128GB以上のストレージ容量に設定した3県の予定価格は確認できなかった。」(書類で確認できないというは不思議な話です。また、県立中学校と県立高校とでネットワーク設定、ウイルス対策ソフトなどの点で違いがあるのは、どういう理由に基づくのでしょうか?)
「なお、次の3点を意見として述べることとする。
1点目は、物品の調達手続についてである。
全国の自治体による学習用端末の一斉確保やコロナ禍における部材の高騰などに より需給がひっ迫する中で、最低価格落札方式を採用したことから、発注者にとっては、製品の品質よりも価格を優先した物品納入がなされる恐れが生じていた。今回の物品調達においては、その危惧されたリスクが発現したと言えなくもない。タブレット端末製品は、一般の物品に比べ、その品質や耐久性について、本来は配慮が求められるものであるが、その対策が不十分であった。
なお、タブレット端末に限らず、今後の物品調達にあたっては、事前の市場調査を徹底するとともに、従前の仕様要件では必要とはされていなかった『製品の耐久性』を担保する第三者機関の認証を追加するなど、調達内容に応じた『品質の担保』 や『故障リスクの回避』に向けた対策を十分に検討すべきである。
2点目は、調達物品の保守管理についてである。
県立高校において、令和5年12月11日現在、納入台数の約39.3%に当たる6,487台(うちバッテリー膨張によるもの5,510台)の端末で故障が発生している(下表参照)が、落札業者との間で、納入後1年間しか無償の修理はできない契約となっている。教育委員会教育政策課によれば、『端末の調達を検討する段階において、 当初は保守契約付リース契約を考えていたが「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源とした「危機管理調整費」から費用を捻出することとなり、複数年にまたがる保守契約料を支出することができなかった。』との説明を受けた。
本来であれば、無償の保証期間が終了する前に、保守契約に係る検討を行うべきであるが、当時の状況を書面で確認することはできなかった。無償の保証期間の終了後の端末の故障が増加していた令和4年度において、『保守契約に係る予算措置の検討は行ったが、結果的に、保守契約は締結せず、その都度修繕費の予算措置で対応することとなった。』との説明を受けた。 このように対症療法的な対応は行っているものの、令和3年1月に策定された『徳島県GIGAスクール構想』には、『機器導入後5年間端末を利用する必要がある ことを考えると、機器保守契約を締結し、教育活動に支障を生じさせない必要がある。』と記載されていることに対し、それを着実に履行する努力を怠っていたと判断せざるを得ない。
3点目は、危機管理意識の徹底についてである。
令和3年5月に県立中学校において端末の不具合が発生した際には、『県立高校分の端末は、同メーカーの製品とはいえ機種が異なることから、同様の不具合は想定されなかった。』との説明を受けた。国内で流通している主要メーカーや第三者機関の認証を受けた製品であるならまだしも、国内での納入実績の乏しいメーカーの端末であったことを鑑みれば、通常以上に危機管理意識を持って一斉点検を行うべきであった。
以上の3点について、今後の物品調達事務や保守管理業務がより適正なものとなるよう期待する。」(なお、下表は省略しました。)
監査委員の意見の妥当性はここで問いませんが、かなり厳しい意見であることは確かでしょう。とくに3点目については「その通り」と言わざるをえません。ただ、私は、やはり教育委員会における仕様の設定や機種の選定(最終的には納入業者側が行ったとしても、教育委員会も或る程度は選定なり想定なりはしていたでしょう)に問題があったと考えざるをえません。それとともに、ギガスクール構想そのものの問題点はなかったのか、冷静に検証することが必要でしょう。