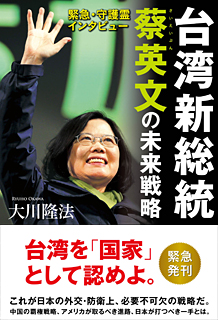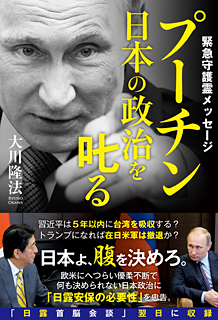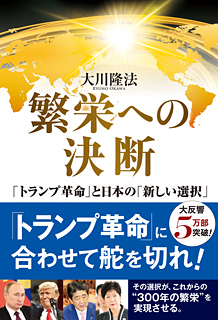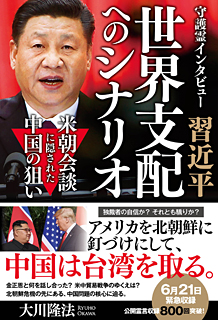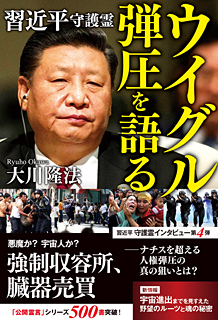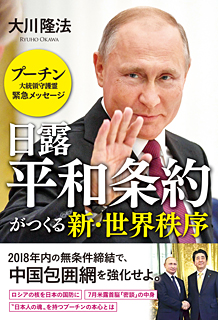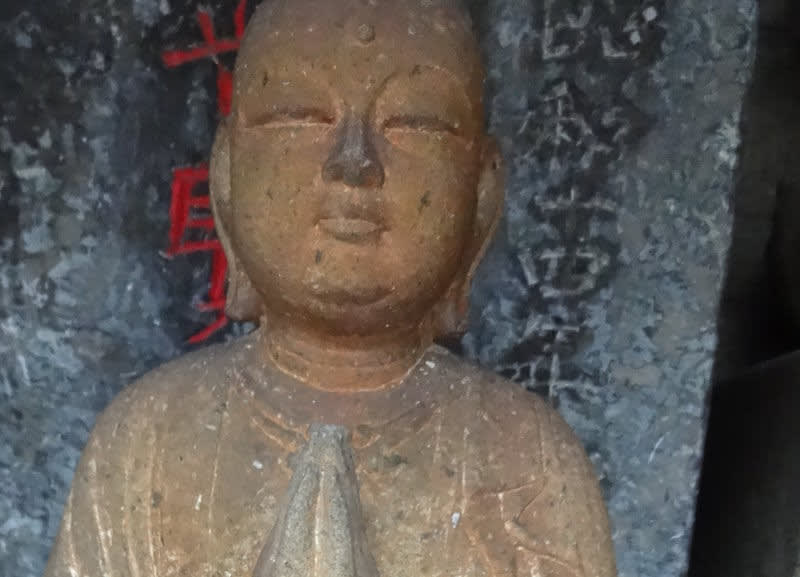
冬至過ぎ 蝋燭一つ 光増し
中村 梅士 Baishi
冬至と言い、クリスマスと言い、蝋燭の灯りが心に浸
みる季節である。
今日は思い切って音楽聴き放題というプライムミュー
ジックに加盟した。
夜になって、グレゴリオ聖歌を聴いている。
静かな祈りの雰囲気があって、『青銅の法』を読み終
えることができた。
岐阜の友人に伊木力みかんを送ったが、ワープロ書き
のハガキが届いた。
クリスマスの時期という事で、燭火賛美礼拝などのこ
とが綴られていた。
クリスチャンになっているようだ。
「エホバの証人」でなければよいがと心配したが、そ
の匂いはしなかった。
よかった。
教会でキリストの生誕を祝うのは最も楽しみな時期で
ある。
年金生活でやりたいことができる身分のようである。
信仰に生きているなら、それはめでたいことである。
仲間とバンドを組んでアコースティックギターを担当
しているという。
良い年を迎えるであろう。

青銅の法とは、重い信仰の扉を押しあけて、無私なる
境地で愛に生きる覚悟という事のようである。
最も難しいのは、裁き心を捨て、許しの愛に生きるこ
とであろう。
それは、菩薩の境地でもあろう。
しかし、許せない人間は多い。
職場にも許せない無礼な人間がいる。
許せないと言っても、関わらないという姿勢であるが、
人間関係は最小限にしている。
しかし、裁いていることには違いない。
迷惑スマホ族に対しても許しがたいと感じている。
不愉快千万である。
食事処で喫煙し、道路では火が付いたままポイ捨てす
る喫煙者も許せない。
そのように、他人の迷惑を顧みない下等な人間たちに
は死をと思ってしまう。
行いと人とは別だと言うが、人から発するのが行いで
あろう。
道義的責任ないし人格形成責任という刑法理論もそう
いうことだろう。
理屈としては、行いの限りで法的責任をとえばよいの
であって、行いを全人格的に裁いてはならない、人を憎
んではならないというのだろう。
しかし、人格と行為を区別することができるのか。
確かに、リンカーンも「人を裁くな、自分が裁かれた
くなければ」と言い、D・カーネギーも「神でさえも、
死の時まで待っていてくださる」という言葉を紹介して
いる。
イエス・キリストの隣人愛でも、「右の頬を打たれた
ら、左の頬も出せ」と言う。
なるほどと思う。
しかし、憎たらしい人間のために祈れと言われても、
本気では祈れない。
理屈ではないのだ。
それが自分の正直な信仰レベルであるらしい。
信仰体力の弱さなのだろう。
青銅の扉は何とも計り知れない重さである。
日本国独立宣言・神聖九州やまとの国
New Asia Happiness Party