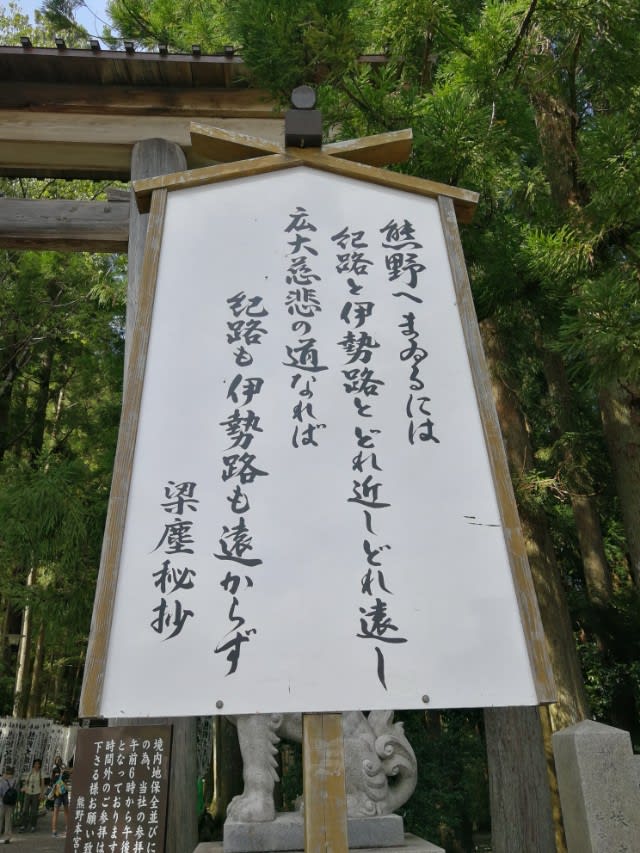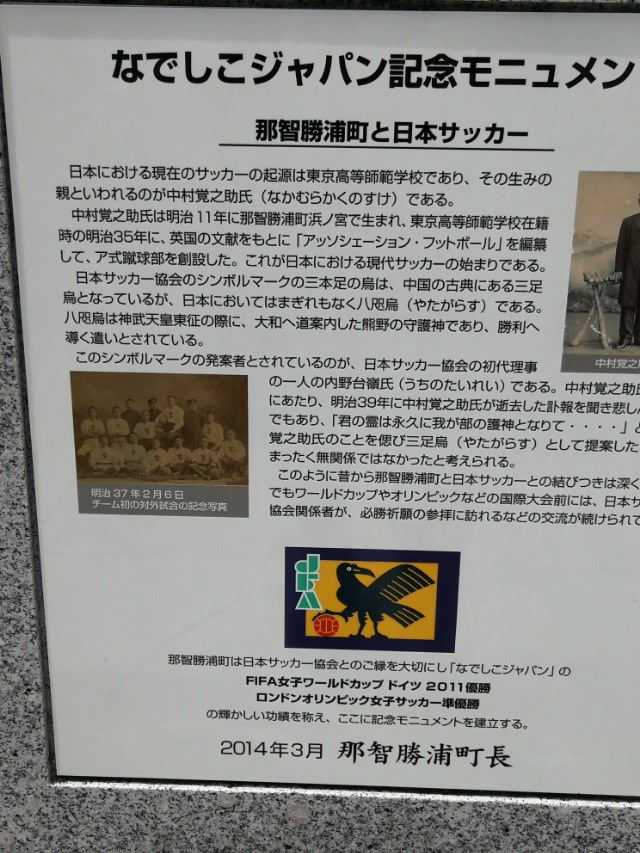今日お墓参りをしてきた。
父の死が東日本大震災と原発事故に重なって、家族だけの見送りになったのと同じように、妻の一周忌は新型コロナウィルスの非常時態宣言のため、母と息子(上)と3人3代で墓参りを済ませてきた。
首都圏にいる息子(下)は呼ばなかった。
若い時分は、法事なんて何の意味があるのか分からなかった。
今は少しその意味が分かるような気がする。私にとっては、可能性の扉を一つ一つ閉じていく営みなのだ。
だからこれはあくまでも現在形の仕事だ。
過去に止まってはいられない、と思っていたのは30代までのこと。
40代になると、いままでやってきたことの「報い」というか、「結果」が出はじめる。
50代になると、何はともあれいままで考えてきたことややってきたことの大きな全体像が見えてくる。
一方、平凡な人生を歩む私たちにとっては、今までと同じだけ時間をかけて何かをすることは、もはや許されていない、と自覚させられる年代でもある。
父は、震災の存在すら理解せず、ただ「家に帰りたいよ」と呟きながら亡くなった。
妻は「令和」の年号が発表された後、「知らなくてもいいことを知ったね」と笑いながら死を受け入れた。
お墓にお参りしたり、法事を執り行うのは、その人と共に生きてきた人生の可能性の扉を一つ一つ静かに閉じていく行為なのだ、と今は思う。
1人の人間が亡くなったからといって、「遅るる者たち」の心の中からその人の存在が消去されるはずはない。
また一方、どんな身近な家族であろうと、乳幼児でもなければ24時間を共に生活はしないだろう。
私たちは幾分かは常に、「記憶の中のその人」といつも一緒に生きているのだ。
だから、その人は死んでもいなくならない。私たちが次に会ううまでは「記憶されたその人」と付き合っているように、それと同じように私たちは死者とも付き合っている。
もちろん、死んだことは分かっている。だが、ちょうど連休中に読んだガルシア・マルケスの『百年の孤独』に登場する死者の亡霊のように、私たちは彼らを見、彼らと対話しながら生きていくのだ。
そしていつか、死者たちは二度目の死を迎える。それは亡霊となった彼らが、私たちと共に生きる可能性が閉じられた時だ。
それは必ずしもこの世の中から亡くなった日、ではない。
一方、思い出さなくなったときが終わり、でもないだろう。一生記憶の中には思い出として残っている。
今考えているのは、それとは少しべつの話しだ。
こうして、何度かの墓参りをし、法事を済ませ、仏壇や神棚などに手を合わせていく中で、そのの人との新たな出会いの可能性の扉を一つ一つ閉じていく。
そういうことだ。
その「可能性の扉」を閉じる終わり方は、繰り返し終わっていくリアルタイムな仕事の結果、訪れるのかもしれない。
可能性、とは何だろう、ということも考えるようになった。
人生に無限の時間が与えられてはいないのだから、私たちは有限の生を生きる。そこでは可能性は開かれているものの、限りもまた、ある。
有限の生と有限の生が互いに出会い、影響しあって生きることの中に、「より良き生」がありえるのだともし考えるとすれば、それは「可能」を生きる、ということなのかもしれない、とも思う。
私にとっては共に生きる可能性が無くなることが、悲しさの一番なのかもしれない。
これから一緒に旅行に誘おうと思っても誘えない。
美味しいものを分かち合おうとしても分かちあえない。
1人で過ごしてても、いつか一緒に語らいたい、と思うこともかなわない。
それは、愛着とはおそらく少しちがうのではないか、と思う。
人との別れが悲しいのは、愛着ゆえ、だけだとはどうしても思えない。
愛着や依存という情緒はもちろんあるし、大切でもある。
だが、それが一番掛け替えのない感情だとも思えないのだ。大事な人やもの、ことを失えばそれは寂しいし、悲しい。
だが、本当に自分に問い直してみるとき、人との出会いが終わりを迎えるとき、「愛着」が一番だというのは端的にどこか足りないような気がしている。
とはいえ、それを声高に主張すると、まるで愛情の欠如の現れでもあるような気もして、言葉にするのもためらわれる。
愛着や依存、思い出にすること、とは少し違う形で、「可能性の扉」を少しずつ閉じていく営み。
その辺りの事情を、妻の一周忌の雨の夜、自分なりにゆっくりと考えている。