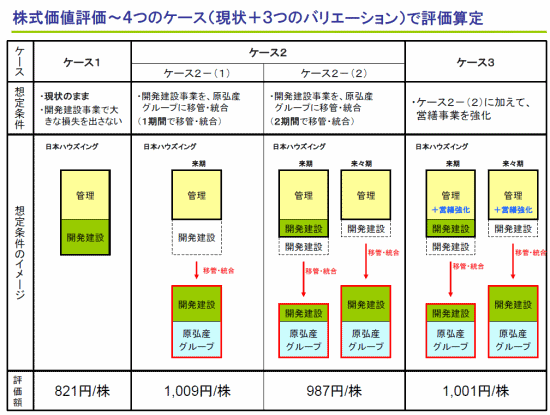大荒れの株式相場のなかでは、もはや後日談程度の話題性しかありませんが。
日本ハウズイング株式会社に対する買付説明書の提出のお知らせ
(平成20年10月20日 株式会社リロ・ホールディング)
当社は、平成20 年10 月20 日開催の取締役会において、株式会社原弘産、井上投資株式会社および株式会社カテリーナ・イノウエ(以下、本売主)との間で、日本ハウズイング株式会社(以下、日本ハウズイング)の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、本買収防衛策)に基づく対抗措置が発動されないことを条件として、本売主の保有する日本ハウズイング株式を譲り受ける株式譲渡契約(以下、本株式譲渡契約)を締結することを決議し、同日、日本ハウズイングに対し、本買収防衛策に基づき誓約書および買付説明書(以下、本買付説明書)を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
ヘロヘロの原弘産(+井上投資)から買うだけでなくカテリーナ・イノウエとも話がまとまったんですね。
これに対しては日本ハウズイングはいきなり尻尾を振っています。
株式会社リロ・ホールディングからの買付説明書の受領について
(平成20年10月20日 日本ハウズイング株式会社)
当社は、本買付説明書提出に先立ち、リロ・ホールディングから当社株式の取得及び業務提携に関する非公式な打診を受け、リロ・ホールディングとの間で、両社の業務提携に関する初期的な検討を行っております。このように、当社は、本買付説明書が提出されることを予期していたものですが、その内容について早期かつ前向きに鋭意検討してまいる所存です。
根回しも済んでいたようですね。
それで翌日早速
株式会社リロ・ホールディングとの間の業務提携に関する正式協議の開始及び買付説明書に基づく当社株式買付けに対する対抗措置の不発動の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本買付説明書の内容に関し慎重な審議を行った結果、
①リロ・ホールディングとの間で業務提携に関する正式協議を開始することとし、・・・「業務提携に関する基本合意書」(以下「本基本合意書」といいます)を締結すること
②本買付説明書に記載された内容のリロ・ホールディングによる当社株式の取得・・・については、本プランに基づく対抗措置の発動を行わないこと
を決議いたしました
お家騒動の相方のカテリーナイノウエもいなくなって万々歳、ということでしょう。
1.本買付説明書の受領及び本決定に至る経緯について
リロ・ホールディングは、平成20年10月中旬ころから、株式会社原弘産、井上投資株式会社及び株式会社カテリーナ・イノウエ・・・との間で、本売主の保有する当社株式の全部(合計3,977,000株・当社の発行済株式数の約27.09%。・・・)の譲受けに関する協議・交渉を行っておりました。一方、リロ・ホールディングは、当社に対し、当社との業務提携に関する非公式な打診を行っておりました。そして、当社とリロ・ホールディングは、両社の業務提携が各社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資することとなるかを初期的に検討するため、協議を行ってまいりました。・・・その結果、当社は、リロ・ホールディングとの間の業務提携の実現のため正式な協議・検討を開始することは、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資する可能性が高いと考えるに至りました。
2番目のリリースでは業務提携の打診は株式取得より前ではなかったようなので業務提携の協議も「平成20年10月中旬ころ」からだったわけで、10日あまりで決断したわけです。
原弘産からの買収への対応と比べると電光石火の意思決定といえましょう。
取締役会での「慎重な審議」の内容に興味があります。
このリリースの別紙1として「リロ・ホールディングが当社の関係会社となること及び本業務提携に関する当社の考え方」というのがついてますが、原弘産の買収への反対意見の裏返し以上のものではありません。
結局最初から最後まで、なんだかなぁ、という感じがつきまとった案件ではありました。
カテリーナイノウエとしては出口が見つかってよかった、ということなんでしょうが、株価の動きを見るとほかの株主はあまり喜んでいないようです。(参照、またリロへの売却協議が始まったとされる10月中旬以降の株価が高値で張り付いていることについてはこちらをご参照。でも、買い続けていた合人舎はどうするんでしょうね。将来的には経営権争いが再発すると見てキャスティングボートを持っておこうということでしょうか。はたまた裏約束?)