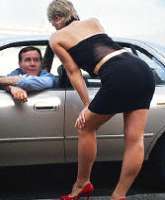邦題は
『ウォール街アナリスト物語 - ネットバブルからの生還』という平凡な書名と陳腐な副題がついていますがとても面白い本でした。
原題は"Wall Street Meat: Jack Grubman, Frank Quattrone, Mary Meeker, Henry Blodget and Me"で、原題に出てくる3人は、ワールドコムの問題以降顕在化した証券アナリストの利益相反問題で罪に問われたスターアナリストです。
著者はATTのベル研究所の技術者からITアナリストとしてペイン・ウエバー証券に雇われ、その後モルガン・スタンレーに転職するなかで、くしくも3人とともに仕事をしながら、1980年代後半から90年代にかけて証券会社が投資銀行業務に傾斜していく中でアナリストの仕事が中立性を失い、投資銀行業務のサポートをするようになっていき、ネットバブルの際にそれが頂点に達したあと2000年に崩壊するまでの様子を描いています。
もともと証券会社は顧客からの注文を取り次ぐだけでなく取引相手のいない場合には自らがポジションを取ることで市場に流動性を供給し、そのトレーディング手数料が収益源になっていました。
ところが1987年のブラックマンデーの際に殺到する売り注文の中、証券会社のトレーダーが電話に出るのをやめてしまったことが契機になり、SECは小口注文処理システムを導入し、千株未満の注文は時価で自動処理されるようになりました。
これに目をつけたプログラマーがこのシステムを悪用し、小口の注文を何百回にも分けて自動的に行い、証券会社のトレーダーを狙い撃ちにする(これが出イーとレーダーのはしり)ということがおき、これを避けるためにトレーダー同士は大口注文を通すために証券会社同士のバイパスを作るようになりました。
このバイパスが1996年の大規模な暴落につながり、証券会社のトレーダーたちが一般投資家のマーケットへのアクセスを阻害しているという集団訴訟「ナスダック・マーケットメーカー反トラスト訴訟」が提起され(証券会社としてはデイトレーダーの攻撃を「阻害」したのは事実なので)ウォール街は10億ドルで和解しました。
この結果コンピューターによる注文のマッチングシステムにお墨付きが与えられ、証券会社のトレーディングのシェアがさがり手数料(利ざや)も低くなってしまいました。
その結果証券会社はIPO(新規公開)などの投資銀行業務を収益源とするようになり、アナリストの役割も新規公開株の公開後の価格維持・上昇をサポートすることに変質して行きます。
ちょうどそこに(またはそれをひとつのきっかけとして)ネットバブルが起き、投資家は新規公開株の割当てを受けるために証券会社に手数料を落とし(それは不正なキックバックです)スターアナリストは株を推奨する預言者になってしまいました。
そこにネットバブルの崩壊、ワールドコム問題などが起き、出世欲に燃える無名のニューヨーク州司法長官スピッツァーがスターアナリストの3人を標的に訴追をし(結果的にメアリー・ミーカーは訴追を免れる)、彼らは一転してすべての張本人とされてしまいます。
この本を読んで思うのは、今や日本でも盛んになっているネットでの証券取引などはアメリカでもたかだか10年前に始まったもので、ただいちど出来上がった仕組みを導入するのは簡単なので、だんだん時差がなくなっていく、ということです。
しかし一方で上のような、そのしくみの導入に至る経緯は逆に圧縮した形で現れるわけでそれが混乱を増幅することになります。
それはデイトレーダーや先般の急激な円高におけるFX(外国為替証拠金取引)を利用している個人のパニックとか、「J-Sox」の導入への対応に大わらわな企業とか、もっと広げれば中国の公害問題などもその一種ですね。
これを「個体発生は系統発生を繰り返す」と見るのか、
「歴史は繰り返す、ただし二度目は茶番」と見るのかはその人のスタンスによると思います。
また、そういう出来合いの制度を導入した場合の混乱はビジネスチャンスでもありますが、「混乱の後にも十分耐えうるような先進的なビジネスモデルを作ろう」とするのか「導入元ではもう禁止されてしまった抜け道がまだ違法とされならないうちに荒稼ぎしよう」とするのか、というのも、スタンスの問題ですね(往々にして全社はあまり儲からず、後者は短期的にはすごく儲かったりするところが悩ましいところなのですが・・・)。
PS
トレーディング手数料の減収を補うもうひとつの収入源がデリバティブ商品の提供でした。つまり、商品の仕組みを複雑にして、商品の価格の中にこっそり(かつがっぽり)手数料を忍ばせるというやりかたです。
こちらはサブプライムローンを組み込んだCDSなどに正常進化をとげて、これまたお茶の間を騒がせていますね・・・