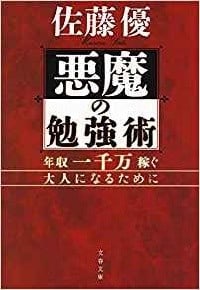「柿渋色」は、晩秋を思わせる味わい深い赤茶色だ。平安時代からある色だが、江戸時代からは歌舞伎役者の市川團十郎が用いて、「団十郎茶」とも呼ばれている。今も、襲名披露の口上などでは、一門が必ずこの色の裃(かみしも)を着けるのでおなじみだろう。
この色のもとである柿渋液は、意外なことに熟れた赤い柿の実ではなく、まだ色づく前の未熟な青い柿の実を絞って作るそうだ。この液を熟成させ、さらに、日光に当てながら何度も重ね塗りすることで、深みのあるこげ茶にすることができる。
日本の伝統色は、中世には十二単(じゅうにひとえ)のような色を重ね合わせた着物を着たり、婆娑羅(ばさら)や、風流といった派手なオシャレを楽しんだりする風潮があって鮮やかな色彩が発展した。
一方、江戸時代になると、幕府の「奢侈(しゃし)禁止令」によって、農民から武士まですべての階級で華美な服装を禁じたので、茶色やねずみ色などの中間色が流行した。柿渋色はその渋さゆえに、江戸時代に好まれたのだ。
□南雲つぐみ(医学ライター)「柿渋色 ~歳々元気~」(「日本海新聞」 2017年11月21日)を引用
↓クリック、プリーズ。↓



この色のもとである柿渋液は、意外なことに熟れた赤い柿の実ではなく、まだ色づく前の未熟な青い柿の実を絞って作るそうだ。この液を熟成させ、さらに、日光に当てながら何度も重ね塗りすることで、深みのあるこげ茶にすることができる。
日本の伝統色は、中世には十二単(じゅうにひとえ)のような色を重ね合わせた着物を着たり、婆娑羅(ばさら)や、風流といった派手なオシャレを楽しんだりする風潮があって鮮やかな色彩が発展した。
一方、江戸時代になると、幕府の「奢侈(しゃし)禁止令」によって、農民から武士まですべての階級で華美な服装を禁じたので、茶色やねずみ色などの中間色が流行した。柿渋色はその渋さゆえに、江戸時代に好まれたのだ。
□南雲つぐみ(医学ライター)「柿渋色 ~歳々元気~」(「日本海新聞」 2017年11月21日)を引用
↓クリック、プリーズ。↓