飛行の生命線とも言える揚力がどうやって発生するかということはまたの話として、揚力の計算式を先に書き出して、少し説明します。
L=CL×1/2×ρ×V×V×S

PC入力では分数や二乗の文字が出せないので不便ですが、L(揚力)=CL(シーエル・揚力係数)×2分の1×ρ(ロー・大気密度)×V(Velocity・速度)の2乗×S(Surface・翼面積)と読んでください。
つまり、どんな飛行翼でも、揚力は揚力係数というその翼特有の飛行性能を表す数値、大気密度、対気速度、翼面積で決まるということになります。
揚力係数は飛行翼の形状と迎え角で決まりますが、これについてはまた後ほど。大気密度は気圧と温度と湿度で決まります。速度と翼面積はどういうこともありませんね。揚力Lはこの4つの要素で決まるわけで、それぞれの値が大きいほど大きくなるということになります。対気速度は2乗されるから影響が大きいのもこれで良く分かるよね。
これを押さえた上で、次は抗力ですが、これを求める式は D=Cd×1/2×ρ×V×V×S です。Cdは抗力係数といって、揚力係数と全く同じように飛行翼の形状と迎え角で決まります。
揚力と抗力を並べてみましょう。
L=CL×1/2×ρ×V×V×S
D=Cd×1/2×ρ×V×V×S
一目瞭然で、揚力も抗力もそれぞれの係数の他は、全部同じ要素で決まるということが分かります。つまり大気密度の増減に応じて同じように揚力も抗力も増減するので、揚抗比(L/D)=滑空比は大気密度の変化(高度や温度や湿度)に関係しないということになります。
L=CL×1/2×ρ×V×V×S

PC入力では分数や二乗の文字が出せないので不便ですが、L(揚力)=CL(シーエル・揚力係数)×2分の1×ρ(ロー・大気密度)×V(Velocity・速度)の2乗×S(Surface・翼面積)と読んでください。
つまり、どんな飛行翼でも、揚力は揚力係数というその翼特有の飛行性能を表す数値、大気密度、対気速度、翼面積で決まるということになります。
揚力係数は飛行翼の形状と迎え角で決まりますが、これについてはまた後ほど。大気密度は気圧と温度と湿度で決まります。速度と翼面積はどういうこともありませんね。揚力Lはこの4つの要素で決まるわけで、それぞれの値が大きいほど大きくなるということになります。対気速度は2乗されるから影響が大きいのもこれで良く分かるよね。
これを押さえた上で、次は抗力ですが、これを求める式は D=Cd×1/2×ρ×V×V×S です。Cdは抗力係数といって、揚力係数と全く同じように飛行翼の形状と迎え角で決まります。
揚力と抗力を並べてみましょう。
L=CL×1/2×ρ×V×V×S
D=Cd×1/2×ρ×V×V×S
一目瞭然で、揚力も抗力もそれぞれの係数の他は、全部同じ要素で決まるということが分かります。つまり大気密度の増減に応じて同じように揚力も抗力も増減するので、揚抗比(L/D)=滑空比は大気密度の変化(高度や温度や湿度)に関係しないということになります。










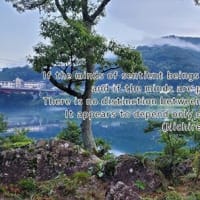
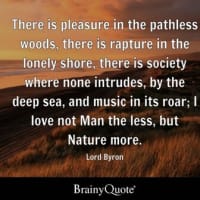
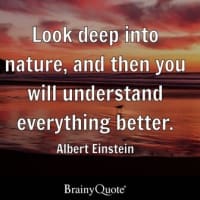







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます