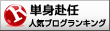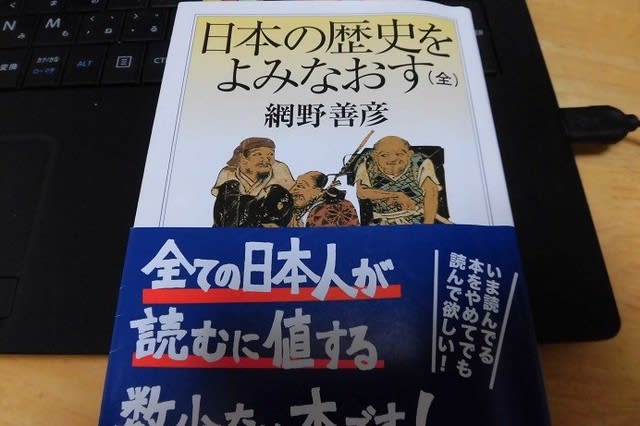
最近 三浦先生のリベラルアーツセミナーにでて歴史学者の網野善彦さんと民俗学者の宮本常一さんは
ほんとの日本の姿を知るにはといわれたので、読んでいる。
網野善彦の日本の歴史の分析はすばらしい、一体われわれは教科書でなにをならってきたのだろうかと思う。
内容は 1貨幣と商業 金融 2畏怖と賤視・・・古代の差別、悲田院の人々 けがれの問題 の出現
・・・東日本と西日本の違い(これに関しては自分も関東にきてからびっくりはしました)
3女性をめぐって 4天皇と日本の称号 これは目から鱗 天皇の称号は天武 持統から 推古天皇あたりからと
思っていましたが随分あと700年ごろから天皇の称号になった そして日本国という称号もあくまで大和を中心とした
畿内をおさめる国の称号であったので、九州 東北 北海道 沖縄は違う国家民族であったということです。
あほの女性歌手が前のサッカー応援で混じりけのない青い血とほざいていた、お笑いもの・・一体当時の純粋たる
大和民族は日本の何パーセントいるのであろうか?0.0001%てなところかもしれない。
大いなる誤解がある統一国家としての天皇ではなかったということを知らない人が多すぎる。
5日本の社会は農業社会か? これも目から鱗・・ 6海からみた日本列島 西と東の文化の差
DNAの分析すると西日本に住んでいる人たちと朝鮮半島に住んでる人たちとかなり濃い類似性があるのがわかっている
そして東日本に住む人たちとはアイヌ人に近く 同じ日本で大きく異なるということ。
もともと国の形としては東日本と西日本はまったく別物であったと考えるのが適切だとおもわれる。
7荘園 公領の世界 8悪党海賊と商人 金融業者 9日本の社会を考え直す。
おもしろい!今まで読んだ歴史の本なんぞ足元におよばない先生の歴史はスケールが大きい
西と東の衝突という部分では長野県の諏訪大社がその歴史がいわれている 諏訪の山の民狩猟民族 に
弥生の農耕文化が入り込み 両方で争いになったのを静めたのが諏訪大社の成り立ちともいわれている。
このスケール感をみれば明治維新賛美の小説はやはり小説事実ではなくスケールも小さいように思える。