


『愛と哀しみのボレロ』
1992年11月30日にジョルジュ・ドンが亡くなって早くも23年、まだ45歳の現役バレエダンサーでした。
ロシア移民の子としてアルゼンチンで育ち、16歳の時に観たベジャール・バレエに魅せられて押しかけ弟子入り
19歳『ロミオとジュリエット』でロミオを踊って好評を得た後は、次々とベジャールバレエ団の主役を演じました。
代表作は、ラヴェル作曲・ベジャール振り付けの『ボレロ』、それまでは女性ダンサーが踊っていたメロディ役を
初めて男性ダンサーが演じたことで知られています。その衝撃的な踊りに触発されたクロード・ルルーシュ監督が
1981年に映画 『愛と哀しみのボレロ』
 を制作し、一躍バレエ・ファン以外にも名を知られるようになりました。
を制作し、一躍バレエ・ファン以外にも名を知られるようになりました。映画は第二次世界大戦から1960年代にわたり、フランス、アメリカ、ロシア、ドイツに於いて交錯する、2世代の
4家族を描く壮大な人生ドラマでした。ルルーシュ監督がイメージした4人の実在人物のうち、ルドルフ・ヌレエフを
演じたのが、J・ドンでした。映画の中盤で踊るベートーヴェン交響曲も素晴らしいですが、圧巻はラスト遥か遠くに
エッフェル塔を望むシャイヨー宮のテラスで踊る12分間の『ボレロ』。
この映画でドンやヌレエフを知り、ネット動画やDVDでロシアバレエの魅力に嵌ったKimitsuku。現在はファルフ・
ルジマトフに耽溺中







この『ボレロ』を始めとして、『アダージェット』や『ニジンスキー』などレパートリーを共有するルジマトフのバレエに
亡きジョルジュ・ドンを偲んでいます。













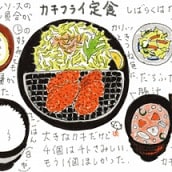


 )の「人生が見えてくる…」
)の「人生が見えてくる…」




 」お礼を言うと、「アリガトウ」と上手な日本語が返ってきました。「素敵でした
」お礼を言うと、「アリガトウ」と上手な日本語が返ってきました。「素敵でした












 トリオ・ラファール
トリオ・ラファール


