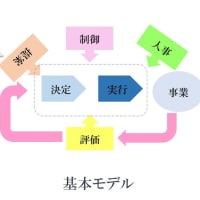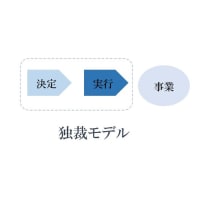第二次世界大戦末期にあって、核分裂から生じる膨大なエネルギーを破壊力として用いる核兵器の開発は、連合国側であれ、枢軸国側であれ、戦争当事国の至上命題でもありました。同兵器を手にした側が、圧倒的に有利になることが予測されたからです。戦局の悪化で追い詰められていた日本国もまた、同兵器の開発に一縷の望みを抱いていたのです。戦争末期の核兵器開発競争は、結局、ナチスによる迫害を逃れてアメリカに渡ってきた科学者達の貢献もあって、アメリカの勝利に終わります。そしてそれは、第二次世界大戦における連合国の勝利をも意味したのです。
かくして第二次世界大戦は、アメリカによる核兵器の開発成功に終わるのですが、核兵器の存在は、その後、国際社会に多大なる影響を与えることになります。しかしながら、核兵器とは、そもそも国際法違反となる都市空爆を前提として開発されたとしか考えざるを得ません。実際に、アメリカは、広島並びに長崎のみならず、日本国内の複数の都市を攻撃対象リストに挙げていました。核兵器は、少なくともアメリカでは、最初から違法行為となる民間人の大量殺戮用の兵器として開発されているのです。この点を考慮しますと、核兵器の使用を正当化しようとすれば、誰もが納得するような違法阻却事由を示さなければならない、ということになりましょう。
そして、今日、違法阻却事由の一つとして提起されているのが、日本国側による核兵器開発の事実です。核兵器の使用の違法性を糾弾されているアメリカからすれば、‘日本国も同じことをしようとしたではないか’ということになります。この主張は、正当防衛や緊急避難の根拠ともなり得ますし、被爆国である日本側としましても、正直に申しますと‘痛いところ’ではあります。しかしながら、この指摘を正面から受け止め、考察・検証を加えますと、核が第三次世界大戦から人類を救ったとする核の抑止力の評価による原爆投下正当化論の問題も、核廃絶運動やNPT体制をめぐる今日的な問題も見えてくるように思えます。
そこで、先ず考えるべきは、戦争末期にあって核兵器開発競争をめぐっては、およそ3つの可能性があった点です。その三つの可能性とは、(1)アメリカ一国が先に開発し、核兵器を保有するケース、(2)日本国側が先に開発に成功し、日本国のみが保有するケース、そして、(3)日米が共に同時期に開発に成功し、両国が共に核兵器を保有するケースです。現実の歴史は、第一のケースとなったのですが、それでは、仮に第二と第三のケースでは、核をめぐる議論はどのような展開となったのでしょうか。
古来、兵器の性能は戦争の行方を左右しますので、仮に、第二のケースとして、日本国側が核兵器を先に開発した場合、日本国は、アメリカに対して軍事的に優位な立場を得ることとなります。もっとも、実際にそれを使用できたかどうかについては怪しく、核兵器の使用を想定した潜水艦の開発を急いだとしても、同兵器の運搬手段については疑問が残ります。しかしながら、核兵器を保有しながら大陸間弾道ミサイルの開発には至っていない今日の北朝鮮の立場と同じく、アメリカに対して武力攻撃を控えさせる効果は得られたかも知れません。つまり、日本国の場合、核兵器を開発したとしても、実際にアメリカの都市に対して使用するよりも、抑止力として用いた可能性の方が高いように思えます。おそらく、アメリカが実行した無慈悲な対日空爆作戦も回避されたことでしょうし、終戦交渉を開始するに際しても、連合国側をテーブルの席につかせ、講和交渉を優位に進めることができたことでしょう。
それでもなおも、日本国による対米原爆投下の正当化論として、保有のみならず、日本国による核兵器の使用という緊急の危機があったと主張するならば、むしろ同論者は、日本国による原爆投下をも正当化せざるを得なくなります。核兵器による甚大なる人的物的・被害が‘見せしめ’となって、その後の人類を救ったとする論理構成からすれば、‘見せしめ’は、ニューヨークであれ、ワシントンD.C.であれ、あるいは、ロンドンであれ、新型兵器の犠牲となる都市はどこでも構わないことになるからです。
なお、原爆の投下を、‘強欲な侵略国家日本国の当然の報い’と見なしたり、‘自由と民主主義を護るためには必要であった’とする違法阻却事由の主張も、人類史上最初の使用による‘見せしめ’効果だけを取り上げれば、説得力を失います。(なお、植民地支配が横行していた当時の世界情勢からすれば、日本国が‘邪悪な国’であったとは言えないのでは・・・)。邪悪な国家による核の独占とその使用も、あり得ないわけではないのです。仮にこうした状況に至った場合には、非核保有国は、核独占国によって常に脅迫されるか、あるいは、実際に戦争を仕掛けられるかもしれません(核保有国の必勝状態・・・)。科学技術のレベルは倫理観とは無関係ですので、新型兵器の開発競争は、‘邪悪な国’が唯一の保有国となる場合もあり得るという問題をも提起しているのです。そしてこの問題は、今日における問いかけともなるのです(つづく)。