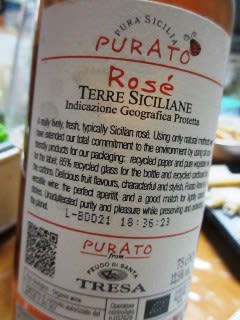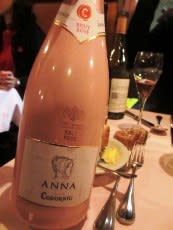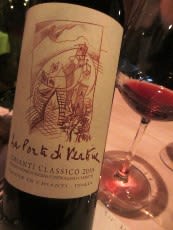イタリアのピエモンテ州といえば、ネッビオーロ種からつくられるバローロやバルバレスコの赤ワインがとても有名ですが、この同じ州で、
ネッビオーロでつくられる別の赤ワイン“ガッティナーラ Gattinara”のことを知っている人は、よほどのワイン通でしょう。
ガッティナーラ はDOCD名ですが、そもそもは村の名前です。
ピエモンテ州の北東部ヴェルチェッリ県にあり、バローロやバルバレスコよりもずっと北です。
“ネッビオーロ”は、ガッティナーラでは
“スパンナ Spanna”と呼ばれます。
今回は、このガッティナーラの生産者として一目置かれる
「トラヴァリーニ TRAVAGLINI」から、輸出マネージャーのアレッサンドロ氏が昨年秋に来日した際のメーカーズディナーのリポートをお届けします。

イタリアのワインガイド“Gambero Rosso”は、
「トラヴァリーニはガッティナーラのネッビオーロを語る時に避けては通れない重要な生産者」と記しています。
 一度見たら忘れられない特徴的な形のボトル
一度見たら忘れられない特徴的な形のボトルが印象的ですが、この形には意味があるのだとか。

ボトルのお腹を下にして置くと(ご覧のように、テーブルの上で転がることはありません)、オリがお腹の下に自然に溜まるので、デカンタージュをする必要なく、このままグラスに注ぐことができます。
実際に目の前にして、たしかに!と納得しました。
トラヴァリーニは100年以上続く家族経営の造り手で、現在4代目になりますが、このユニークなボトルデザインは1958年から採用されています。
ボトルにオリが溜まるということは、長期熟成を見越したワインということで、
アレッサンドロ氏も
「トラヴァリーニは熟成能力のあるワイン」と言います。

アレッサンドロ氏 Travaligni Export Manager

トラヴァリーニでは、昔から
ネッビオーロ種の赤ワインのみを生産してきました。
主力ワインは、もちろん“DOCGガッティナーラ”ですが、DOCG以外のランナップもあり、今回は色々と飲み比べをさせていただきました。
 Gattinara 2009 Travaglini
Gattinara 2009 Travaglini (Italy, Piedmonte)
毎年つくられるベーシックなガッティナーラで、2009年は、スラヴォニア産オーク樽で2年、瓶熟1年、合計3年熟成させています。
アルコールは13.5%と控えめで、エレガントなスタイルを心がけているといいます。
飲んでみると、ジューシーさがありながら、タンニンがキュキュッと小気味よく、キレイな味わいでした。バランスがいいので、幅広い料理に合わせられると思います。

そもそも、
ガッティナーラの産地はアルプスに近い北部に位置し、アルプスの影響を大きく受ける土地です。土壌は火山灰が多く見られます。
アルプスから吹き下ろす風が畑を通り過ぎて行くので、湿気がこもらず、病虫害対策にいい結果をもらたします。
また、標高の高い山が近くにあり、標高が高い丘陵地帯ですので、昼は日照に恵まれ、夜はグッと冷え込みます。この大きな昼夜の温度格差により、よく熟しながらもキレイな酸を保った良質なブドウが得られます。
ですから、ガッティナーラを飲むと、同じネッビオーロであるのに、バローロやバルバレスコと違い、
より繊細さ、涼やかさ、エレガントさを感じます。とはいっても、
芯がしっかり通り、凛としています。
料理も、ガツンとパワフルなものよりも、少し繊細さを感じるもの、どこかしらシンプルさを残したものが合うように思います。

なお、
トラヴァリーニでは、単一畑ではつくらず、色々な畑の良さを取り入れてブレンドするワインづくりをコンセプトとしています。
また、大樽で熟成させ、
ミネラル豊富で、酸がほどよいワインを特徴としています。
 Gattinara Reserva 2008/ 2007 / 2004 Travaglini
Gattinara Reserva 2008/ 2007 / 2004 Travaglini (Italy, Piedmonte)
リゼルヴァは良年のみ生産される特別キュヴェ。
ブドウの樹齢は40~70年になるとか。
スラヴォニア産オーク樽と小樽で最低3年熟成させ、さらに1年瓶熟させています。
今回は3つの年の飲み比べをしました。
「リゼルヴァはストラクチャーのあるワイン。トラヴァリーニは小さなワイナリーだけれど、それでもヴィンテージによって個性が出てくるので、その違いを見てほしい」とアレッサンドロ氏。
2004:春らしく、夏は暑く、冬は寒い、完璧な年。
2007:暑めの年。リゼルヴァを造りにくい傾向の状況ながら、造る価値があると判断。
2008:寒い年で、生産量も少量。
飲んでみると、
2008年は、まだ全然若々しく
2007年は、まろやかで飲みやすく、チャーミングで、肉とよく合う
2004年は、緻密でカドが取れ、複雑味あり、トリュフなどにピッタリ
アレッサンドロ氏は、この中で一番古い
2004年にもまだ若さ、フレッシュ感があり、後20~30年はおいしく飲める、と言っていました。
ガッティナーラ以外では、2つの赤ワインがありました。


左)
CINZIA 右)
IL Songo 2008 Travaglini (Italy, Piedmonte)
チンツィアはオーナーの名前を冠したヴィーノ・ダ・ターボラで、ネッビオーロ、ボナルダ、ヴェスポリーナのブレンド。ステンレスタンクのみで熟成を行なっています。
味わいはフルーティーで、軽やかさがあり、スーッと入ってきますが、ミネラリーです。まろやかで、果実の甘みがあり、フルーツの豊かさを感じます。
アレッサンドロ氏は、赤ワインだけれど、魚にも合うと言っていました。
イル・ソンゴはネッビオーロ100%のIGTワインで、高い標高の畑のブドウを使い、収穫後は約100日間陰干しをしています。
熟成はスラヴォニア産オーク樽(20L)で40カ月、瓶詰してから8カ月。
糖度の高いアマローネ的なワインで、アルコールは15.5%、
3500本のみの限定品です。
アロマが豊かで、味わいは甘美。スイーツやうま味の乗ったチーズなどにピッタリ。
Songoは“夢”という意味だそうですよ。
赤ワインだけをつくってきたトラヴァリーニですが、
ネッビオーロから白のスパークリングワインを造り始めました。
 Nebole 2010 Metodo Classico Extra Brut Travaglini
Nebole 2010 Metodo Classico Extra Brut Travaglini (Italy, Piedmonte)
シャンパーニュでも黒ブドウから白の発泡ワインをつくりますから、よく考えれば不思議なことでもないんですが、ネッビオーロからというのが面白いですよね。
トラヴァリーニでは、ネッビオーロの収穫を10月初旬に行ないますが、このスパークリング用のネッビオーロは、9月中旬に房の先だけを摘んでいます。
収穫を早くすることで、酸がしっかりとしてバランスの取れたスパークリングワインになります。
シャンパーニュと同じ
瓶内二次熟成で、期間は48カ月。かなり長いですね。
飲むと、酸がしっかりと残り、みずみずしくフレッシュ!
この2010年が初ヴィンテージです。
生産量はさらに少なく、わずか
1950本のみの超限定品。
姿も洗練されているので、フォーマルなシーンでも活躍してくれそうです。

これらの素晴らしいトラヴァリーニのワインに合わせたのは、
ローマ出身のフランコシェフが腕を振るう
Trattoria「Il FORNELLO」(イル・フォルネッロ)のスペシャルなコース料理。
 リンゴのクロッカンテとゴルゴンゾーラのファゴッティーノ
リンゴのクロッカンテとゴルゴンゾーラのファゴッティーノ
パリパリの食感のリンゴが楽しい♪
これをつまみながら、スパークリングワインと合わせて。
 マグロのタルターラ オーリオノヴェッロとリモーネの薫り
マグロのタルターラ オーリオノヴェッロとリモーネの薫り
フレッシュなオリーブオイルのヌーヴォーを使ったマグロのタルタルに、フレッシュな赤ワイン“チンツィア”。オリーブオイルがいい“つなぎ役”になってくれています。
 ウズラとポルチーニ茸のトルテッリ スーゴディカルネのソース
ウズラとポルチーニ茸のトルテッリ スーゴディカルネのソース
こっくりとしたソースのパスタで、トルテッリもソースもおいしい!
ベーシックなガッティナーラと合わせました。
 タッレッジョとガッティナーラワインのリゾット “トラヴァリーニ風”
タッレッジョとガッティナーラワインのリゾット “トラヴァリーニ風”
ガッティナーラは米の産地でもあるらしく、リゾットは名物のひとつだとか。
リゼルヴァの中で一番若く、酸味のしっかりした2008年と。
 蝦夷鹿のロースト マルサラとトリュフのソース
蝦夷鹿のロースト マルサラとトリュフのソース
力のあるメイン!しかも、ボリュームたっぷり!トリュフたっぷりも最高!
リゼルヴァの2007年、2004年と。まろやかでコクがあるタイプ、熟成の進んだものが合いますね。
 栗のトルタとジャンドゥイアのセミフレッド
栗のトルタとジャンドゥイアのセミフレッド
甘さ控えめながら、ほっこりした栗のトルタと、濃密なセミフレッドに合わせた“イル・ソンゴ”が夢の世界へと誘ってくれました。

ワインも素晴らしかったですが、料理も素晴らしく、大大大満足のディナーでした。
お世話になった皆さん、ありがとうございました。
今回のトラヴァリーニのワインのうち、一部はすでに日本に輸入されています。
(輸入元:日欧商事株式会社)

最後に紹介した数量限定の
スパークリングワインですが、1950本のうち60本を「Il FORNELLO」で採ったそうです。近いうちに店に登場するそうですから、飲みたい方は要チェック!
「イル・フォルネッロ」は料理がとにかくおいしいですし、よく色々なフェアを開催していますので、インプットしておくとお役立ちの店です。
Trattoria 「Il FORNELLO」 (イル・フォルネッロ)
東京都中野区中野4-7-2 SHビル1F
TEL.03-3387-5210
Facebook
https://www.facebook.com/Trattoriailfornello/










































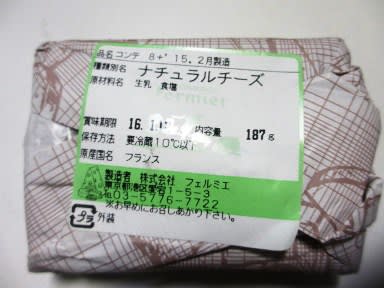























 第一位 KASA (福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第一松村ビル1F)
第一位 KASA (福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第一松村ビル1F)