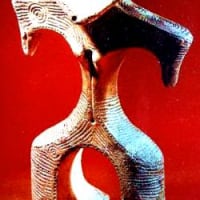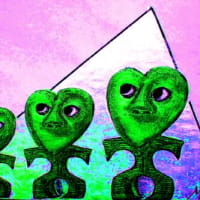かつての東北は貧しく、農家はたくさんの子供をかかえ、産まれてきた子供を育てられないことが多かった、だから、仕方なく処分、これが「間引(まび)き」、どんな手段があったか、
1、濡れた和紙で顔をおおう
2、しりで圧殺
3、真冬 戸外に一晩 放置する
4、山に捨てる
5、川に流す
6、臼の下に置く・・・
6の臼(うす)はあの臼で、先日、博物館に臼があったがブキミな気配なのだ、
「やったな」
「サルカニ合戦」で、臼がサルを懲らしめるシーンがあったと思うが、これには意外な事実があるのかもしれない、泣きわめく我が子の声は、若い母親の胸に、どう響いただろうか、だから、恐山の信仰には、言語を絶した悲しみがあるんだろう、イタコの口を借りて、
「こっちで たのしくやっているよ」
「うっうっうっ」
「だから しんぱいしないでね」
「あーあーあー」
野外に捨てられた子供はどうなったんだろう、かつて日本民俗学の父・柳田国男は、
「世界中に オオカミがヒトの子供を育てたというエピソードがあるが わが国にはない」
おそらく多くの弟子を動員して調べたんだろう、ところが南方熊楠、
「いいかげんなことを 言ってもらってはこまる」
「なにがいいかげんだ」
「いいかげんだからいいかげんなのだ 君は学問に向いていないね」
ワナワナと震える民俗学の権威、スパコン並の頭脳の南方は、
「この古文書のここに ちゃんと記録されているではないか」
その通りだった。