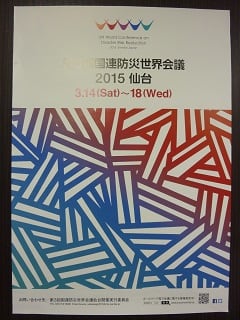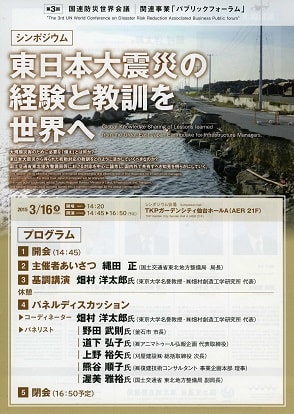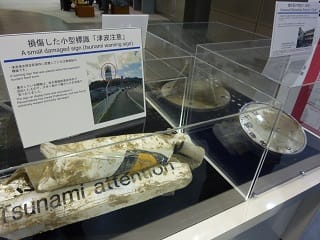■広瀬川の白鳥


今日の仙台は、朝から雨が降っています。
霧雨のような雨で、何となく肌寒さも感じられます。
今日の天気予報は、雨のち曇りで最高気温も10度と余り上がりません。
仙台は梅の花が開花したというニュースが流れていました。
春の足音が聞こえてくる季節になりました。
先日、広瀬川の堤防を歩いてきました。
そろそろ北帰行が始まる白鳥かと思いますが、まだ、広瀬川のほとりに白鳥を見ることができました。
広瀬川の白鳥は、年々、増えているような気がしています。
今年も20数羽の白鳥が飛来していました。
ひところ、鳥のインフルエンザとかで白鳥に餌を与えないで下さいとか近づかないでくださいとか言われていましたが、今では、市民がパンくずをもってきて与えている様子を度々見かけるようになりました。
白鳥に与えているはずの餌が、カモメが横取りをしている様子を見ると何とも腹立たしく思うこともありました。
最近、仙台も暖かい日が続いています。
北帰行も間もなくやってくるのではと思うと、たっぷり栄養補給をして飛び立って欲しいと願わずにはいられませんでした。


今日の仙台は、朝から雨が降っています。
霧雨のような雨で、何となく肌寒さも感じられます。
今日の天気予報は、雨のち曇りで最高気温も10度と余り上がりません。
仙台は梅の花が開花したというニュースが流れていました。
春の足音が聞こえてくる季節になりました。
先日、広瀬川の堤防を歩いてきました。
そろそろ北帰行が始まる白鳥かと思いますが、まだ、広瀬川のほとりに白鳥を見ることができました。
広瀬川の白鳥は、年々、増えているような気がしています。
今年も20数羽の白鳥が飛来していました。
ひところ、鳥のインフルエンザとかで白鳥に餌を与えないで下さいとか近づかないでくださいとか言われていましたが、今では、市民がパンくずをもってきて与えている様子を度々見かけるようになりました。
白鳥に与えているはずの餌が、カモメが横取りをしている様子を見ると何とも腹立たしく思うこともありました。
最近、仙台も暖かい日が続いています。
北帰行も間もなくやってくるのではと思うと、たっぷり栄養補給をして飛び立って欲しいと願わずにはいられませんでした。