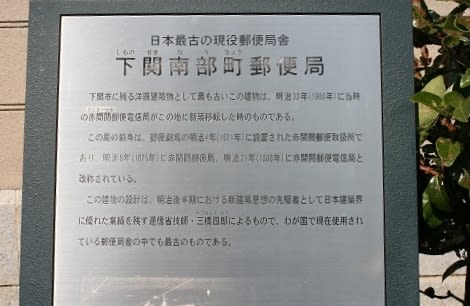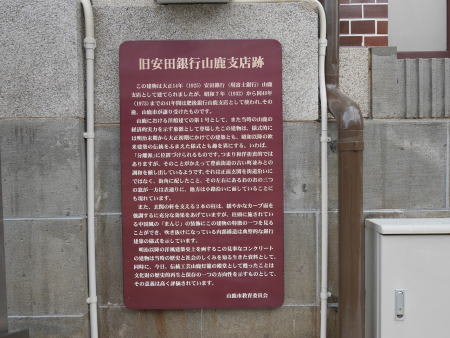海老津赤レンガアーチは、
九州鉄道本線(現在の鹿児島本線)の旧線跡に残る橋梁の遺構である。
九州最初の鉄道会社である九州鉄道は、
1889 ( 明治22 ) 年に
博多駅〜千歳川仮駅 ( 現在の佐賀県鳥栖市 ) 間で開業後、
門司に向かって延伸して翌年に遠賀川駅まで開通した。
海老津赤レンガアーチはこの時に建設されたと思われる。
当初の路線は城山 ( じょうやま ) 峠を越えるルートで通されたが、
急勾配が蒸気機関車には負担だったため、
山を貫通する城山トンネルが建設されて
1909 ( 明治42 ) 年にルートが切り替わり、
峠越えルートは廃止された。
この旧線跡をはっきりと示す遺構は、
海老津赤レンガアーチの他には残っていないようである。
なお、海老津赤レンガアーチとは後年に付けられたものであり、
現役時代の本来の名称は分からない。
住所 : 福岡県遠賀郡岡垣町海老津
竣工 : 1890 ( 明治23 ) 年頃